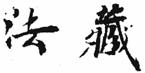|
|
|
|||
|
�^�@��J�h ��e�� |
|
|||
|
�g�b�v�@�����Љ��@�^�@�̋����@�����̊����@�{���Č��@���L�@ �Q�q�̂��ē��i�i��[���E�i��o�j�@�֘A�����N�@��e���Č��ւ̎Q��ɂ��� |
|
|||
|
|
������Ƃ͕\�����邱�� |
|
|
|
|
���� ���Y������ɁA���̉��l�����Ă����|�� �ߔN�A�����^������c���̔�������яo���A�א��҂́u�����v�ɑ���ӎ����_�Ԍ����悤�ŁA���|������o�����B���̍���c���͂���G���i8�����j�Ɋ�e���ALGBT�̐l�����ɑ��āu�ނ�ޏ���͎q�������Ȃ��A�܂�w���Y���x���Ȃ��v�Ƃ��A�����ɐŋ����g���Ă����̂��A�咣���Ă����B���̃C���^�[�l�b�g�̔ԑg�ɂ����Ă����l�̔��������Ă�����ʂ��������A�����Ƃ���ł̓i�`�X�̃z���R�[�X�g�A�n���Z���a���҂ɑ���D����p�A���ݐ��������n�߂���Q�҂ɑ���D����p�A�����āA�_�ސ쌧�̏Ⴊ���Ҏ{�݂ŋN�����E�������Ȃǂ��A�X�̎��������Ōq���ꂽ�o�����Ƃ��ē����悬�����̂ł���BLGBT�Ƃ́A���Y�r�A���i�����������ҁj�A�Q�C�i�j���������ҁj�A�o�C�Z�N�V�����i�������ҁj�A�g�����X�W�F���_�[�i�o���̐��Ǝ��F���鐫�̕s��v�j�̓�������������Z�N�V�����E�}�C�m���e�B�i���I�����ҁj�̐l�X���w�������̂Ƃ����B�X�̎���̍����q�ɁA�u���Y���v�̂���Ȃ�����ɁA���Ƃ��l�Ԃ̉��l�����߂Ă����A���Ƃ��̂��̂�����l�ԓI�ȗ⍓�����f���Ă���Ƃ����v���Ȃ��B�܂�A�u���Y���v����ɂ������l�́A���ƂɂƂ��ď]���ł悭�����u�����v�����A���݉��l������Ƃ���D���v�z���̂��̂������̑I�ʂł����Ȃ��B�������āA�펞���ɂ����Ă͘V�l�A�Ⴊ���ҁA�����A�����đ��������S�~�̂悤�ɎE����Ă����B�u���ɗ��������Ȃ����v�Ƃ����������̓���ӎ����܂߁A�������̎Љ�͂ǂ�����ׂ��Ȃ̂���₢�A���������Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�i�g�j 201�W�^�W�^�P�R |
|
�y�X�V�����z ��2018�N8���R�P���A�b�v���܂����� �i�����2018�N12�����{�A���L�͐����A�b�v�\��ł��j ���N���b�N���@�ŐV�j���[�X�@���N���b�N��
|
���V���[�Y��
�R�����@�@�@�@�@▷�����\�E����̕�◁�@�@ �`�S���搶�ɋ�����ꂽ�w���Y���x�` |
|
8��3��(���j���͋v���Ԃ�ɂ�����K�˂��B �����āA�����O�킪�q�ɓ˂�����ꂽ�u�}�}�ɂ͕�����Ȃ���v�̈Ӗ����l���Ă����B �@�i�����\�E�j |
|
���A���̂������Ȃ����Ă��� �]�^�@��J�h�E�@�c�e�a���l���S�\��䉓���e�[�}�] |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
�@�@�@�@ |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
�@�@�@�@ |
|
|
|
||
���N���b�N������������
|
���z���̖{�����ɏ���ꂽ�㓏���� �������� 2005�N10��23�� |
��e���{�� 2006�N7��10������ |
|
�㓏���̂�������̒����ɂЂƍۑ傫�ȁu�얳����ɕ��v�̊|�������u����Ă��܂��i������A�ʐ^�j�B���̊|���́A���������ɂ������A��l�̂���k�i�̐l�j���炢�����������́B���̂���k�͕s���R�ȑ̂������Ď���K�ˁA�u�킽���Ⴀ�A�e�a���l�̔O���̋����ł˂A������˂��v�Ə�X����ĉ������܂����B���U��ʂ��ĔO���ɐ�����ꂽ����k�̂��p���v�������ׂȂ���A��b�@�v�E�㓏�����߂����Ă������������������������܂��B�i�g�j�@�@�@�N���b�N ���@�@�{���Č��ւ̋O���@�@�A��e���Č��ւ̎Q��ɂ��� |
|
|
��HP�u�@���v�J�݂ɂ������ā� �}���ɕω�����Љ�A�����l�ԊW �u�Љ�v�Ƃ������̐��Ԃɉ����Ԃ���Ă����悤�Ȋ��o��� �ǂ�����Ƃ��Ȃ������Ă���A�����邱�Ƃ̐S�ׂ��E�s���̒��� �������A�킽�������� �����邱�Ƃ́e���o�f������ �e�\���f�Ƃ������̂������Ă��܂������ �ᐶ����Ƃ͕\�����邱�Ɓ� �������V�O�O�N�O�A�l�Ԃ̐[���߂��݂Ƌ�Y�Ɍ��������� ��l�̕��ҁE�e�a���l �e�a���l�̂��Ƃ�����X�̏����Ȃ�������Љ�Ɍ����Ĕ��M���܂� �����������S�ɏ��������߂����߂ɥ�� �l���l�Ƃ��Đ����邱�Ƃ́�\��������邽�߂ɥ�� �i2006�N7��15���j |
|
e-mail�@ jyoyoji@yahoo.co.jp �^�@��J�h ��e���@�Q�q�W |
���L���E�ʐ^�̖��f�]�ڂ��ւ��܂��B