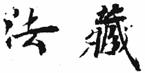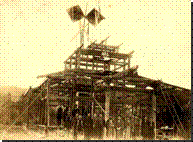|
|
|
真宗大谷派 浄影寺 |
|
参拝のご案内(永代納骨・永代経) 関連リンク 浄影寺再建への参画について |
|
本堂再建への軌跡 |
|
本堂落成慶讃法要 ‐本堂再建から浄影寺再興へ‐ 表 白 信楽山・浄影寺の本堂落成慶讃法要にあたり、本尊・阿弥陀如来並びに三世十方の諸仏如来に申し上げます。 顧みれば、浄影寺旧本堂は、一九二五(大正十四)年に村田町・願勝寺の本堂を当地に「願勝寺支院」として移築したのが始まりでした。寺号の由来を思うに、一六八八年、一人の念仏者・釋宗玄師が仙台市南鍛冶町に坊舎・円乗坊を建立、明治初頭に「浄影寺」と寺号を改めました。併しながら、時を経て荒廃、一九三七年、願勝寺衆徒の釋随恵師が弥陀の勝縁あって仙台・浄影寺の住職となるも、仙台空襲による焼失のため再建叶わず、一九四五年、当地に寺地移転、「願勝寺支院」を「浄影寺」として改め、本願念仏の教法の宣布に尽力されたのであります。 そして、時代は移り、浄影寺の旧本堂は自然の摂理に順ずるように、老朽していきました。そこで、浄影寺総代初め役員一同、親鸞聖人の教えを宣布する道場を再建せんとの志願を立て、新しく本堂を建立、浄影寺を再建するに至ったのであります。 本日、茲に、本堂落成慶讃法要を厳修するにあたり、本願流伝の歴史への参画に心新たに、有縁の同行とお迎えできることは、偏に如来のご恩徳に他なりません。 二○一一年にお迎えする宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌に思い向けて、真宗興隆に尽力することをここにお誓い申し上げます。 信楽山・浄影寺第二世住職 釋広度、敬つて申す。 (二〇〇六年十一月五日) |
|
|
|
|||
|
浄影寺再建 2006年11月5日
|
|
|||
|
|
|
|||
|
本堂落成慶讃法要勤修‐本尊に浄影寺再興誓う‐ |
||||
|
晩秋の2006年11月5日、本堂の落慶を迎えることができました。この本堂再建は、建設計画が持ち上がってから8年の年月が経つ、まさに浄影寺門徒にとって悲願でありました。この間、役員を初めご門徒や門徒外から多くのご支援を頂きましたこと、厚く御礼を申し上げます。 さて、落慶法要当日をダイジェストに纏めてみました。 |
|||||
|
◇受付
午前8時半、受付開始。受付では旧本堂の柱を加工した念珠などが入った記念品と炊き立ての赤飯をお渡ししました。 【受付の様子】 |
|
【喚鐘を叩いて法要開始】 午前10時、喚鐘の音で法要開始が知らされると、本堂内に雅楽の音色が鳴り響き、本山(東本願寺)代行の陵木文道仙台教務所長、仙南組内の各寺院住職など法中(ほっちゅう)が出仕、最後に七条袈裟を身に纏った住職がゆっくり出仕・着座し、式事を含めた法中16人で法要が始まりま 合掌が解かれ伽陀(かだ)が発声されると、住職は本尊正面に進み、中央の高座に着座、焼香し「表白(ひょうびゃく)」を読み上げ、ご本尊に浄影寺再建と真宗興隆を誓われました(巻頭参照)。 |
|
続いて、住職の発声で『阿弥陀経』が勤まりました。間もなく、華葩(はな
|
|
|
|
法要後には、大崎市岩出山の浄泉寺住職・赤羽根證信師に記念法話をいただきました。赤羽根さんは浄影寺前住職・隨惠師の思い出を通して真宗における寺院の意味を語りながら、お寺を聞法の場として輝かして欲しいと、話されました。 |
|
◇記念式典 記念式典では、まず住職が挨拶、役員はじめ門徒各位、工事関係者に謝辞を述べ「本堂を親鸞聖人の話が聞ける場として共に歩みたい」と語られました。続いて門徒を代表して |
|
|
|
本堂落成慶讃法要前日の2006年11月4日、当院の役員をはじめ、ご門徒の参詣のもと、落慶法要お逮夜並びに報恩講を厳修しました。当日は、住職の挨拶、勤行の後、親鸞聖人の生涯を纏めた蓮如上人筆の『御俗鈔』を拝読しました。平常とは違い、落慶法要のお飾りで荘厳された本堂の前でお参りしたご門徒からは「厳かで綺麗ですね」との声も寄せられました。 |
|
|
本堂中央にひと際大きく立てられた仏華 |
落慶法要お逮夜並びに報恩講を厳修 |
|
2006年9月19日から20日にかけて搬入された仏具等の安置が終わった後、ご本尊を前で、住職の導師のもと、入仏式(ご本尊をお迎えするおつとめ)を勤修いたしました。1年4ヶ月ぶりにお迎えしたご本尊を拝し、浄影寺再興の決意を新たにいたしました。 |
ご本尊・仏具の修復が終わり、搬入される(2006,9,19)
|
|
|
本堂の建設工期にあわせ、ご本尊や欄間などを京都で修復してきましたが、2006年9月19日、約1年4ヶ月ぶりに帰ってきました。ご本尊や仏具等の新しい本堂への安置には2日間を要しました。 |
|
|
ご本尊・阿弥陀如来を丁寧に安置 |
分解された仏具を搬入し、組み立てる |
|
【閑 話】 時 刻 時を刻む「人生」という名の時間
|
|
浄影寺再建 2006年8月3日 |
|
浄影寺再興 七宝講堂道場樹 方便化身の浄土なり 十方来生きわもなし 講堂道場礼すべし (讃阿弥陀仏偈和讃) |
|
方便化土としての本堂 「方便化土」と聞くとすぐさま思い浮かぶのは「ウソも方便」という言葉ですが、元々はそんな意味では毛頭ありません。方便というのは仏教語で、私たちを救うための如来の様々な手立てを意味します。煩悩を生きる私たちの眼では、形なき浄土(真実)や如来の精神を見ることはできません。そこで、如来は私たちにもわかるように形なき浄土の世界を「形」で表現してくださったのです。この「形」こそ、私たちを救済せんとする如来の表現だったのです。如来が方便化土の浄土として表現してくださった本堂に“いのち”が吹き込まれます。(H) |
|
|
|
|
|
工事が完了し、引渡し‐本尊をお迎えし落慶法要へ向けて‐ |
||
|
2006年8月3日、設計監理者の立会いのもと、請負業者から施主の住職に対して本堂の引渡しが行われました。 当日は、当院の総代や建設実行副委員長らが見守る中、本堂建設工事が無事終了したことを確認し、住職が引き渡し書に捺印、本堂の権利書を受け取りました。本堂に関する説明を受けた後、本堂が引き渡されました。 以後は、工事と平行して修復していたご本尊・阿弥陀如来をお迎えし、落慶法要を勤修するのみとなりました。京都で保管していただいていた仏具等が戻ってくるのは9月中旬になりますので、本堂の使用は11月以降になりそうです。 |
|||
|
|
|
引渡し当日の様子=2006年8月3日 |
|
閑 話 「人を愛するということの一番もとは、 その人にまなざしを向けること」 世情を見てみる。北朝鮮によるミサイル発射問題、イスラエルのレバノンへの空爆によって多くの子どもたちが死傷している現状、イランの核開発。一方、国内では、母親が我が子を川へ投げ入れ死亡させた事件、親による幼児虐待死・・・。どれも、人が人に対して向ける「まなざし」からはほど遠い凄惨な事件だ。「まなざし」という言葉も聞かれなくなった現代にあって、仏様が眼を薄く開けておられるのは「まなざし」でないかと思う。(H) |
|
浄影寺再建 2005年10月23日 |
|
|
|
定礎法要のおかざり。中央に「南無阿弥陀仏」の名号。その両脇には棟札が安置された(左)。棟札には表に如来の名号・発起人・大工棟梁などの名、裏には沿革が書かれている。=2005年10月23日 |
|
浄影寺本堂上棟式 |
|
|
|
|
|
定礎法要・上棟式執行‐本堂再建へ思いを寄せて‐ |
|
2005年10月23日、施主の住職や建設副委員長など当院の役職者、設計監理者、請負業者など、関係者63人の出席のもと、定礎法要・上棟式が執り行われました。 当日は、まず午後2時から住職、候補衆徒らが出仕し法要が営まれました。その後、当院の建設実行委員長らが足場に上り餅撒きが始まると、境内には近隣住民や子どもたちが集まり賑やかでした。 第二部では、本堂内で特設された会場で祝宴が行われました。乾杯に先立ち、住職が挨拶、工事関係者や建設委員の方々の労をねぎらいました。続いて、当院の建設委員を代表して副委員長が挨拶に立ち、浄影寺草創期のことや本堂再建に掛けた思いを述べられました。また、設計監理者、請負業者の代表がそれぞれ挨拶に立ちました。 当院建設実行委員長による乾杯音頭の後、それぞれに歓談が行われ、終始和やかでした。 |
|
|
境内から見た本堂の様子=2005年10月23日 |
|
浄影寺沿革を記した棟札を披露 ‐棟札に役員名を記し、門徒名歴史に刻む‐ |
|
定礎法要・上棟式当日、新本堂の棟木に掲げる棟札を門徒総代初め関係者に披露しました。棟札は本堂等上棟の年月や沿革、願主・工匠など関係者の名が記され、後に貴重な歴史史料となるものです。 今本堂建設においては棟札を二枚納めました。一枚目には、表に如来の名号・発願人名・設計監理者名・請負名・大工棟梁名、裏に浄影寺の沿革。二枚目には、表に建物名・住職名・設計者名・請負現場代理名・建設委員正副委員長名・建設実行委員正副委員長名、裏に建設委員全員の名(故人も含む役員)が記載されています。 また、役員以外にご尽力いただきました多くのご門徒の芳名につきましても、ご披露し、浄影寺の歴史に長く刻んでいきたいと考えております。 思えば、本堂の建設は、単に古くなった建物を新しく建造するということが主眼ではありません。それは、棟札が象徴しているように、多くの方々がお寺に対して様々な思いや願いをもって関わって下さっています。その思い・願いに応えることができるお寺に再生する、言わば、建物としての「本堂再建」から念仏道場としての「浄影寺再建」へと転換していくことが求められていると受け止めます。その意味では、本堂の再建は、念仏道場としての浄影寺再生の始まりであり、足がかりだと思います。 これからの新しい試みとして、ご門徒宅を会場とした報恩講などの仏事や、親鸞聖人の話を聞く集まりを持たせていただきながら、親鸞聖人の魅力や浄土真宗の伝統を少しずつお伝えできる場を作っていきたいと思っています。そして、ご門徒を初め、地域社会に生きる人々の悲しみに寄り添い、心の支えになっていけるようなお寺を作っていきたいと思います。ぜひ、皆さんの力をお貸しください。(浄影寺再建へ) |
|
維持二〇〇五年(平成十七)十月二十三日、 蔵王町遠刈田温泉 真宗大谷派浄影寺再興略記
信楽山浄影寺の堂宇を再建するにあたり、顧みれば、二〇一一年に宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌を迎えんとする旧本堂の老朽化甚だしきに由りて、浄影寺総代初め役員一同、念仏道場再建の志願を建て、住職釋廣度のもとに結集す。爾来七年、如来の願力により道場の樹、建たんとす。 浄影寺の沿革を記せば、堂宇と寺号と異なれり。旧堂宇は、一九二五年に柴田郡村田町願勝寺衆徒の釋隨恵が願勝寺旧本堂を現在地・遠刈田温泉に移築、支院として建立す。寺号「浄影寺」の沿革は、これに先立つこと一六八八年、釋宗玄、仙台市南鍛冶町に坊舎「圓乗坊」を建て、浄影寺の基を築けり。然れども、明治初頭、坊舎の寺号を「浄影寺」と改称するも時経て荒廃す。一九三七年、釋隨恵、弥陀の勝縁ありて坊舎の住職となるも仙台空襲による焼失のため再建叶わず、一九四五年、遠刈田温泉に寺地移転す。これにより、釋隨恵は願勝寺支院を「浄影寺」と改め開基、本願念仏の教法の宣布に尽力せり。 本日、茲に、弥陀・釈迦二尊および親鸞聖人の尊前にて、本願流伝の歴史に参画せられし吾ら門徒祖先の労苦を念じつつ、有縁の同行とお迎えする上棟の儀に際し略記す。 信楽山浄影寺第二世住職 釋廣度 謹白 (釋弘道書之) |
寺説
深まる人間の闇に対する仏教的考え方・見方・価値観
最近、幼児や小学生が死傷するという痛ましい事件、多数の死傷者を出した列車事故、建築耐震偽造問題、ライブドア事件など、私たちの生活基盤を突き動かすニュースがあとを絶たない。これらの事件について、突発的に起こったものとする見方が一部にあるが間違えで、私は一連の事件として考えている。それらの事件に共通して言えることは、戦後、築き上げられた価値観、いわゆる、高度経済成長の中で作られた物質万能主義が遠因であった、否、「明治」の立役者の一人・福沢諭吉らが生きた近代という時代や思想の中に、その兆しがあったということである。古来、私たちは自然に対して畏怖・畏敬の念をもち、物質的価値観に置き換えられない生命への畏怖と尊厳を抱いていたものだ。そのことが精神風土を創り、生活の土台になっていた。しかし、ライブドアや耐震偽造の事件は、この社会は砂上の楼閣でしかなかったことを暴露したものだった。 近代以降、あるいは、戦後社会において価値観が大きく転換し、工業化・合理化・物質万能主義が唱道され、一面、経済的に「豊かな」社会を享受したものの、他方、精神文化の喪失や一人ひとりの独自性や生命の尊厳が脅かされるなど、存在の根っ子にあるものを失い、人間の闇・迷妄性はますます深まった。そして、社会に対する不安や心細さは増幅し、どこにも「安心」と言えるものがなくなったと言わざるを得ない。 本当の意味で、人間存在に「安心」を与えるのが仏教であり、近代の価値観ではない、古くて新しい価値観を与えるのが仏教だと思っている。今、この時代や私たちに求められているのは、ものについての「考え方」「見方」である。換言すれば、「精神(心)」の基礎工事である。つまり、仏教的価値観、仏教的考え方、仏教的見方が今の時代には必要なのだ。(候補衆徒) |