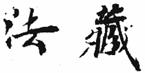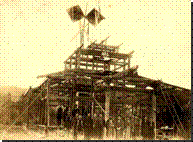|
|
|
真宗大谷派 浄影寺 |
|
参拝のご案内(永代納骨・永代経) 関連リンク 浄影寺再建への参画について |
|
【浄影寺紹介】‐1‐ |
今、いのちがあなたを生きている‐宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌テーマ‐ |
|
雄大な蔵王の大自然に囲まれた温泉郷の玄関口に浄影寺があります。 森林浴と温泉で体の疲れを癒したあとは、お寺で心のリフレッシュ。 本堂で静かに手をあわせる、お茶をいただく、お話をする・・・ 何気ない、そんな“癒しの空間”を提供いたします。
そして、お寺にはもう一つ大事な役目があります。 それは、疲れて渇ききった心に“いのちのことば”を注ぎ、心を潤すということです。
あなたは生まれるべくして生まれたのです。 昨日のあなたではなく、明日のあなたではなく、“今のあなた”が大切なのです。
長い人間の歴史を経て誕生した掛け替えのない“あなた”と“いのちの声“を聞きたい。 そして、寄り添って生きてゆきたいのです・・・。
|
|
名峰・蔵王山に向かう人を出迎える地蔵菩薩と当院の看板(参道入口) |
浄影寺は京都・真宗本廟(東本願寺)を本山とする真宗大谷派(浄土真宗)の寺院です。 当院の寺号は江戸時代前期まで遡り、現在の地・遠刈田温泉に寺地移転、1952年(昭27)に「浄影寺」として開基しました(詳細はこちら)。 遠刈田温泉は17世紀初めに蔵王山東麓(宮城県側)に開湯した湯治場。もともと山岳信仰が盛んで浄土真宗の地盤のない土地柄でした。先人たちは大変な苦労をして、この地に念仏道場の基を創りました。 |
|
名 称 |
真宗大谷派 浄影寺(しんしゅうおおたには じょうようじ) |
|
所在地 |
宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字東裏38番地 |
|
本 山 |
真宗本廟(東本願寺) 京都市下京区烏丸通七条上る常葉町754 |
|
宗 旨 |
真宗大谷派(浄土真宗) |
|
本 尊 |
阿弥陀如来(南無阿弥陀仏) |
|
宗 祖 |
親鸞聖人 |
|
経 典 |
浄土三部経(『無量寿経』『観無量寿経』『阿弥陀経』) |
|
聖 典 |
『顕浄土真実教行証文類』(『教行信証』)、『歎異抄』など |
|
開 基 |
圓乗坊 釋 宗玄(仙台市南鍛冶町) 浄影寺 釋 隨恵(蔵王町遠刈田温泉) |
浄影寺再建について |
|
|
|
|
|
浄影寺の沿革 |
|
◇本堂の歴史 ‐旧本堂の棟札から‐◇
当時、村田町の願勝寺住職であった隨縁のもと、教区の「佛教積徳一心会」が中心となり、教化事業の道場として願勝寺支院を建立せんとの志願を起こしたが建立するには至らなかった。そればかりではない。本堂建立に奔走した「佛教積徳一心会」会長の木川田栄五郎、大沼勘十郎の二氏が死去したのであった。 しかし、それで本堂建立の志願が終ったわけでは決してなかった。隨縁は二氏の遺志を受け継ぎ、佐藤源兵衛氏らを発願人として、再び、本堂建立に力を注いでいくこととなる。このことは、旧本堂解体のおり、発見された棟札から伺えるが、この時はまだ「浄影寺」という寺号は見えない。つまり、この時点では、本堂は現前するも、まだ「浄影寺」の開基とは言えなかった。それは、本堂の歴史と寺号の歴史が異なるためであった。本堂と寺号、それぞれの歴史が融合するには「時」を俟たねばならなかった。
◇浄影寺の前身 ‐江戸時代前期‐◇
釋隨恵師 ◇寺地移転 ‐浄影寺再建と開教‐◇
さて、仙台市にあった「浄影寺」が諸般の事情により荒廃していたところへ、願勝寺衆徒であった隨恵が転属し住職になったのは、1937年(昭和12)のことである。併しながら、荒廃した「浄影寺」を寺院として再生するには、事実上、困難な状況であった。 加えて、1945年(昭和20)7月10日の仙台空襲による戦火で庫裡が焼失したことから、「寺の存在がない」ことを理由に官有境内地が没収されてしまった。そして同日、遠刈田温泉に寺地移転したことが、1952年(昭和27)5月に本山・東本願寺宗務総長へ提出された「寺地移転承認申請書」によって確認することができる。ちなみに、宗教法人法の公布は、前年の1951年(昭和26)4月であった。 そして、この寺地移転は、隨恵がひとえに、荒廃した浄影寺の再生と、新天地・遠刈田温泉での伝道開教に、いかに情熱を傾けていたのか、これらの史料によってその一端を知ることができる。 歴史は遡るが、寺地移転前の浄影寺の住職就任の年 本堂の再建と共に、さまざまな史料が発見されているので、今後、史料についても紹介していきたい。 旧本堂の上棟
『法蔵』第22号(2005年3月発行)より
|