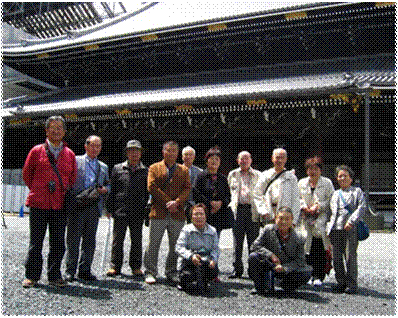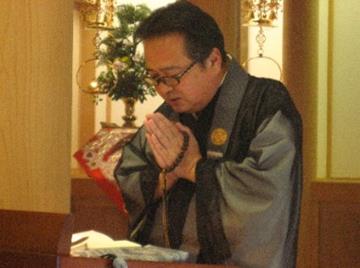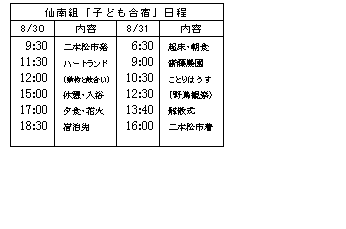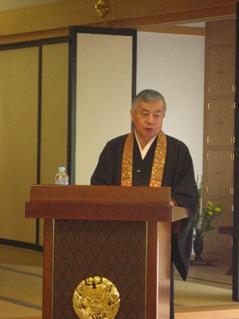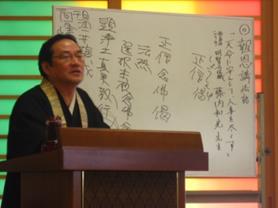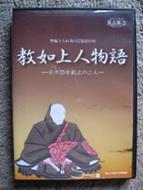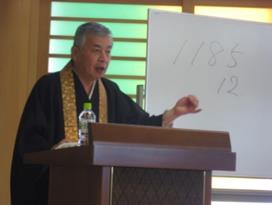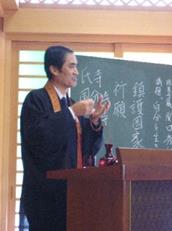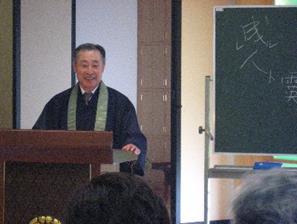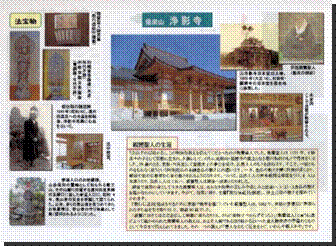|
|
|
|
�^�@��J�h ��e�� |
|
|
�g�b�v�@�����Љ��@�^�@�̋����@�����̊����@�{���Č��@���L�@ �Q�q�̂��ē��i�i��[���E�i��o�j�@�֘A�����N�@��e���Č��ւ̎Q��ɂ��� |
|
�ŐV�j���[�X
|
|
|||||||
|
�ߑ�A������u���{�̖閾���v�u�ߑ㉻�v�Ƃ����X���������̂��ƂɁA���{�����m�ƌ�����ׁA���E�I�ȑ�푈�ɓ˂��i��ł�������ł��������B����J�h����O�Ȃ��A����ɒǐ����A�푈�ɉ��S���Ă������j�̈Õ��ł�����B����ȏ@�h���A�P�X�X�T�N�ɕs�팈�c���o������A�̏@��ߑ�j���؍�Ƃ̒��ŁA�@�h����Ǖ����邢�͖��������`�ŁA����̈łɑ����Ă����O���҂�m�邱�ƂɂȂ�B�ނ�͂܂��ɁA����̈łɍR�����O���҂����������B�u��t�����v�ɘA���������������،����t�͂��̈�l�B�����A�퍷�ʕ����̂���k�Ƌ��ɐ����悤�Ƃ����t��Ǖ����Ă����B���̓��h���u���̗��j�v�������A��������l�ЂƂ肪�A�ނ炪�S�����ۑ�ɐG��Ă������Ƃ����߂��Ă���B�u�����@�v�u���d���v�Ƃ����@����������ł�������A�ł���B �U��22������24���A�u��t�����v�̕���ɂȂ����ꏊ�̈�E�a�̎R���V�{�s��K�ˁA�s���t�B�[���h���[�N���тɌ����t�䂩��̏�ŋΏC���ꂽ�t�̏ˌ������E�������@�v�ɁA���ԂƋ��ɎQ���B�u��t�����v��ʂ��Ď��Y���x���l���Ă݂����B |
|||||||
|
�u��t�����v�ɘA���E�v�z�e�����ꂽ �V�{�A�F��̃t�����e�B�A���� |
|||||||
|
�U��22���A�d�Ԃ����p������11���ԁA�a�̎R���V�{�s�ɓ����A���̓��͈ړ������ň�����I������B�������ɂ���ʂ̗������ǂ��Ƃ͌����Ȃ��n�悾��������ς�������Ƃ�������B�V�{�E�F��𒆐S�Ƃ���I�ɂ̕����́A�J��A���̒n�̗��ɂ���Č���Ă����ƁB�����Č�ɂ݂�悤���u��t�����v�A���҂̈�l�E��ΐ��V���Ȃǂ́A���x���C�O�֓n�q����ËZ�p�݂̂Ȃ炸�A��i�I�Ȑ��_�������������Ă����Ƃ����A�����䂦�̓������������B �u��t�����v�͂P�X�P�O�N�A�ߑ���{�̗��j�ɂ�����łł������B����[�ɁA���Ƃ����̖ړI�̂��߂Ɏ�i��I�Ȃ��A������u���|�����v���n�܂����B���ƌ��͂ɂ���đS���W�̂Ȃ��R�̎������A�K���H�����u��d���v�Ƃ����u�����V�c�ÎE�v�Ƃ��������ɂ܂Ńt���[���A�b�v����A���Y�@�������ɑߕ߁A24�l���ٔ��Ƃ��������u���v�̕���ɔz�����ꎀ�Y��������Ƃ����i����12�l�����Y�j�A���_�E�v�z�ւ̒e���������B�u�����v�Ɋ������܂ꂽ���،����i�ȉ��A�����j�͂��߁A�V�{�E�F��̂U�l�́A�@���ɂ��Đl���̃t�����e�B�A�ƂȂ�A�e���������邱�ƂɂȂ����̂��B�ނ���o�����V�{�E�F��̕��y�����������Ǝv���B |
|||||||
|
�u��t�����v�ɘA�������l�X������42�N�� �O�����ΐ��V���A�����ߓ��A�ʒu�^�g�B������v�ې���A���،����A�V�����Y |
�u��t�����v�]���Ҍ�����w�u���p���x |
||||||
|
�y�u��t�����v�]���Ҍ�����w�u���p���x�z |
|||||||
|
������J�~��ŁA����͕����ꏊ��������B�ē��l�͐V�{�s�ό��K�C�h�̉�K�C�h�ō��،����t���������̌I�ъm�����B�}�C�N���o�X�̉^�]�œo��A�P�l�Q���Ƃ������Ƃ��낾�B �܂�����������̂��A�u��t�����v�]���Ҍ������w�u���p���x�B�Q�O�O�P�N�A�V�{�s�ł��u��t�����v�ɘA�������V�{�E�F��̂U�l�����_���n�܂�B���N���u�u��t�����v�̋]���҂�����������v�i��͒ʕv��j�������オ��A�Q�O�O�R�N�ɐ����ɍ�L�O�ٕ~�n�Ɍ�����������A�̂��V�{�w�ɂقNj߂��ꏊ�Ɉړ]���ꂽ�B���́u�u���p���v�̔蕶�́A����ږ�ŁA���݁A�����t�v�L�O�يْ��̒Җ{�Y�ꂳ�M������ꂽ�������B���ł��u�u���p���v�͍�ƁE���㌒���̌��t���̗p�������́B�l�߂𐰂炷���Ƃ����ړI����������ɒ���́u�l�߂����ꂽ�炻��ł����B���R�E�l���E�����E�������S�l�����������ď�����낤�Ƃ����B���̎u���p���ŁA�����Ȃ�����v�ƌ����Ă����A�ƌI�т����B���̂S�l�Ƃ͑�ΐ��V���A���Ε��l�Y�A���،����A�����ߓ��̂��ƁB�����ɐ��Ί��O�Y�ƍ�v�ې�����������U���S�������Y�����ƂȂ������A���Y�͑�ƕ��l�Y�j�̂Q�l�A���̂S�l�͖��������Ɍ��Y�ƂȂ�B�������A���Y�ƂȂ�������͍����A�����͕a������B����A���O�Y�ƍ�v�ۂ͍�������o�����A���O�Y�͏o�ĂQ�N���Ŏ��S�B���a�܂Ő������͍̂�v�ۂ����������B �I�т���́u��X�K�C�h�́A�蕶�ɂ��镽���E�����E���R�E�l������葱���Ȃ���Ȃ��Ǝv���܂��B�Ƃɂ����A�����ɑ���e�������ӂ�����A�ǂ�Ȃ��Ƃł�����Ă��܂��̂����ƂƂ������̂�����c�v�ƁB |
|||||||
|
�y�t���וۊفz |
|||||||
|
�o�X�͗וۊّO�ɒ�ԁB���̕t�߂ɁA���ĉ痴�R�Ƃ����R�������āA�����ɒ���t���悤�ɔ퍷�ʕ����̐l��������炵�Ă����B���̋߂��ɑ�ΐ��V���̏Z�����������Ƃ����B���̑�ɂ��Ē��㌒���͑�ϑ��h���Ă����Ƃ����B����͂��c�ꂿ����̘b���悭��������Ă����B�u�h�N�g����̈�@�ɍs������g���g���g���ƂR��A�@�����B�������牽�������ƁA�h�N�g���͊F��f�@���Ă����v�ƁB�h�N�g���Ƃ́u�łƂ�v�Ƃ�����ΐ��V���̈��̂��B��͎����̖R�����퍷�ʕ����̐l�ɑ��ẮA�f�Ô�����Ȃ������B�����̈�t�͖����f�@���������͂Ȃ��������A�퍷�ʕ����n��։��f�ɓ����Ă������̂͑�����������B���������b���悭�������ꂽ���㌒���͑�h����悤�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����ƁA�I�т���B���̏t���וۊقɂ͒��㌒���̌��e�⎑���������������Ă���B��������s���ɂ��u�F���w�v�̑O�g���n�܂����B�����͒����l�̑��A�퍷�ʕ����̌ØV�̘b���B���̒��ɗႦ�A�����̎��E��̖�k�Œm�b�̂��邨�k�����̘b������B�����S����A���̒U�߂���͖V����ł͂Ȃ����A�����Ƃ����������Ă���A���̂悤�Ȏ��b������́w��N�̖��y�x�ɏo�Ă���B |
|||||||
|
�y�u��t�����v�������z |
|||||||
|
�J���܂��܂������Ȃ钆�u��t�����v�������ɓ����B�����́A���ĕ����ߓ������ق��������͐쐅�Q�̉e���ŕ��A���݂��u��t�����v�]���҂����������^�c���Ă���B�I�т���́A�Q�l�̕������̎����̖{���𑨂��Ă���ƁA�͂����߂Č����B�u��͒ʕv�搶�́A�l�߂Ƃ����Ȃ�Ɛl�������Ȃ���Ȃ��B�Ƃ��낪�A���̎����ɂ͔Ɛl�����Ȃ��B��t�߂��l�����l�͈�l�����Ȃ��B�����炱��́A�l�ߎ����ł͂Ȃ��e�������Ƒ�����ׂ����Ɓv�u�Җ{�Y��搶�́u��t�����v�ɂ����K�����ʂ������ł��B���ʂ�t�����ɏ����Ă��܂��ƁA�����u��t�����v���������悤�Ɉ�ۂÂ����Ă��܂��v�ƁB�������̂��̂����݂��Ă��Ȃ��̂ɁA���݂��Ă��邪���Ƃ����Ƃ����グ�v�z��e�����Ă����B�I�т���͎����̖{�������ꂽ�B �Ȃ��u��t�����v���N�������̂��B���ڂɂ͓��I�푈�ō��������g���߂��Ă������Ƃ��傫���B�I�т���ɂ��ƁA���Ɨ\�Z���S���~�ň�ʓI���C����20�~�̎���B���ɐ��\���~��������A�؋����W���~�܂Ŗc��オ���Ă����B���̌R�������m�ۂ̒��A�����������܂��܂��������A�\�����N����B���������̒��ŁA�����{��`��Љ��`���s�����������Ă��鑽���̐l�����ɉe����^���n�߂Ă����B���ɁA�K���H���̌��t�ɋ������̂��A���Y��������24�l�������B�����ɎЉ��`�҂����ԑŐs����D�@�Ƃ݂����Ƃ́A���Y�@�u��t�߁v�������ɑ�ʌ��������B���Y�@��73���ɂ��u�V�c�A���c���@�A�c���@�A�c�@�A�c���q���n�c�����j�V��Q�����w���n���w���g�V�^�����m�n���Y�j���X�v�Ƃ���A�ٔ��ƂȂ�Α�R�@�̈�R�݂̂Ŕ���J�Ői�߂��A�����͎��Y�̂݁B�㍐�͂Ȃ��B |
|||||||
|
|
|
||||||
|
���̍ٔ��ŁA�����ƍ�v�ې���ٌ̕�������̂́A�^�Ӗ�S������˗����ꂽ���o�C���B�ٔ��̒��ŕ��o�́u���ꂾ���̂��Ƃ����Ȃ�A���A�ǂ��ŁA�N���A�����A�Ƃ������Ƃ����܂��Ă��Ȃ��Əo����͂��͂Ȃ��B���߂čٔ����Ŋ�����킹���l����ŁA�d�c�����`�Ղ��S���Ȃ��v�Ǝ����̖����_�����A���@�̝s���ł��邱�Ƃ��w�E�������o�ٌ̕�͑f���炵���ƌI�т���B �����Ă��̕��o�̍ٔ��L�^���A�u��t�����v�̐^����m��l��������A�ΐ����B��́@�u�u��t�����v�͑��A���Ȃ��O�̍߈Ă��ЂƂ܂Ƃ߂ɂ��āA�����̖����{��`�������ɖo�ł���@�����낤�Ƃ������̂��v�Ǝw�E�A�����̊j�S��͂�ł����B�������A��͊Ԃ��Ȃ��A26�̎Ⴓ�ŖS���Ȃ�B��͂R�̎����A���Ȃ킿�A����{��q��{�����g�Ȃǂ́@�u�V�c�ÎE����v�A���R�ɂ���u�c���q�ÎE�v���v�A�����čK���H���𒆐S�Ƃ����u�����s��̌v���v�B���̂����R�ڂ̌��Ɋւ��āA��ΐ��V���𒆐S�Ƃ����u�V�{�O���[�v�v�������Ɋ������܂�Ă������B�I�т�����u����Ȏ����Ȃ������B�����A���������̂悤�ɒ�����������Ă����B�D�ɏ���ĉ�������Ă��邱�Ƃ��u�d�c�v�Ə�����Ă�������v�ƁB�֘A�̂Ȃ��R�̎�����̎����Ƃ��Ă��������Ƃɑ��āA�I�J�V�C�ƌ������̂���������B��������24�l�����Y���������B�������A���̗�����12�l�����������Ɍ��Y�B�����Ė��������ɂȂ������̂ɑ��āu�ǂ������v�Ƃ����A�����ɂ��傫�ȗ��Ƃ���������A�ƌI�т���B�u�V�c�É��̉����v�Ƃ������t�ŁA���݂��Ȃ��������Ƃ������Ƃ��Ď���������Ă��܂����Ƃ̍I�݂ȍ\�}���w�E���ꂽ�B�u�����t�v�����ɏ�肢���Ƃ������Ă���B�T���r��H�������Ǝv������A�ǂ�ȗ��R��t���Ă��r��H�����āB���Ƃ�������͎ז���Ǝv������A�ǂ�ȗ��R��t���Ăł��r�����Ă����v�ƁB �W���i�̒��ɂ́A�ۖ؈ʗ��E�r�̊G��w��t�����x�i�͎ʁj���Lj�ʂɌf�����Ă����B�u�{���͔��͂�����ˁB����͎��ʂł͂Ȃ����Ǝv���܂����v�B�u��t�����v�Ŏ��Y�ƂȂ���12�l�Ƃ��ꂼ��̏�ɂ͍i�ꂪ�u����A�G�̍��[�ɂ͐��X�����i��Y�̖͗l���`����Ă����B���̊G�̉E���ɑ�ΐ��V�����`����Ă���B�I�т���́u���V����1911�N�P��24���̂Q��23���ɏ��Y�▽���܂����B���ꂩ��107�N��̍��N�̂P��24���������ɁA�V�{�s�͔ނ𖼗_�s���ɂ��܂����B�����ł���v�ƒx�������Ƃ����A���V���̖��_����ꂽ�B |
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
�u���Ί��O�Y����́u��t�����v��������Ƃ������l�ł��A���V���ɂ͂P�Q������Ă��܂���B�n��̂��߂ɐV�����_�Ƃ�ڎw���Đ���������ł���悤�ɂƊ撣���Ă����l�Ȃ�ł��v�B�Ƃ��낪���Y����A�n��̐l�͖��W�����B���ɁA��������o���l���A������앨���o�ׂ�����A�u�����Ɋւ�����y�n�ō�������̂ȂH���邩�v�ƌ�����B�܂��A�d���ɏA�����A�c�т��������Đ������Ă����l�B��������������������B���Y�������o�����A��ΐ��V���̐f�Ï��O�Ɏ�������o�����ƁA�u���̐l�͈����l������ˁv�Ƙb���l�̉�b�𐽔V���̎q�ǂ��������ĈӋC���������ȂǁA�u��t�����v�̘A���҂݂̂Ȃ炸�A���̉Ƒ��́u�t�k�v�Ƃ��Ĕ�Ƃ̐�����]�V�Ȃ�����Ă����B �I�т��ˑR�A�₢������B�u��������Ēm���Ă��܂����B�[��A�X�C��{���_�����ɁA�^���ÂȒ��ōs�������ŁA���ɜ݂�l�����̑����͂��̂悤�ɂ�����̂ł��v�u��t�����v�]���҂̈⑰�̐l�����ɁA����Ȉ������ƁA����ĂȂ�����A���X�Ƌ����ĕ\�ɏo�Ă��Ă��炤�A���ꂪ�������̊����Ȃ�ł��v�ƁB �Ƃ���ŁA�����ɘA�������V�{�E�F��̐l�X�́A����Ӗ��ł͕K�R�I�ł������Ƃ�������B�܂�A���E���a�E�����ʂɐ��������䂦�ɁA�����āA�����͐e�a�̐��_����O���҂ł��������䂦�ɁA���Ƃɂ��e�������̂��B��ΐ��V���Ƃ̊ւ��̒��Ō����Ă���B��҂ł����͐��m�ȂNJC�O�n�q�����������B���̒��ň�x�֍s�������A�J�[�X�g�Ƃ������������ʂ�m��Љ��`�̏��Ђ����A�A���B�Ƃ��낪�A�V�{�ł��퍷�ʕ����̐l�X�ɑ��錵�������ʂ�ڂ̓�����ɂ��邱�ƂɂȂ�B�����ő�͌����Ƌ��ɕ���������i�̑g�D�u���S��v��������B���Ɂu�����А錾�v�����ɏo��16�N���O�̂��Ƃł���B ����A�^�@��J�h����Ǖ�����Ă������،����́A1996�N�S���A������10���ɂ���āA�u�Z�E���Ɓv�u���ˁv�������������ꖼ�_���Ȃ��ꂽ�B�����ɂ͏@��Ƃ��č��Ƃɒǐ���������Ǖ��������Ƃւ̜Μ��ƎӍ߂��q�ׁA�����̎��тɊw�ь������Ă������Ƃ��Ăъ|���Ă���B�����Ɂu�s�팈�c�v�����\���Ĉȗ��A�����͎������̉ۑ�ƂȂ����B �V�{�E�F��̂U�l�͕������ʖ��A�����Đ푈�ɑ��Đ��ʂ�������������B����ȃG�s�\�[�h���Љ�ĉ��������B�����A�����̂����͔퍷�ʕ����̂���k�������A�o�ϓI�Ɍb�܂�Ă��Ȃ��Ƃ����������B�u�푈���͂⒉���茚���̂��߂������o���ƌ����Ă��悤�����Ƃ����ƁA�����ƌ����Ă�����ł��v�B�܂��A�V�{�Ɍ��݂̗V�s�����݂���悤�Ƃ������A�����͐�Δ��Ƃ����ӎv�������A�V�s���o���Ă���͓����ŋq�𑨂܂����������������邱�Ƃ��������B����ɂ��ČI�т���́u����k�̔퍷�ʕ����̑����̏����������V�s�œ����Ă�����ł��傤�B�������ʂ̓A�J���Ƃ����̂Ƌ��ʂ������̂ł��v�B���̈���Łu���̐l�́A���͍��ʎ҂ł����v�ƁB�ł́A����������ς����̂��B |
|||||||
|
|
|
||||||
|
�����O�Y�̏����Ɂw�ނ̑m�x������B����͌��������f���������́B������������̍��A�퍷�ʕ����̂���k��̖@���֏�����H��������邱�Ƃ��������B�u�@���ŏo�Ă��闿���͍A���ʂ�����v�ƁB����ŁA�@����p�ɋ^������������ƁA���ʂ̕@�����ȂǁA�n�����������J�����čH�ʂ��Ă������Ƃ�m��ƁA�u����ŕ����]�����N�����B�����ĕz�{��Ⴄ�킯�ɂ͂����Ȃ��ƁA��������͎�����ɂȂ��āA�����̐H���Ԃ����҂��ł����̂ł��v�B����ȍ~�A�퍷�ʕ����̎q�ǂ��������W�߂ĕ��������銈�������Ă����Ƃ����B �퍷�ʕ����̂���k�Ƃ̊ւ��̒��ŁA�O���ҁE���،�������܂ꂽ�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�e�a���l�̋����ɐ����ɐ����A�����Љ�����H���悤�Ƃ��錰���ɂƂ��āA���������핽�a���͏o����Ȃ���Ȃ�Ȃ������ۑ�ł���A����䂦�ɁA�u��t�����v�A���҂ƂȂ��Ă��܂����̂ł���B�����̒���w�]���Љ��`�x�̒��ɓo�ꂷ��u���Ɂv�Ƃ������t���A���߂ċP��������Ă���B |
|||||||
|
�y���ʑ�Ёu������v�z �����t�v�L�O�قɍ~�藧���A���ʑ�Ђ̎Гa��ʂ�߂���ƁA�T���Ƃ������̗t�ɕ���ꂽ��p�ɒ����肪�������B�~�T�C���̌`��������́A���܂�ɂ��O���e�X�N���B���I�푈�����ɕ�������O�Ɂu�������Ԃ̂���߂�v�ƌ��R�Ɣ����������́A������̌��݂ɂ��Ă��������B |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
��J��n�u���،���������v �V�{�s���̃t�B�[���h���[�N���I���A��s�͎s���x�O�ɂ����J��n�Ɍ��������B�����ɂ��̉J�ŁA�u���،���������v�ɑ������͐�Ɖ��������A�吨�̐l���č��ɂ݂��Ă����B���̌������1995�N9��25���ɏ@�h�������������̂ŁA���ׂ̗ɂ͕l���ɂ����������؉Ƃ̕悪�ڐ݂���Ă���B ���،����t�䂩��̏�ŋΏC�����u�������@�v�v�ɐ旧���āA�ߑO11�����猰����O�s���܂����B |
|||||||
�Q�O�P�V�N�u�t�̖@�v�v�ΏC
�u�×��Ƃ������ꏊ���������琶���Ă͂����Ȃ��v
|
|
|
�Γc�G��搶 |
|
|
�@�t���₩�ȂT��14���A�u�t�̖@�v�v���ΏC�v���܂����B���̖@�v�͎ߑ��̌�a���A�@�c�e�a���l�̌�a���A�O�Z�E�E笌b�t�̖��������Ƃ��āA���N�T���̑�Q���j���ɋ߂��Ă��܂��B�{�����ł͐��ʂ̑傫�ȑO��Ɋ|����ꂽ�ŕ~�A���̏�ɂ͕�����傫������ꂽ�����������܂����B�܂��{���̊O�Ɋ|����ꂽ�ܐF�햋�A���ւɂ͒a���������u�����Ԍ䓰���Q�w�҂��o�}���܂����B�a�����͎ߑ��a���̎��A���������ēV�ƒn���w�����p��\���������̂ŁA�V����ØI�̉J���~�����Ƃ����̎�����A���{�ł͊Ò��𒍂��ł��a�������j�����Ă��܂��B �����͌ߑO10������s�E�w�䕶�x�q�ǁA�����āA�������S�R�s�̓������Z�E�E�Γc�G�掁���w�Y��Ȃ��@�����ā@�����Ɂx�Ƃ����u��ł��@�b����܂����B�@�b�̒��ŐΓc�搶�͂Q�O�P�P�N�ɔ������������{��k�ЂɐG��A�u�l�͌×��Ƃ������ꏊ���������Ȃ琶���Ă͂����܂���B�i�k�Ђ��j�Y��Ȃ����Ƃ��×��ɒʂ��Ă����̂ł��v�u�e�a���l�́A���l����̊፷���ɋC�Â��Ƃ������Ƃ�ʂ��āA�×���`�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���v�ƌ���܂����B �@�@�b��A�쎝�����J�ÁB�O�N�x��v����э��N�x��v�\�Z����o���ꗹ������܂����B�I����A�w�l���i���_�q�����j�̊F���������ꂽ���ցi���i�����j�ɁA�Q�w�҈ꓯ�A��ۂ�ł��܂����B |
|
�Q�O�P�U�N�u�u�v
���J�֔Ԃ��u�t�Ɍ��C |
|
��N�i2016�N�j�P�P���U���A�u�����C����A���n��E�^�@���@�̂��Z�E��P�O�l�o�d�̂��Ɛ��M��̐����{�����ɋ����n��܂����B�u�Ƃ͏@�c�e�a���l�̂������̏W���ŁA���l�̂����ɐS����䕧���ł��B��{�R�E���{�莛�ł́A���N�P�P���Q�P������Q�W���ɓn���Č��C����܂����A����ɐ旧���đS���̐^�@���@�ł��u���߂��Ă��܂��B �@�����͌ߑO�P�O������s�E�䑭��䕶���߁A���̌�A�@�b�B�u�t�͓��{�莛���k�ʉ@�̐��J�^���֔ԂŁA�u�����O���v�Ƃ����u��ł��b�����������܂����B�搶�̓n���Z���a���ɐG��u����̋����u���ɂ���āA�n���Z���a���҂͌̋��Ɩ��O��D��ꂽ�B���O��D���Ƃ������Ƃ́A���݂̍�����D���Ƃ������Ɓv�u���O�������Ă���̂����O���ł��v�ƌ���܂����B �@�@�b��A�Q�w�҂͌ɗ��Ɉړ��A��e���w�l���i���_�q�w�l�����j���p�ӂ��ꂽ�u���Ƃ��v�i���H�j�ɐ�ۂ�ł��܂����B |
�Q�O�P�U�N�u-�ߑ��a���E�@�c�a���E�O�Z�E����-�v
�u�t�̖@�v�v�ΏC
|
|
|
|
���₩�ȏt�̓��������S�n�����T���W���A�u�t�̖@�v�v���ΏC���܂����B���̖@�v�͕������J���ꂽ�ߑ��̌�a���i�S���W���j�E��y�^�@���J���ꂽ�e�a���l�̌�a���i�S���P���j�E��e���O�Z�E笌b�t�̖����i�U���R���j���䉏�ɋ߂���@�v�ł��B�����͎Q�w�҂ƈꏏ�Ɂu���M��v���߂���A���킫�s�E�������Z�E�̓����a���搶����u�n���E�Ɋy�v�Ƒ肵�āA�@�b�����������܂����B���b�̒��Ő搶�́A�n���͐l�Ԃ���錻�����E�ł��邱�Ƃl���w�E���ꂽ�̂ł��A�Ƙb����܂����B |
����킩��V�P�N�E���n����̕�
�u���ǂ����v-���ꂩ����{���l����
|
|
|
���{�莛����ʉ@ |
�Q�O�P�U�N�Q���P������R���A��䂩���s�@�Ŗ�R���ԁA����킩��V�P�N�ڂƂȂ�u�����v�Ɏ��͂����B���k�͐^�~�A�������A����ł͂ǂ����t��������B�����A�܂��K�˂��͓̂��{�莛����ʉ@�B�Q�O�P�O�N�S���A���{�莛����J���{���͎؉Ƃ���A�X��p�s�̕ČR���V�Ԋ�n�ɒ��߂��Ƃ���Ɉڐ݁A�ʉ@�����������B���̌��ւɂ́A����o�g���̑�J�h�m���ʼn���̐l�̒n�ʌ���ɗ͂𒍂����ʑ㐨�@�_�i���܂悹�E�ق�����j�̎ʐ^�������Ă����B���֔Ԃ��瓌�{�莛�̕z�������̐��������B |
|
���@����u���䎛�v |
������O���E�|���u���ǂ���v�E�{�� �����@����u���䎛�v |
|
�Q���ځA�m�ԏ��ꂳ�����������@����u���䎛�v��K�˂��B�m�Ԃ���͕��V�Ԋ�n�̒n��ŕ��a�^���ƁA�̂��ɐ^�@��J�h�m���ƂȂ����B�u�L���X�g���ł͏@�����v�̃��^�[�B���{�ɂ͐e�a�������B�e�a�ɍ��ꂽ�˂��v�B�m�Ԃ���͑�J�h�̃n���Z���a���̎��g�݂����|���Ō𗬂����悤�ɂȂ�m���ƂȂ����B����ɓ���ƁA�����ɖ{���A�E���ɐe�a���l�̊|���A�����ɗ����y��̎O���Ɓu���ǂ���v�̊|���B���a�ȗ������o�������ߎS�Ȓn���Ŗ�20���l���E���ꂽ�B����̐l���ł���ɂ��錾�t�A���ꂪ�u���ǂ���v�A��������Ƃ������t�Ȃ̂��B |
|
|
�`�r�`���K�} |
�m�Ԃ���̈ē��ʼn���̏Z�����������Q�̎��R�A�V���N�K�}�ƃ`�r�`���K�}��K�˂��B�O�҂͓������S����������A��҂͂W�T�l���W�c�������i�����j�̋]���ƂȂ����B���̉^�������͕̂č����w�������o���̂���l�̐����œ��~���ď��������V���N�K�}�B����̃`�r�`���K�}�́A�u�S�{�ĉp�v�Ƃ���������A�u�ߗ��̐J�߂���ȁv�u�K�}���o��Εĉp�ɂ݂ȎS�E�����v�Ƃ��������|�ӎ����������ŁA��e���c�q���E���A�Z�����m���݂��ɎE���������B�����ɂ͈⍜�̈ꕔ���i���c����A�Èł̉�����A�S���Ȃ����l�̙������������B���������̐l���Ǔ��ɖK���B |
|
�ߌォ��͕Ӗ�Â̕ČR�L�����v�V�����u�O�ŁA�ČR��n���ݔ��̍��荞�݂ɎQ���B��������ƊԂ��Ȃ��A�����̋@���������荞�݂����Ă��鉫��̐l�����������r�����������B���ꂪ�A���̂悤�ɌJ��Ԃ���Ă���B�u�l���E���ɍs����n�͂��߂v�u��������v�A����Ȑ��������n��B��\�͂ői����l�������r������@������O�ɁA���������s�������Ȃ������B�V�O�N�o���������A�����ɉ���킪�����Ă���c�B |
�L�����v�V�����u�ō��荞�݂����鉫��̐l���������ꌧ�E�Ӗ�� |
|
���������p�� |
�R���ځA���V�Ԋ�n�ɗאڂ��鍲�������p�ق֍s�����B�����͊�n�ɓ��荞��ł���̂ŁA�R�p�@�̊����H���悭������B���{�ɂ���ČR��n�̂V�O�����A���{�̋͂��P���ɖ����Ȃ�����ɒu����Ă���B���ɁA���V�Ԋ�n�͏Z��Ȃǂ����W���Ă���댯�ȏꏊ���B���������A�ČR��n�͕ČR��������̌�A�����Z���̉Ɖ���y�n�������ڎ��������Ƃō��ꂽ�̂��B����ɂ��ĉ���̐l�́u�e���ƃu���h�[�U�[�v�Ƃ������t�Ō���Ă���B�����ɂ͉�����`������Ƃ̊ۖ؈ʗ��E�r�v�ȁi�̐l�j�̊G��u�����̐}�v���W������Ă���B�푈�̎c�s���Ƌ������A�����Đl�Ԃ̜ԚL�c������̂����āA�����n���������������i���B |
|
�����čŌ�Ɏ�B�{�y�Ƃ͈قȂ�A�����⒩�N�����Ƃ̌��Ղ����������Ƃ������錚�z�l�����B�܂������A���Ă͗��������������̂��B���{�͗����Ɠ��̌��t�╶����D������������s���A�R���͂������āu���������v�Ƃ������̕������s�����B���N�ɂ��Ă������ƂƓ������B ���@��������������тсA�푈�ł���u���ʂ̍��v�Ɍ��������鍡�A�������͉��ꂩ����{�����A�푈���l���鎋�_���ƂĂ���ł���ƍl����B���Ƃɂ���Ċ����ƂȂ����l�X���������Ă����̂���m�邱�Ƃ́A���ꂩ��̓��{�⎩���̐��������l�����ő傫�ȉۑ��^���Ă������̂Ɗ����Ă���B |
�遁����s |
�Q�O�P�T�N�@�u���C
�`�@�c�̐��U�Ɋw�ԁ` |
|
|
�z�K�֗Y�搶 |
���₩�ȏH����ƂȂ����Q�O�P�T�N�P�P���P���A���n��E�^�@���@�̂��Z�E���P�O�l�o�d�̂��ƕu�����C�A���M��̐����{�����ɋ����n��܂����B�u�Ƃ͏�y�^�@�̏@�c�e�a���l�́u�䉶�ɕ�ǂ��v�ŁA�S���̐^�@���@�ł́A���N�P�P���Q�P������Q�W���̈�T�Ԃɓn���Č��C������{�R�E���{�莛�̕u�ɐ旧���ċ߂��Ă��܂��B �����͌ߑO�P�O������s�E�䕶���߁A���̌�A�@�b�B�u�t�͍�N�Ɉ��������ĉ�Îᏼ�s�E�������Z�E�̐z�K�֗Y�搶�ŁA�u�@�c�̐��U�Ɋw��-���݁i���܁j����-�v�Ƃ����u��ł��b�����������܂����B |
|
�搶�́u���͎��L���ł͂Ȃ��A�����A���̂��̂ł��v�u�i���ɂ��āj����������̂Ɛ[��������͈Ⴄ�B�������ł��Z���A�Z�����ł������Ƃ������Ƃ�����B�N���͉ߋ��ɐ����A��҂͖����ɐ����Ă���B�������A�����Ă���̂́s���t�Ȃ̂ł��v�Əq�ׂ��A�u����厖�ɂ��Ă����̂́A�i�[�������邱�Ƃɂ��āj������w�Ԃ��Ƃ���������ł��v�ƐÂ��Ɍ���܂����B �@�@�b�̌�A�ɗ��ŏ�e���w�l�����p�ӂ��ĉ��������u���Ƃ��v�i���H�j�ɎQ�w�҂͐�ۂ�ł��܂����B |
|
�H�G�ފ݉�@�v�E��k���̎Ғǒ��@�v
|
|
�Q�O�P�T�N�X���Q�R���ɏH�G�ފ݉�@�v���܂�܂����B����͖�k���̎Ғǒ��Ƃ��ċΏC���ꂽ�@�v�ŁA�����ɓ�����Ƒ��₲��k���Q�w���܂����B�@�ߌ�Q������s�A���̌�A���Z�E���u�����Ă��܂����v�̍u��Ŗ@�b�����܂����B |
�t�̋��s�@�{�R�E���{�莛���Q�q���s
�`�e�a���l�䋌�Ղ�K�˂ā`�@2015�N4��14���`16�� |
|
|
���Ԃ̗]�C���c��Q�O�P�T�N�S���P�S������P�U���A�u���s�E���{�莛���Q�q���s�v�����{�A��e����k�P�R�l���^�@��J�h�̌�{�R�E���{�莛�Ȃǂ��Q�q���܂����B���̎Q�q���s�́A�k�Ђ���S�N�z���Ŏ����������̂ł����B �S�N�O�̂Q�O�P�P�N�R������T���ɂ����āA��{�R�ł́u�@�c�e�a���l�V�T�O��䉓���@�v�v������Ɏ���s���A��e�����瑽���̂���k�Ƌ��ɂR���̖@�v�ɎQ�w����\��ł����B�u�䉓���v�i�����j�Ƃ́A��y�^�@���J���ꂽ�@�c�e�a���l�̌䖽���̂��ƂłT�O�N�Ɉ�x����s����A�������ɂƂ��Đ��U�Ɉ�x�̖@�v�ƂȂ�܂��B�Ƃ��낪���N�R���P�P���A�����{��k�Ђ��������A���]�L�̑�ЊQ�ɂȂ������Ƃ���A��{�R�ւ̎Q�q�𒆎~������܂���ł����B ���ꂩ��S�N�A�����n���āA��{�R�ւ̎Q�w�����A���܂����B��{�R�֕���������Ă������Q�w�����߂Ă̕��ȂǁA�l�X�Ȏv���̒��ł��Q����������܂����B |
|
|
|
|
|
�P���ځy�@�@�z�@ 4��14�������A�����c����⑼�̒n�悩�����`�ō���������s13�l�́A��H�A�ɒO��`���o�ċ��s�s���ցB�V��͂����ɂ��̉J�B�ŏ��ɖK�˂��͓̂V��@�̖�Վ��@�E�@�@�B��Վ��@�Ƃ͓V�c�����̎��@�̂��ƂŁA�K�͂͏������Ȃ�����R������Ù����B �@���̐@�@�́A�e�a���l���W�̎��ɓ��x�i����ɓ��邱�Ɓj���ꂽ�����ŁA�䔯�i�Ă��͂j���s�����̂͌�ɓV�����ƂȂ鎜���a���ƌ�����B�[���ɐ@�@�̖��@�����e�a���l�́A�����K�˂�悤�a���Ɋ��߂�ꂽ���A���l�́u�����A����Ǝv���S�̂������@�锼�i���j�ɗ��̐������̂���v�Ɖ̂��r�݁A���x�����肵���Ƃ����B �����e�a���l���䔯���䓰�������̂܂܈���Ă���A��藎�����������{����Ă���ƕ����B |
|
|
�y����J�E���@�z �@�@�̖���o�āA�_�{�������炭�����ƁA���@�i������������j�Ƃ���������������B�����͖{�莛���˂̒n�E��J�Ƃ����ꏊ�B�e�a���l�S����A���l�̌�^�e�����u���鏬���ȕ_�������Ė����̊o�M�u����E�v�i�邷�����j�Ƃ��Č���Ă����Ɠ`������B |
|
|
�m���@
��J�c�_ |
�y�m���@�z ���@���߂���ƁA�傫�ȐΒi�̏�Ɉ�ۑ傫�ȎR�傪������B��y�@�̑��{�R�E�m���@���B ��y�@���J�����͖̂@�R��l�B���̖@�R��l�����A�Ⴋ�e�a���l�̐搶�ł������B�W�����b�R�ł��C�s�Ȃ������e�a���l�ł͂���������Y�͂܂��܂��[�܂����ł������B29�̎��A�������q�䂩��̋��s�E�Z�p���֕S���ԎQ�Ă����̂��������B���̌�A�O���ɂ���ĒN�ł����₷���~����Ɛ����@�R��l�̑��������K�˂���q�ƂȂ����̂��e�a���l�ł���B�e�a���l�͖@�R��l�̋����ɂ��傫���l����ς��邱�ƂɂȂ�B �������A���̌�A�@�R��l�̋g�����c�͑��̕����⒩�삩��e�������U�������Ă��܂��B�@�R��l�͓y���ցA�e�a���l�͉z��֗��߂ƂȂ�^����H�邱�ƂɂȂ�B �y��J�c�_�z �m���@����~�R��������ƁA�����Q�����o�}����B�e�a���l�̂��揊�u��J�c�_�v���B�����ɂ͓��{�莛���̌���ƑS���̂���k�̂��⍜�����߂��Ă���B |
|
|
���Q���ځy�Z�p���z �Q���ځB�h���悩��قNj߂��Ƃ���ɘZ�p��������̂ŁA���{�莛�֎Q�w����O�ɖK�˂��B �����ɂ͘Z�p�� ���@���Ƃ����B�r�V���˂̒n�Ƃ��ėL���ł��邪�A�����́A�@�R��l�ɏo������O�ɁA29�̐e�a���l���Q�Ă������䓰�B�������q���n�����ꂽ�Ƃ����Z�p���́A�Â����珎���̐������q�M�Ɩ��̂��������ꏊ�Ƃ��ĐM����Ă����ꏊ���B��{���̔@�ӗ֊ω��͐������q�̖{�n�Ƃ��Ēm���Ă���B�����̃r���Ɉ͂܂ꂽ�s��̐^�ɂ���Ȃ���A�����ɓ���ƐÎ�ł��邱�Ƃɋ����B�����̒����ɘZ�p���A�E��ɂ͖������e�a���l�u���z�̑��v�����u����Ă���e�a��������B |
|
�y���{�莛�z �Z�p������^�N�V�[�ʼnG�ےʂ��ցB���炭����ƁA���ʂ��ނ������s�w�r���A�E��ɋ��s�O���̈��e����B���̌�e���傱���A�^�@��J�h�̖{�R�E���{�莛�̎R�傾�B ���{�莛�ɓ�������Ȃ�A���Z�E�̈ē��ł܂����a�ē��B���{�莛�͐����ɂ͐^�@�{�_�A�܂�A�^�@��k�̋A�ˏ��ł���A���{����Ƃ����Ӗ����B ��e���傩�狫���ɓ���ƖP�����H���L�����悤�Ɉ�ۑ傫�ȉ�����������B�e�a���l�̌�^�e�����u����Ă��邱�̌�e�����Q�w���ď��a�����w���悤�B ���������{�莛�̗��j��R�����ƁA�{�莛12��E���@��l�́A�L�b�G�g�̍����ɂ��B����������̏y�@��l���Ղ��p�����ƂɁB�������A�G�g������A����ƍN�����͂������n�߂�ƉB���������@��l�ɓ��Z���̓y�n����i���V�����{�莛�������������B���ꂪ���݂̓��{�莛�A�P�U�O�P�N�̂��ƁB����ɂ��A�{�莛�͓������{�莛�ɕ��h���邱�ƂɂȂ����̂��B ���{�莛�͉ߋ��ɂS�x�Ђɑ����A���̓s�x�A�Č�����Ă����B���̉����́A�֖�̕ς̕��ɂ��Ď�������A�P�W�X�T�N�i����28�N�ɗ������ꂽ���́B��k76���A����58���A����38���A�剮���ɕ�����銢177,5000���́A���E�ő勉�̖ؑ����z�ł���B �y���{�莛�E��Q�a�z ��e�����獂�L��������Ă����ƁA�������ɑS������Q�w����邲��k�����}������Q�q�ڑҏ��B���̎�O�Ő^�@�{�_�����o�z�[���̃M�������[����Ƒ�Q�a�ɒ����B��Q�a�͂��̖��̒ʂ�Q�a����A����k�̂��։��Ƃ��Ă��g�p����Ă���B���̒��ɓ���ƁA���{��ƁE�|�����P�攌�̐��n�悪����B�|�т��щ�鐝��`�����u���|�쐝�v�A�O���ɏo������Ԑ���`�����u�쐝�v�i����j�A�����č��ɂ��܂ꂻ���Ȍ͂ꂽ���̎}�ɔ��܂薰��ӂ����i�����j��`�����u�V������v�i�낤��イ�݂���j�A��������O���̐��E��`���Ă���B |
|
|
������e���O�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������Q�a |
|
|
�y���{�莛�E�{��a�z ��Q�a���牜�̘L��������Ă����ƁA�V�c�Ƃ��牺�����ꂽ�{��a������B���ɓ���ƁA��̉�����F�ŁA���ɂ͋{���̏K�����`����Ă���B�䏊�ɂ������������A�Ȃ������ɂ���̂��B���́A����͍]�˖��{���疾�����{�ɕς�낤�Ƃ��钆�ŁA�����ԁA�]�˖��{�ɔ�̂��Ƃɂ��������{�莛�́A�������{�̂�����`�ŁA���{�������i�߂�k�C���J��ɏ@���E�Ƃ��Ă������������������A�k�C���ɐi�o�������j�����B�k�C���͂��ăA�C�k��Łu�A�C�k���V���i���l�Ԃ̑�n�j�v�A������A�A�C�k�����̓y�n�ł������B ���V�A�̓쉺�����ꂽ�������{�͑O���Ƃ��āA�A�C�k�����̏Z�ރA�C�k���V���ɐi�o���A��������𐄂��i�߁A�A�C�k�����̌��t�╶���A�y�n��D���Ă������B����������������ɏ@���ʂ���⊮����������ʂ������̂����{�莛�ł������B�{��a�͂����������j�̒��ő��݂��Ă���B�����������̗��j�������ĖY��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���B ���݁A�^�@��J�h�͂��������ߑ�̋��c�j���������Ȃ̏�ɗ����āA �A�C�k�����Ƃ̌𗬁A���E���a�̎��g�݂��s���Ă���B �{��a�ɗאڂ��Ă���r������B���̒r�̐��͔��i���痬��Ă��邩��������B��ɏq�ׂ����A�ߋ��S��Ђɑ����Ă��铌�{�莛�́A�����ȍ~�A�h���ۑ�ł������B�����ɂȂ�Ƌ��s�s���s���̈����ړI�ɁA���i�̐����T���t�߂̏R��܂őa���H���������B�������瓌�{�莛�͓Ǝ��ŁA�R�ォ�瓌�{�莛�܂ł̍��፷�𗘗p���Ėh�Ηp��������������������Ƃ����B |
|
|
�{��a���̒��w�i�ɁB���͌�e�� |
�{��a���̉��G�����w |
|
�y���{�莛�E��e���z �ߑO10��40���A�Ăь�e���B���{�莛�E���̈ē�������������e�����ցB�s�������̔��Â��L����i�ނƁA�e�a���l��^�e�����u����Ă���{��d�̐^���ɂȂ�B�����ŁA�{��d�����������̂��⍜�i�����j�����߂���B����A�������ꂽ����k�ɂƂ��ẮA�S�N�z���̎v������芴�S�[�����̂ɂȂ����B�����āA��e���̗����琳�ʂֈړ����s�B |
|
|
�y�����z �s���I���ƁA���{�莛��ђn�����́u�����v�ցB���̒뉀�͍��̖����ŁA����O��E�ƌ��̂Ƃ��A�ΎR��R�ɂ���č�낳�ꂽ�r���V���뉀�B���̒��ɂ���u�Ւr���v�Ƃ����{�݂�݂���A���Η����ɐ�ۂ�ł����B �y�������z �H�����I����Ɠ��R�̐������ɎQ�q�A�[�H�͒��ƕ�����铤�����̘V�ܗ����u�����O�v�i�O��؉����ニ�j�A���s�̖�����\�����B |
�������ɂ���Ւr�� |
|
�_���u�C���喾�_�v |
���R���ځy�C���喾�_�z �ŏI���B�����ɓ���ɐ旧���āA���s�炵������̂���ꏊ�ɂ��ē������B�_���̒��S�E�V���ʂ�ɂ���C���喾�_�B�����́A�_���̕��q�����|�q���������ɏo���肷��O�ɕK��������邨�{���B�Ώ�̒ʂ�ɒ��ƁA�_���̐^�𗬂�锒��̊E�G�͉f��̃��P�ɂȂ邱�Ƃł��L�����B���̓��́A�V�Y�V�w�̑O�B��i�B�e�j���s�Ȃ��Ă����B �y���t���E�������E�m�a���z �_���炵������̂��钬�ƊE�G��������s�́A���t���E�������E�m�a���A�����ė��R�Ɗό����A���s����ɂ����B �Q���R���Ƃ����Z�����Ԃł͂��������A�e�a���l�䂩��̌Ù��A�����Ē��Ƃ����ďt�̋��s�i�������ł������B�i���j |
�t�̖@�v�ΏC�@�@�u�t�͐��J�֔�
�@�`2015�N5��10���`
|
|
|
|
�@�z����ῂ����T��10���A�t�̖@�v���ΏC����܂����B���̖@�v�́A�����̊J�c�E�ב��i���߉ޗl�j�̌�a���A��y�^�@���J�����e�a���l�̌�a���A��e���O�Z�E�E笜��t�̂����������ɊJ���ꂽ���́B�ߑ��a���̈Ӗ���ʂ��āA���������l�ԂƂ��Ēa���������Ƃ̈Ӗ����l���Ă������Ƃ��肢�Ƃ��Ă��܂��B �@�ߑO10���A�����̍��}�ŋs�A�Q�w�҂Ƌ��ɐ����炩�ɋ߂��܂����B�s��@�b�A���{�莛���k�ʉ@���炲�o�����ꂽ���J�^���֔Ԃ̖@�b�����������܂����B �@���J�搶�́A�܂��A�u���͕��i�ł����Ȃ������v�ƌ���ꂽ���I�E���M�҂̌��t�������A�����B������Љ�̖����w�E�A���ōl����q�ǂ������̌����b����܂����B���[���t�ō�Ƃ̐ؐV�厁�̌��t���Ƃ����āA�畆���o�Ƃ��Đg�̑S�̂Ŗ��������邱�Ƃ̑�����q�ׂ��A�܊��Ŋ����镧���������V�ł���ƁA���b������܂����B |
��e���@�u�u�v���C�@�`2014�N11���Q���`
|
|
|
|
�O���܂ŐS�z���ꂽ�J���オ��A���₩�ȓ��ƂȂ����Q�O�P�S�N�P�P���Q���i���j�A���n��̂��Z�E��P�O�l���Q�A��e���u�i�䖞���j������Ɍ��C���ꂽ�B �u�Ƃ́A�e�a���l�̂������Ɋ��ӂ��A�^�@��k�Ƃ��ė����Ԃ�@�v�B�^�@��J�h�̌�{�R�E���{�莛�i���s�s�j�ł́A���N�P�P���Q�P������Q�W�������Đ���ɋ߂��A�S������^�@��k���吨�Q�w�����B ���̌�{�R�̕u�ɐ�āA�S���̖����₲��k�̂�����ŕu���߂��邱�Ƃ���u�����z���v�Ƃ������Ă���B �����͌ߑO�P�O������s�E�䑭��䕶���܂�����A��Îᏼ�s�E�������Z�E�̐z�K�֗Y�搶����u���̂��̐[���E���̂��̏d���v�̍u��Ŗ@�b���������B �@�v��A�ɗ��ɂĕw�l���ɂ��A�V�Ăɉ����A�{�̐H�ނ������u���Ƃ��v���U�镑��ꂽ�B |
�H�G�ފ݉�@�v�E���̎Ғǒ��@�v �ΏC�i2014�N9��23���j
|
|
��N�A�H�G�ފ݂̒����E�X���Q�R���ɁA�u�H�G�ފ݉�@�v�Ȃ�тɕ��̎Ғǒ��@�v�v���܂����B ���̖@�v�́A�ފ݉�@�v�ɍ��킹�A���@�����̂���k���̎҂̒ǒ��@�v�B���ɂ��̈�N�ɕ��̎҂ƂȂ�ꂽ����N����ɓ����邲��k���Q�w�����B �����͌ߌ�Q������s�A���̌�A���@�̏O�k�ł������u�����Ă��閽-������Ƃ�������-�v�Ƒ肵�Ė@�b���s�����B |
��䋳����g��ÁE�ۗ{����
�������E�n�[�g�����h�������Ɂu�q�ǂ����h�v�J��
�`2014�N8��30���`31���`
|
|
|
|
�W���R�O������R�P���̂Q���ԁA��䋳����g�i����Ȃj��Ái��e�������ߐ��n��U�����j�ɂ��ۗ{���Ɓu�q�ǂ����h�v���J�Â��ꂽ�B ���̎��Ƃ́A�Q�O�P�P�N�R���P�P���ɋN���������d�͂̌������̂ɂ��A�������̍L�͈͂����˔\�����������Ƃ���A�q�ǂ������ւ̉e�������Ȃ�������g�݂Ƃ��ĊJ�Â��ꂽ�B ���ː��ʂ̒��łP�O�O�}�C�N���V�[�x���g�ȉ��̒���ʔ픘�̉e���ɂ��ẮA�Ȋw�I�ɂ܂��悭������Ȃ��Ƃ��낾���A���ː��̉e���ɂ���臒l�i���������j���Ȃ����ƁA�q�ǂ��͑�l�ȏ�ɉe�����������ƂȂǂ���A�̓��Ɏ�荞��ł��܂������ː��j��E�Z�V�E�������o���邾���̊O�ɏo���Ă����邱�Ƃ����߂��Ă���B �����ŁA�����n��̊O�ŗV�Ԃ��Ƃ��o���Ȃ��q�ǂ���������˔\�����̐S�z���Ȃ��n��ŁA�v��������V�сA�H�������邱�ƂŁA�����ł����C�ɂȂ��ĖႨ���Ƃ�����悪�ۗ{���ƁB ����́A��������{���s�̎q�ǂ������y�ѐe�䂳��Q�O�l�قǂ��Q���A�X�^�b�t�͐��n��̎��@�̎��m�����k��A�Z�E�ō\������A��R�O�l���Q�������B �����́A�n�[�g�����h�ŊJ��̂��ƁA�����Ƃ̐G�ꍇ����{�[���V�сA�S�������Ȃǂ��y���B���̌�A�h���{�ݓ��̉�������A�o�[�x�L���[�ɐ�ۂ�ł����B����̒��ߊ���ɂ́A�ԉ����A�q�ǂ������͑��т������B
���̎��g�݂́A�q�ǂ������݂̂Ȃ炸�A���X�A���˔\�̉e�����l���Đ����𑗂��Ă���Ⴂ���ꂳ��₨�����A���̊Ԃł��A���̃X�g���X����������鎞�Ԃ��߂����Ă����������߁B��e������́A�Z�E�E���Z�E�炪�Q�������B |
��䋳���Á@�R�E�P�P�@�����{��k��
�u�S�ɍ��ޏW���v���J��
�`�����@���E���E���̖���a���`2014�N5��22��
|
|
�u�S�ɍ��ޏW���v�i�ȉ��A�W���j�͐k�Ђŋ]���ƂȂ�ꂽ���X�Ɏv�����A�S���Ȃ������A��Q�ɑ���ꂽ���A�x���҂ȂǁA���ꂼ��́u���̂��v��a���A�k�Ђ�S�ɍ��ݖY��Ȃ����Ƃ�����ĊJ�Â��ꂽ���́B�k�Ћ]���҂̎O����ɂ������N�R���ɊJ�Â���Ĉȗ��A�Q��ڂƂȂ�B�@ �@�J�Ãe�[�}�́u�����i�ʂ��䂢�j�v�́A����̃Q�X�g�ł���̎�E�����o�I�q���k�Ќ�ɋ]���҂Ɏv����y���č��ꂽ�̂���ؗp�������̂ŁA�L������Ŏg�p����Ă��錾�t�B�����́A���k���ݒn��⌴���̔�Ў҂͂��߁A�x���ҁA����k�ȂǁA��P�O�O�O�l������B��e������15�l���Q�������B �u�W���v�͂R���ō\������A�ߌ�P���ɖ����J���J��B�����̉��ŋs�A�����Łu������Ȃ����Ȃ��̐��A�Ί��z���v�Ƃ������t�Ŏn�܂�w�\���x���ǂݏグ��ꂽ�B ��Î҂ł���z�K�֗Y�E��䋳�拳���c���̈��A��A�Ìy�O�����t�҂̉��t���n�܂����B���͂̂���Ìy�O�����̉��t��A���k���\���閯�w�̉̐��͊ϋq�𖣗������B�܂����t�����ތ`�ŁA�{��E���E�����̔�Ў҂U�l���k�Г����̏�v���ɂ��Č�����B���ɁA���˔\����c���q�ǂ�����邽�߂ɔY�ꂵ�ޏ����̌��t�ɗ܂���l�����������B �@�Ō�ɉ̎�̉����o�I�q���o��B�悭�m����u�m�����v�u�S���{�̃o���v���߁A�u�����v�u���ǂ��ɂ��܂����v�Ȃǂ��I�����B |
|
�����{��k�Ђ���R�N�ڂɂ�����Q�O�P�S�N�T��22���A�u�R�E�P�P�@�����{��k�Ё@�S�ɍ��ޏW���`�����@���E���E���̖���a���`�v�i�^�@��J�h��䋳���Áj���A��䍑�ۃZ���^�[�����ɊJ�Â���A�k�Ђ̔�Ў҂��͂��߁A���E�{��E�����ȂǁA��P�O�O�O�l�����ꂳ�ꂽ�B�ʐ^�̓t�B�i�[���B�E����Q�Ԗڂ������o�I�q����B �@ ���I�[�v�j���O�B�k�Ћ]���Ғǒ��́u���Ƃ߁v�B ���z�[���̊O�ɐ݂���ꂽ���������L��B���ݏZ��̕��X��x���҂Ȑ��삵����i���̔�����A�����̗���҂��w�����Ă����B |
�@�u�t�ɐΓc�G�掁�����}�����A�t�̖@�v�ΏC
�@�@�Q�O�P�S�N�T���P�P��
|
|
�t��炩�ȂT���P�P���A�t�̖@�v���ΏC���ꂽ�B���̖@�v�́A�����̊J�c�E�ߑ��i���߉ޗl�j�̌�a����A��y�^�@���J�����e�a���l�̌�a���A��e���O�Z�E�E笜��t�̌䖽�������ɊJ���ꂽ�@�v�B�{�����ʂɂ͒a�����̉Ԍ䓰�����u�A�{���ɂ͌ܐF�햋�A�{�����ł͌�{�� �ߑO�P�O���A�����̍��}�ŋs�A�Q�w�҂Ƌ��ɐ����炩�ɋ߂�ꂽ�B�s��A�@�b�B�u�t�͌S�R�s�E�������Z�E�̐Γc�G��搶�A�u���炩�ɐ�����v�Ƒ肵�Ă��b�����������B �Γc���́A����ɕ����f����ꂽ�l�\����̒��̑�O�\�O��u�G���_��̊�v�������A�u�a�`�����ɓ�����ƊÊ`�ɂȂ�悤�ɁA�l�Ԃ́i���l�́j���ɓ�����Ə_�炩���Ȃ�B���������肢�ɐ����邱�Ƃ��A�_�炩�ɐ�����Ƃ������Ƃł��v�ƁA���ꂽ�B �@�b��A�쎝���ɑ����āA���Ƃ����������B |
����ɕu���C
�]�u�t�́A���킫�s�������Z�E�̓����a�����] |
|
|
�@�v�̗l�q
���b������u�t�̓����� |
�H����ƂȂ����Q�O�P�R�N�P�P���R���A����̐^�@���@���炲�Z�E���P�O���o�d�̂��ƁA�u�i�䖞���j�����C�������܂����B �s�́A���M��i�^�l��ډ��j�E�O���a�]�i�ܓ��j�E����Ői�߂��A����Ƃ͈قȂ�_�C�i�~�b�N�Ȑ����ɁA�{���͏I������]�C�ɕ�܂�Ă��܂����B�����āA�䕶�u�a��l�v�̔q�ǂ�����܂����B ���ɁA�O�N�Ɉ��������āA���킫�s�������Z�E�̓����a�������A�u�V���Ɉ��Đl����s�����v�Ƒ肵���@�b�����������܂����B�������́A����ɂȂ��ĕG�̐������܂邱�ƂŋN��ɂ݂��ɋ����A�u��\�҂͎���O���M��ƌ�����������Ȃ����A�����Γ�����O���Ƌ�����̂��O���B���O���͎��̗����ʒu���ς��Ƃ����s�ł��v�u�Z���ɐU���Đ�������̂��}�v�B���ꂪ�A�얳����ɕ��������Ƃ��Đ�����̂���y�^�@�Ȃ̂ł��v�ƌ���܂����B �܂��A�O���̂Q���ɂ͌�ߖ邪�܂�܂����B |
�H�G�ފ݉�@�v�E���̎Ғǒ��@�v
�ΏC
�]���{�莛�J��E���@��l���Â�Ł]2013�N�X��23�� |
|
|
���₩�ɐ��ꂽ�H�G�ފ݂̒����̂Q�O�P�R�N�X���Q�R���A�u�H�G�ފ݉�@�v�E���̎Ғǒ��@�v�v���ΏC�������܂����B���̖@�v�́A�̐l�ƂȂ�������k�̂���J���ÂтA���O���̋����������ł��B �Q�O�P�R�N�͓��{�莛�J��̋��@���F��400����ɂ����邱�Ƃ���A�܂��A��l�̂����U�Ɋw�Ԃ��Ƃ��e�[�}�ɁA���Z�E�����b�����܂����B�����āA���{�R�����삳�ꂽDVD�u���@��l����v���ӏ܂��܂����B |
��f���ꂽDVD�u���@��l����v �i���{�莛����E��f����35���j |
�t�̖@�v �ΏC
�]�ߑ��a����E�@�c�a����E�O�Z�E�䖽���]2013�N5��12�� |
|
|
|
�Q�O�P�R�N�T��12���A�����̂��Q�w�̒��A�u�t�̖@�v�\�ߑ��a����E�@�c�e�a���l�a����E�O�Z�E�䖽���\�v���ΏC����܂����B�@�b�ɂ́A�S�R�s�E�������Z�E�̐Γc�G�掁�����������A�k�Ђ⌴���ЊQ�ȂǁA�������鎞��ɂ����āA��������������Ӗ��͉����ɂ��āA���b�����������܂����B |
|
�u�₩�ȓV��Ɍb�܂ꂽ�T��12���A�u�t�̖@�v�v���܂�܂����B���̖@�v�́A�J�c�E�ߑ��̌�a���A�@�c�E�e�a���l�̌�a���A�����đO�Z�E�̌䖽�������˂ċΏC���ꂽ�@�v�ł��B �ߑO10���A�����̍��}�ŋs���J�n�A�w�䕶�x�̔q�ǂ�����܂����B�����Ė@�b�B��N�Ɉ��������A�S�R�s�E�������Z�E�̐Γc�G�掁�ɂ��o�����������A�u�����邱�Ƃ̑���v���u��ɁA���b�����������܂����B |
|
���g �������C��
�`�菟���Z�E�u�t�ɊJ�Á` |
|
|
|
�Q�O�P�R�N�S���T���A���g��Â̓������C��A��e����ɗ������ɊJ�Â���A���g���̏Z�E�Ȃ�тɖ�k���35�l����u���܂����B����́A�菟���Z�E�̐M�y�G�������u�e�a�̘ŋ��v�̍u��̂��ƁA���b����܂����B ���͂܂��A�u��ɂ��ĐG��A�u�s�́t�͏��L�i�ł͂Ȃ��A�e�a���[�����������Ƃ����Ӗ��v�Əq�ׁA�e�a���l�������������u�^�@�v�Ƒ��̕����Ƃ̈Ⴂ������܂����B�܂����l��������u��Áv�Ɩ���������Ƃɂ��āA�^�@�̖@���̓����ɕ���q���Ӗ�����u�߁v���t�����Ă��邱�ƂɐG��A�u�e�a�̏��ɂ́u�߁v��t���ĂȂ��ӏ�������B����͕���q���ǂ����̉ۑ肪���邩��B���͂��̐l���v���N�����B��ÂƖ���点���@�R�Ƃ̏o����������v�ƌ���܂����B |
���̎���ɑ�������悤�Ȍ`�ŋ߂Ă����䉓��
�`2012�N11��4���ɕu�i�䖞���j�A11��3���Ɍ�ߖ�����C�`
|
|
|
�����a�� �搶 |
����̐^�@���@����10�l�̂��@���i�ق����イ�j�ɂ���Đ����炩�ɋ߂���@�v ��11��4�� |
|
�@�H����̉��₩�ȓV�C�ƂȂ���11��4���A�u�i�䖞���j�����C����܂����B�u�Ƃ́A�@�c�e�a���l�̌䉶�Ɋ��ӂ��A�^�@��k�ł��邱�Ƃ����o����䕧���ŁA�������^�@��k�ɂƂ��Ĉ�N�ōł��d���@�v�B����e���ł́A���N��P���j���ɉc�܂�Ă��܂��B �@�����́A���C�E�R���̏����������A�ߑO10���A�����̍��}�ŁA���n��ȂNj�J���̂��Z�E�炪�@���i�ق����イ�j�Ƃ��ďo�d����A�s���n�܂�܂����B�u�̂��߂́u���M��v�^�l��ډ��E�ܓ��Ƃ����āA����̐߂Ƃ͈قȂ�_�C�i�~�b�N�Ȃ��́B�Q�w���ꂽ����k���������炩�ɋ߂��A�{�����͐����i���傤�݂傤�j�������n��܂����B�����āA�s�̗]�C���c�钆�A�w�䑭��x�̔q�ǂ�����܂����B�w�䑭��x�͖{�莛�攪��̘@�@��l���e�a���l�̂����U�ɂ��ď����ꂽ���莆�B�d�X�����q�ǂ����̂�Â��ɕ����Ȃ���A�Q�w�҂͖����A�e�a���l�̂������������Ă��܂����B �@�s��A���킫�s�E�������Z�E�̓����a�������A�u�㐶�̈�厖�v�Ƒ肵�Ė@�b�����������܂����B�������́A�܂�2011�N3��11���ɔ������������{��k�Ђɔ����A�{�R��3����5���ɎO��ɂ킯�ċ߂���\�肾�������S�\��䉓���ŁA3���̌䉓���@�v�𒆎~���u��ЎҎx���̂ǂ��v���߂�ꂽ���ƂɐG��A�u50�N���ƂɌ䉓�����߂Ă������̓`���𒆎~���Ă܂ł���Ў҂Ɋ��Y���Ƃ������_�͕]���ł��܂��B�����p���ł������_�������p���ŁA���̒��ŁA���̎��㎞��ɑ�������悤�Ȍ`�ŋ߂Ă����̂��`���ł��v�Əq�ׂ��܂����B�����āu���̐��͏�y�ł��n���ł��Ȃ����A�������͒n�������A���̐���n���Ƃ��Ă��������Ă��Ȃ��B���̊�ɂȂ�̂����ʐS�B�v���ʂ�ɂȂ�Ȃ����E���O�k�����A���̂��Ƃ������ł���A�I�X�Ɛ����Ă������Ƃ��ł���̂ł��v�ƁA��y�̐��E�ɂ��āA�M���ۂ�����܂����B �@�@�b��A�Q�w�҂͌ɗ��Ɉړ��A�w�l�����r��U��������ցi���Ƃ��E�����j�ɐ�ۂ�ł��܂����B �@�܂��O��3���̌ߌ�2�������ߖ邪�߂��܂����B |
|
�H�G�ފ݉�@�v�Ȃ�тɖ�k���̎Ғǒ��@�v���ΏC
�`�k�Љ��ł��}�������䉓���̈Ӗ���������ފ݁`2012�N9��23��
|
|
2012�N9��23���A�H�G�ފ݉�@�v�Ȃ�тɖ�k���̎Ғǒ��@�v���ΏC����܂����B���̖@�v�́A�ފ݉�@�v�ɂ��킹�āA����k���̎҂�ǒ�����@�v�Ƃ��ĉc�܂�Ă�����́B �����́A�ߌ�2������s�E�u�䕶�v�B���̌�A���Z�E�̂��b�Ə�f���s���܂����B��f�ł́A��{�R�E���{�莛�i���s�s�j�����삳�ꂽDVD�w2011�N�@�f���ŐU��Ԃ�@�@�c�e�a���l���S�\��䉓���x�Ɏ��^����Ă�����̂̒�����A�u�f���L�^
�@�c�e�a���l���S�\��䉓���v�Ɓu�����{��k�Ђ���������́v���ϗ����܂����B ���@�ł́A��{�R��2011�N3������5���ɏ@�c�e�a���l���S�\��䉓���@�v�����C����邱�Ƃ���A���̑����@�v�ɂ�����3�����{�ɎQ�q���s���v�悵���������Ă��܂������A���N3��11���ɔ������������{��k�ЂɂƂ��Ȃ��A�@�v�ւ̎Q�q�𒆎~����������܂���ł����B�Q�q�ł��Ȃ���������k���ꂼ��Ɍ䉓���Ɏv�����Ă����̂ŁADVD�̊ϗ��ɂ���āA���߂āA�k�Љ��ł��}�������䉓���̈Ӗ���������ފ݂ƂȂ�܂����B |
�t�̖@�v �ΏC�]�ߑ��a����E�@�c�a����E�O�Z�E�䖽���]
�`�u�k�Ќ���ǂ������邩�v�`�@�@�@�@�@�@�@�@2012,5,13
|
|
|
�Γc�G��搶 |
�@�v�̗l�q |
|
2012�N5��13���A�����̂��Q�w�̒��A�u�t�̖@�v�\�ߑ��a����E�@�c�e�a���l�a����E�O�Z�E�䖽���\�v���ΏC����܂����B�@�b�ɂ́A�S�R�s�E�������Z�E�̐Γc�G�掁�����������A��k�Ќ�A�������͂ǂ̂悤�ɐ�����悢�̂��ɂ��āA���b�����������܂����B���̖@�v�́A�J�c�E�ߑ��̌�a���A�@�c�E�e�a���l�̌�a���A�����đO�Z�E�̌䖽�������˂ċΏC���ꂽ�@�v�ł��B �@�ߑO10���A�����̍��}�ŋs���J�n�A�w�䕶�x�̔q�ǂ�����܂����B�����āA�S�R�s�E�������Z�E�̐Γc�G�掁�Ɂu�k�Ќ���ǂ������邩�v���u��ɖ@�b���܂����B�Γc���́w����L�x�ɂ����n�k�L�^�ɐG��Ȃ��獡��̒Ôg��Q�E�����ЊQ����w���Ƃ��q�ׂ��A�u�����⍬���̐��́A�V�������̂����ݏo����镪��_�v�u�l�Ԃ݂͂�ȍ����q�ɉ��₩�ɐ����邱�Ƃ�����Ă���v�ƌ���܂����B |
|
�ފ݉�@�v�E��k���̎Ғǒ��@�v�ΏC�`��n�ɐ�����`
2011,9,23
|
|
�@����9��23���A�H����̒��A�ފ݉�@�v�E��k���̎Ғǒ��@�v���ΏC����܂����B���̖@�v�́A���̎҂ƂȂ�ꂽ����k��ǒ�����@�v�ŁA���ɁA�N����ɂ����邲�⑰�ɂ��Q�肢�������Ă���܂��B���N�́A�����{��k�Ђɔ����Ôg�̋]���ƂȂ�ꂽ���̂��⑰���Q�w����܂����B�@�v�ł́A�ߌ�2������s�E�䕶�q�ǁB�����Ė@�b���܂�܂����B �@�@�b�ł́A�u��n�ɐ�����v�Ƒ肵�ĕ��Z�E�����b���܂����B�@�b�̒��ŕ��Z�E�́u���̂��т̑�k�Ђ́A�������̉���D���Ă��܂����̂��B���Ƃ����l�Ԃ�����܂Ő����Ă������ƁA���̑S�̂�����Ă���̂ł��v�Ɩ����N�A�u�l�Ԃ͑�n���琶�܂�A��n�ɗ����Đ����A�����s����Α�n�Ɋ҂��Ă������݁B���y���������Ƃ��Ă��A��n���̂��͎̂����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���A���ɐ����Ă���A���́u���̂��v���̂��̂̒��ɐl�Ԃ������Ă����悤�ȑ�n������v�ƁA�l�Ԃ̐S�̕����ɂ��Č���܂����B |
|
�l�X �����{��k�� �����]��Ôg��Q�ƌ����k�Ё] 2011,8,6 |
|
2011�N3��11���A�ߌ�2��46���A�{�錧�����͂��ߓ����{���ݒn��S�̂�k���Ƃ���}�O�j�`���[�h9�̋���n�k�́A�ő�k�x7���̗h����ϑ����A�ꏊ�ɂ����20�����̍����̑�Ôg�������A���k����֓��̉��ݒn������ݍ��B�܂��A�����d�͕�����P���q�͔��d���Ő��f�������N���A���ʂ̕��ː���������o�A���܂������̌��ʂ������Ȃ��B ���ҁE�s���s���҂����킹20,631�l�i8��1�����݁A�x�@�����\�j�Ƃ������\�L�̑�k�Ђ���T�����]��A�����E�������i�ވ���ŁA���ݒn��ł́A���S���ꂽ���Z�E�₲��k�����鑼�A���ەs���҂̑{���͍�����q���ɂ߁A������]�V�Ȃ�����Ă�����X������ł���B |
|
��k��i�R�����j�Ôg��Q -�ꕔ����̂���k���-
�{�錧�E�R���� �@3��11�A�ߌ�2��46���B���܂łɌo���������Ƃ��Ȃ��傫�������h�ꂪ�����܂����B�n�Չ��ǂ����n�Ɍ��{�����A�~�V�~�V�Ɖ��𗧂Ăėh��A�����̕���㉺�ɑ傫�������Ă��܂����B����3����A����k�̈��ۂƔ�Q�m�F�̂��߁A�Z�E�ƕ��Z�E���n���k������K�ˊm�F�A����A�{�R�̎������E��䋳�����֕������܂����B���������̂���k��ł͊������̔j���̏Z������ق��A��n�̐��y���n���ׂ���N���������������܂������A�����҂͂��Ȃ��������悤�ł��B����A���O�ł͎R�����̂���k��ꌬ���Ôg�ɂ���đS�A���݁A����Ă��܂��B�S���A�����Ȃ�тɖ�����ɂ���k�̔�Q��E�������A�Z��S��ƂȂ�������k�ɑ��Č������𑗂邱�ƂƂȂ�܂����B����A�Z�E�ƕ��Z�E���������ƎO�ܖ{���i����ꎮ�j�����͂������Ă��������܂����B |
|
�����k�Ё@�����d�͕��������\ �L�܂���˔\�����̋��|�ƕs�� �\ 3��11���ɋN��������n�k�́A��Ôg��Q�����������ł͂���܂���ł����B�u���̃G�l���M�[�v�u���S�v��W�Ԃ��Ă������q�͔��d�����������܂����B ���̂��������͕̂������Q�]���ɂ��铌���d�͕�����P���q�͔��d���ŁA���q�F���������f�����B���̒��ォ���ʂ̕��ː����������o���Ă���ɂ��ւ�炸�A�����d�͂�o�ώY�Əȕۈ��@�A�����Đ��{�͗\�z�������˔\�����̏���������B���A�u���S�f�}�v�𗬂������A���������A���ɁA�q�ǂ����������E�f��Z�V�E���ȂǑ�ʂ̕��˔\�𗁂тĂ��܂��܂����B�������Ӗ������{�́A���ʁA�����������Ƃ����d��ȉ߂���Ƃ����̂ł��B�d�͉�Ђ����{���g�D�I�ӔC�̉���ƕېg�����S��S�ۂ����U����x�点�A���ʁA���̂������������悤�Ƃ��Ă������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂����B ������������ꕔ�A�����҂Ȃǂ̊Ԃł́A�n�k����ɑS�d���r���A���q�F���̘F�S���n�Z�i�����g�_�E���j���A�n���������̔R���_�����q�F��˂��j���Ă���Ǝw�E���Ă��܂����B�������A�����̑��V���Ђ�e���r�͖������A�����̂́A�Ȃ�ƁA�Q�����ȏ���o���Ă���ł����B�������A�d�͉�Ђ̉���Ăł��B ���ː���������o���A�����̌��ʂ��������Ă��Ȃ����A�������́A�ł��������������W���A�����ēI�m�ɕ��͂����������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B ����A���˔\������O��Ƃ��Đ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ȏ�A�O���픘�Ɠ����ɁA�����H���̐ێ�ɂ�萶��������픘���ǂꂾ���Ⴍ���Ă���������ł��B ���˔\�����ɂ����┒���a�̃��X�N����q�ǂ����������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B |
|
�t�̖@�v�E�����{��k�Ћ]���Ғǒ���ΏC 2011,8,6 |
|
5��8���A�t�̖@�v���ΏC���܂����B��N�A�ߑ��Ɛe�a���l�̂��a�����j���F�ʂ����������ł����A���̂��т̐k�Ђ��ӂ݁A�k�Ђŋ]���ƂȂ�ꂽ���X�Ɏv����v���@�v�Ƃ��܂����B�����͋s��A��Îᏼ�s�̕����~��搶�ɂ��@�b�����������܂����B |
|
�R�E�P�P�����{��k�Ђ���S���� ��Ôg��Вn�́u���v��K�˂�
�`���O���c�s�E��D�n�s�E�O�����`�����` 2011,6,20 |
|
2011�N3��11���A�ߌ�2��46���A�{�錧����k���Ƃ���}�O�j�`���[�h9�̋���n�k�́A�ꏊ�ɂ���Ă�30�����̍����̑�Ôg�������A���k����֓��ɂ����āA�����{�̍L��ɓn���ĉ��ݒn������ݍ��B ���ҁE�s���s���҂����킹23,355�l�i6��13�����݁A�x�@���܂Ƃ߁j�Ƃ������\�L�̑�k�Ђ���3�����]��A�����E�������i�ވ���ŁA�s���s���҂̑{���͍�����q���ɂ߂Ă���B������ɂ����Ă��A���E�{��E�����̉��ݒn��ł́A���܂��A���ۂ��킩��Ȃ����Z�E�₲��k�����鑼�A��������]�V�Ȃ�����Ă�����X������B �k�Г����A��́A�����N�������̂��B����A��䋳��i���E�{��E�����j�ŒÔg��Q�̑傫�������n��̈�A�C��g�̗��O���c�s�E��D�n�s�E�O������K�˂��B �����S�Ȍ����ɑr�����ƋF�� 6��2���A���J�B���͐�䋳���u��ޔǁv�Ƃ��Ď�ޒn�Ɍ������B���O���c�s�ɓ����ĊԂ��Ȃ��p�[�L���O�ŁA����A�ē������肢�����l���Ɨ��������B�C��g�̐������Z�E�E�|�쌺�~�����B�|�쎁�͑�Ôg�̔�Q�����O�����o�g�B���݁A�C��g�̕��g���ł�����B���ꂾ���ɁA����̑�Ôg�ɂ���āA�����g�̂��Z�E���s���s���ƂȂ�A�V�炳�S���Ȃ������Ƃ̏Ռ��͑傫���A�h���E�߂��݂�z������ɓ�Ȃ��B
�@�Ԃ𑖂点�邱��5���B���O���c�s�X�n����܂��x�O�ł���͂��̎R�����̓c���ɂ́A�Y�����̂悤�Ȃ��̂������炱����ɂ������B�����āA�R��������ƁA���͂̌i�F���A�˔@�A��ς���B���n���A���I�Ɖ�������ʂ̎c�[�̎R���_�X�B���̂قƂ�ǂ��A�Ôg�ʼn���������j�ꂽ�Ɖ���ԁA�H��̋@�B�ȂǁA�l�X�̐����������l�܂������̂��B�l�X�̐����̊�Ղ����ꂩ��D���j���������̌��i�́A�k�Е����ʐ^�Ɣ�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ����炢�A�����������Ŕ����Ă���B�������A���̐��S�ȏ��u�����v�̏o�����Ƃ��Ď��ɂ́A���܂���c�����B���̔߂��߂��錻����O�ɁA�����ł��Ȃ����Ƃւ̑r�����ƁA�����F�邱�Ƃ����Ȃ��Ƃ����S���������A�C�����A���ق̒��ɂ����āA���ݏグ�Ă���܂�}����藧�Ă��猩����Ȃ��B �@���������K�ꂽ�̂́A��k�Ђ���3������Ƃ����āA������Ƃ�{�����e�B�A�̈ړ��ɕK�v�ȎԂ��ʂ�邾���̓��H�́A������x�A�m�ۂ���Ă����B���A��ʐ���������M���@�͂Ȃ��A�H�ʂɂ͉��D���������Ă����B���̗��e�ɂ͑�ʂ̎c�[���R�̂悤�ɐς܂�Ă���B ���{�i�����P����20���̑�Ôg �@�u�����ŎԂ��߂܂��v�Ɗ|�쎁�B�{�i�����������ꏊ�ɓ�������B��Ôg�̏P�����A���́A�{���ƌɗ��͐Ռ`���Ȃ��B�����{���̊�b�ƎR��̐Βi���c���Ă��邾���ł���B�u�����A���̐Βi�������āA�{�i���ɓ����Ă��܂����v�B���j������������Â��ȘȂ܂��ł������{���ɁA�����B����ȋL���Ƃ͑S���قȂ�i�F�ɁA���͌��t���������B
���{�i���ՁA�����I�̒��ɂ������和 �u�I�����W�̏d�@�������Ă���A���̕ӂŌɗ��̂Q�K������������܂����B�����āA���q����̗�������́A���̌ɗ����牟���o����āA�j���Ȃ��痬����Ȃ���H�蒅���ď���������ł��v�B ���O���c�s�͐l��23,000�l�̓s�s�B���̑����̐l�����{�S�i�Ɏw�肳��Ă���i���n�E���c�����C�݂���قNj߂��s�X�n�ɋ��Z���Ă���B�����{�i��������A�C�݂���A�����ɂ��Ă킸����1.4�����̋߂����Ƃ́A���̎��܂ŁA���͂��܂�ӎ����邱�Ƃ͂Ȃ������B�������A�Ɖ���r���̑������Ôg�ɂ���ė�����A���E���Ղ���̂��Ȃ��Ȃ������A�{�i�����������ꏊ����C�݂������邱�Ƃ�m�����̂ł���B���̗��O���c�s���A��20�����̍����̑�Ôg����u�ɂ��Ĉ��ݍ��݁A�����j�s�������B ���Ôg���O�A�{���ɂ������Z�E ����̒Ôg�ɂ���āA���O�Ȃ���{�i���̖V�炳��Ǝ�V�炳�]���ƂȂ�ꂽ�B�����āA���Z�E�̍��X�A������́A���܂��s���s���ł���B�����āA���{�����܂���������Ă��Ȃ��B �u���Z�E�͖{���ɂ����ƌ�����ł��B�����A���{�������ł������Ȃ���A�����ē����Ȃ���Ƃ������ƂŁA�Ôg�������Ƃ��{���ɍs���āA���{���������o�����Ƃ��Ă����̂��ȂƑz�������ł��B���{�����Z�E���o�Ă��Ȃ�����c�B����������ƁA���Z�E�����{��������Ă���\��������܂��v�Ɗ|�쎁�B ����܂Ől��{�A���@�̋���������Љ���ɗ͂�s�����Ă������Z�E�����ɁA����k��n��Z������̐M�����Ă��B���̘b���f�����Ƃ��A���������A���Z�E�Ɏ�����킹�邵���Ȃ������B�u�ꉞ�A�ڎ��ł̑{���͏I������̂ł����A�d�@�ŕЂÂ��Ȃ���A�����o�Ă������Ƃ��~�߂āA�Ƃ����`�ł��傤�ˁB���c�����C�݂̍��������Ă����̂ŁA���O���c�͓y�ɖ��܂��Ă�����̂��A���\�A�����Ǝv���܂��B���܂��ɁA��������̐l���������Ă��܂���B�������ꂽ��̂��c�m�`���肳��Ă��A�]���̓������Ȃ�����́A���ʂ����N�ɂȂ�悤�ł��v�B �����Ԃ�3��11���Ŏ~�܂��� �{�i������̎��ӂ�����ƁA�����ׂ��ꌴ�`�𗯂߂Ȃ��ԁA�傫���c�߂�ꂽ�����̓S�╲�X�ɂȂ����R���N���[�g�̉�A���̒��ɁA�u�^�@��J�h �{�i���v�ƒ���ꂽ�和�������B���āA�Q���̓����ɂ������和�����̎c�[�Ƌ��ɒu����Ă���B�����āA����x�A�{�i���Ղɍs���Ă݂�ƁA�����ɂ͐Ԃ������h�Z���ƃA���o�������������ƂɋC�������B���炭�A�Ôg�ɂ���Ăǂ����炩���ꒅ�������̂��낤���B�A���o���̎ʐ^�ɂ́A���D�ɓ����ĉx�ԓ�����A�c��ƎB��c���̎p�ȂǁA���₩�ɗ���鐶���̏�ʂ��L�^����Ă����B���̓���̎��Ԃ��A3��11�������Ɏ~�܂��Ă��܂����B
�Ôg�ŗ��ꒅ�����A���o�� �����c�����́u��{���v �{�i���������ɂ��āA���āA�������Z���������c�����C�݂�������ꏊ�ɎԂ𑖂点�Ă݂�B���S�ɂȂ����h��������āA�Ôg�̔j��͂̐��܂����Ɏ��͐�債���B���l�Ɩh���тƎs�X�n�����傫�Ȗh���炪���������Ƃ��L�����Ă������炾�B����ɋ������̂́A�n�Ղ��傫���������āA�C�ݐ����s�X�n���ɂ��Ȃ���肱��ł��邱�Ƃ������B �u�`���n�k�̒Ôg�̎����A���a8�N�̎O���̑�Ôg�̎����A���c�����͗������Ƃ������Ƃ͂Ȃ������B���������邵�h��������邵�A�Ǝv���Ă�����Ȃ����ȁv�B�n�k��������Ôg����������܂ł̎��Ԃ������Ă��������Ȃ������l�X�����������������B �u�����́A�n�Ղ��������Ă���̂ŁA�g�����Ȃ��悤�ɐ�ς�ł��܂��B����͋��ꂾ���ǁA�C�ɕ����ԋ���ɂȂ��Ă���B�h���炪�����ꏼ�����Ȃ����A���l�Ȃ̂����Ȃ̂��A������Ȃ��Ȃ����v�ƁA���v���ɒ^��Ȃ���b���|�쎁�B���́A���̋߂��ɂ́A�|�쎁�����Z�����ɒʂ�����Z�����������A�Ôg����������Q���Ă����̂��B ���c�����C�݂����n���ƁA�ӂƈ�{�̏����ڂɗ��܂����B�h���т̏����Ôg�ɂ���āA���̂قƂ�ǂ�������Ă��钆�ɂ����āA�ς��������A�����B��́u��{���v���B���c�����s�ł͕����̏ے��Ƃ��Ďc�����Ɨ{����Ƃ����Ă��邻�����B ���L�����ꂽ�A���Ă̊X���� ��D�n�s�������Ԃ̒��ŁA�u���������[�\���B���̊p���p�`���R������B�����Ƀ��X�o�[�K�[���������c�v�B�ē������Ă���|�쎁�̊�ɂ́A�k�БO�̊X���݂������ɋL������Ă���B���������ꂩ��D�������Ă��܂�����Ôg�B�������A���t�����̂قƂ�ǂ́A�C�ɑ��鍦�݂����ɂ��Ȃ��B�ނ���A�܂��l�ɏZ�݁A�����������Ƃ����C�����������̂��Ƃ����B����́A�V�N�ȋ���ނ��l���O���̖L���ȊC�́A���t����̐������̂��̂����炾�B �O�����z�었�ɓ�����������ŎԂ��߂�B���n���ƁA�����ł��A�X�n�Ɖ��������X�ɒÔg�Ŕj�ꂽ�ؑ��Ɖ��̎c�[����ʂɎR�ς݂ɂȂ��Ă���B���̒��ŁA�S�ؑ���̌����������������h�����Ďc���Ă���B���̈����D�n�s�����O���x���B�|�쎁�͒n�k��������1���ԂقǑO�܂ŁA���̂R�K���Ă̖�����2�K�ɂ����Ƃ����B�u�Ԃ��߂āA������2�K�ŗp���������Ă����̂ŁA�A�肪����������ƒx��������A�Ԃ�������Ă��܂����B���̒n��́A�Ôg���^���ʂ��痈����ł��v�B�x��������ƁA�Ôg�����̉�ƂȂ��āA�����̒���˂������Ă������悤�Ȋ������B���̔j��͂́A����Ȗh����ɂ����̒܍��X�����c���Ă���B ���Ôg�P���ʼn����������̂� �u���̖h�g��̏������ĉ������B�Ôg�ł����Ȃ��̂�������ĕt�������ł��B���傪�ꖇ�A����܂������A�Ôg�Ɍ������̑D����̕��ɗ�����Ă��܂��B�Ôg�́A�W�������4���قǂ̖h������z���Ă��܂����v�B �Ôg�������A�|�쎁�͍���ɂ��鎩�V�̋�������A�P������Ôg�̈ꕔ�n�I�����Ă����Ƃ����B
���䂩�猩���낷��l���` �u�Ôg�����Ă����Ȃ���Ƃ������̂�����܂����B�Ôg������O�A�C�̒ꂪ�n�b�L�������܂����B���͂����Ō��Ă��邩��A�u�Ôg���A������A���Č����Ă����v�Ɖł���Ɍ����܂����v�B�Ôg�ɂ���ē]������傫�ȋ��D��A�X�����ݍ��܂�Ă����ɉ����ł��Ȃ������ƁA�X�ƌ��ꂽ�B �u���̏W����10�l���炢�S���Ȃ��Ă��܂��B�����āA�܂�6�l���������Ă��܂���v�B�S���Ȃ����l�̒��ɂ́A�n���̏��h�c���������|�쎁�̒m�l���܂܂�Ă���B�����߁A���U�������Ă��钆�ŁA�O�ƌ�납�痈���Ôg�ɋ��܂�ė����ꂽ�Ƃ����B�u���̈��y�ŁA�n���ł����Ə��N�싅�������Ă���Ă����l�������B�����A�����̃e�g���|�b�g�̂Ƃ���Ō��������B3��11�����玞�Ԃ��~�܂��Ă���悤�Ȋ��������āA���܂��ɁA�{�[���Ƃ��鎞�������ł��v�B ���̑�k�Ђ���3�����o�������A�ē������Ȃ���|�쎁�́A���Đ��������Ă����W���̐l�X�̎p������Ă����B�u�v���n�u�������Ă��邠���肪���X�������B���̏��X�̂����������Ƃ����������s���s���ł��B�����ɉ��������āA�����͒N�X����Ƃ���ƌ����Ă����Ȃ��ƖY��Ă��܂�����������ˁv�B�k�Ђ����ĒÔg�́A�����ɕ�炷�l�X�̉���D�����̂��B�|�쎁�̎p�ɂ́A����Ȑ����̋L����H��Ȃ���A���⎩�����Ă���悤�Ɍ������B ��������O�ց@��l�I �����āA��������ċA�낤�Ƃ���Ƃ��A�u�h����Ɏq�ǂ�������������Ŕ������Ŏʐ^���B���ĉ������v�Ɗ|�쎁�B�����Ɍf�����Ă����̂́A�N�₩�ȐF�ŏ����ꂽ�u�P�����O�ց@��l�I�v�Ƃ����Ŕ������B�Ôg�̔�Вn��K�ˁA�z����₷��S��Ɍ��t�����������������A�Ō�ɏo�������q�ǂ������̌��t�ɁA�ނ���A��܂���Ă���Ƃ́B�k�Ђ������߂��݂͐h�߂��āA���X�A��������̂ł͂Ȃ����A���̎q�ǂ������̃��b�Z�[�W�ɂ́A�����A�߂��݂���]�ɕς��Ă����悤�ȁA����Ȍ����������B
�q�ǂ��������������Ŕu������O�� ��l�I�v �����A�Ôg�ɂ���Đ�����Ղ������A�ٗp��D��ꂽ�����̕��X���s���R�Ȕ��≼�ݏZ��̕�炵��]�V�Ȃ�����Ă���B���̂悤�Ȕ�Вn��̕����E�����̓��̂�͒����B���E����̎x���̗ւ��L�����Ă��鍡�A���������A�����E�����Ɍ����āA���ɁA������O�������ĕ����Ă��������Ǝv���B�����āA��k�Ђɑ������������������̐^�������Őe�a���l�̋��@�������Ă������Ƃ��A������̕����A���Ȃ킿�A�l�Ԑ��_�̕����Ɍq������̂Ǝv���̂ł���B���̂��Ƃɂ����āA���߂āA���������u�@�c�e�a���l���S�\��䉓���v�����}�����邱�Ƃ̈Ӗ����m���߂��Ă����ɈႢ�Ȃ��B�i�g�j |
|
�S�V���Ɂu���M��v�����a�`���U�E�C����` �Q�w�҂ւ��j�h�E�Î���U�镑���A�V�N���j��-2011�N1��1��- |
|
�@2011�N1��1���A�V�N���̕����u�C����v�i���サ�傤���j���܂�܂����B�����́A��N���ɍ~��ς�������ŕ���ꂽ�����ɁA�ЂƂ��튦�����ƂȂ�܂������A���݂ő������ꂽ�{���ŁA�荏�̌ߑO10������@�v���܂�܂����B���w�ƌ����A���Ԃł͐_�Ђw�Ŋ�������邱�Ƃ���ʓI�ɂȂ��Ă��钆�A��e���ł́A���l�̊肢�Ɏ����ς܂��A�O���҂Ƃ��Đ����Ă����S��V���ɂ��Ă������������ƁA�u���w�͕�ł����e���ցv���L���b�`�t���[�Y�ɌĂъ|�������Ă��܂����B �@�s��A�Q�w�҂́A�r�֔O�����q�Ȃǂ̋L�O�i�����A�ɗ��Ɉړ��B���j�h�ƊÎ��̐ڑ҂��܂����B��N�Ɉ�x�A�U������Î��́A�����e���̖����Ƃ��Ȃ�A�������g�̂����܂�ƍD�]�ł����B�@ |
|
�e�a���l�̂��������ӂ���u���C ���A���̂������Ȃ����Ă���`���̂��E���E���`�i2010�N11���U�E7���j |
|
���������i�N���b�N����Ǝʐ^���傫���Ȃ�܂��j�@�@���s�̗l�q�@�@�@�@�@�@�@�@���@�b�̗l�q |
|
�@�b������u�t�̊����i11/1�j�@�@ �@�@�@����̂������i10/27�j �@�@���Ƃ��̏����i10/31�j |
|
|
|
|
|
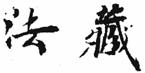

![�u��t�����v�]���Ҍ�����](news/img005.gif)

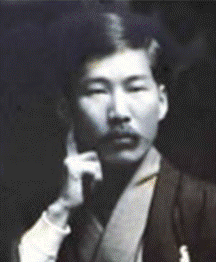



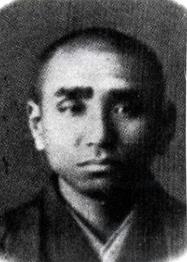













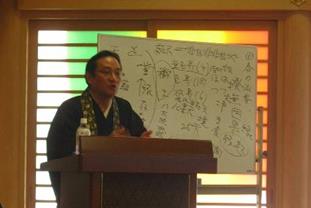










![shorenin02[1]](news/img069.jpg)
![gate[1]](news/img071.jpg)