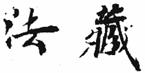法 話 |
|
2007年2月18日、福島県二本松市にある真行寺を会場に、「親鸞教室」(主催:真宗大谷派仙台教区)の第2回が開催され、講師の講義に先立って、当院の衆徒・釋弘道が話をしました。当日の抄録を掲載します。 ☆【はじめに】‐同朋会運動からの問いかけ‐ 「同朋会運動の趣旨」というテーマで少しお話しするようにということですが、この同朋会運動(※1)は、真宗大谷派が「家の宗教から個の自覚へ」というスローガンのもとで1962年から進めてきた信仰運動です。つまり、寺檀制度の中で、自覚的であろうと無自覚的であろうと代々受け継がれてきた浄土真宗という名の仏教を、私一人の目覚めの宗教として回復しようとする運動であったかと思います。そういうことから申しますと、同朋会運動を考えようとするとき、必然的に「あなたにとって真宗とは何ですか」「あなたにとって浄土真宗とは何ですか」という問いかけが突きつけられてくるのです。 そこで、私にとっての真宗との出遇い、これまで親鸞聖人の教えとどのように出遇い、どのように受け止めてきたのか、ということを中心にお話したいと思います。 ☆【幼年期のお寺のイメージ】葬儀会場・お経を唱える場所 私は、宮城県の蔵王山麓の小さな温泉町にあるお寺の長男として生まれました。父方の実家がたまたまお寺というご縁で、父は入寺したようです。しかし、隣町から旧本堂を譲り受けて移築し、寺号を仙台市から移して現在地で再スタートしたお寺ですので、現住職で2代目ということなります。人生で申しますとまだ産声を上げたばかりというところでしょうか。私が幼い頃、本堂自体は大変古いのですが、お寺としては新しいということもあって門徒戸数も少なかったのです。そこで、父は公務員をする傍らお寺の仕事をしていたので、お寺の仕事というと、日曜日には法事を勤め、たまにお葬式が執り行われるといったことで、ご門徒の方々と親鸞聖人の教えを聞くという「場」が殆どと言ってよいほどありませんでした。そんなことで、私がイメージしていたお寺は、いわゆる、葬儀会場であったり、語弊がある言い方になりますが、意味の分からないお経を唱える場所といったものでした。そこには、お寺に対しての夢や希望はないばかりか、ただ、お寺を継がなくてはならないという親の期待のようなものがあって苦痛でしかありませんでした。したがって、次第に、いつかお寺を飛び出したいという気持ちが募っていきました。そして、その気持ちのまま、京都で大学生活を送るようになりました。 ☆【大学時代に出遇った友人・先生・言葉】‐元気が出るのが浄土真宗‐ ところが、そんな私がもっていたお寺のイメージ、そして仏教のイメージを変えたのは、大学時代に出遇った友人、そして先生でした。 ある時、友人と酒を酌み交わしながら話をしていると、その友人は「仏教は君がイメージしているような、ちっちゃなものではない。もっと広いものじゃないのか。そして人間の悲しみや苦しみに寄り添っていくものなんだ」「元気が出るような、そんな学びをしていないのじゃないか。元気が出てくるのが真宗じゃないのか」と。友人が真剣な顔つきで仏教を語っていた姿を目の当たりにして私は、友人をしてこのように真剣に仏教の話を語らせるものは何だ、目を輝かしながら仏教の話をする友人は一体どのような仏教に出遇っているんだと思いました。 後日、その友人の勧めで、ある学習会に参加することになりました。その友人が言うように、その学習会に参加している学生、そしてその学習会を主宰している先生の口から出てくる仏教の言葉の数々は力強く、生き生きとしたものでした。そのとき思いました。人間存在の根底から元気が出てくるものが浄土真宗の学びだと。そもそも仏教を開いた釈尊は人間の根本的な苦悩を超えるために、約束された王位を棄てたのではなかったかと。 今思えば、先生や友人から多くの言葉をいただきました。思い出されるいくつかの言葉を紹介したいと思います。 出遇った言葉のいくつかを紹介します。 「霞を食って生きているものの言葉ではなく、大地に根を張って生きるもののから生まれた言葉が浄土真宗」 「生産道の宗教が浄土真宗である」、つまり、人間の営み、すなわち、子ども産み、育てている命の営み全体が浄土真宗なのだ、と。 「如来のご苦労は、たった一人の苦悩のためにある」 「親鸞聖人は一人、一切衆生の苦悩を一身に担って立っておられる。つまり、一切衆生の代表として如来の本願を受け止められたのである」 ☆【H先生との出遇い】 また、学習会主催の夏季研修会に出席をしたときのことです。その研修会に、真宗大谷派碩学であった曽我量深先生に師事をされ、曽我先生の晩年、お側におられたH先生(当時70歳前後)が講師としてご出席されていました。当時のH先生の言葉が今でも印象深く残っています。H先生は研修会場で初めて会うなり、まだ大学生であった若い私たち一人一人と握手をした後、「なんて凄いことなんだ。私は、50歳過ぎにしてようやく曽我先生に出遇うことができたのに、皆さんは20代の若さで、今、曽我先生の言葉に出遇っている」と涙を浮かべながら喜んでくださったのです。このH先生の姿には、どうして、涙を浮かべながら自分のことのように喜んでくれるのかと驚きました。そのH先生が私たちに向けてお話をされました。 「親鸞聖人が悪人の自覚というが、悪人というのは絶望じゃない。如来の絶対のお救いの眼に映った本当の自分を知らせていただく。自分自分というが、自分が自分を見ると絶望しかありませんよ。悪人の自覚というのは、如来の大悲の眼、絶対救うという大悲の眼に、本当の自分というものを映してくださっている。そこにはもはや絶望なんかありません」と。 このH先生の言葉が、先ほどの「真宗の学びは元気が出る」ということだと思います。如来の本願に触れたものは、世の中や自分自身に絶望しない、このH先生の言葉に出遇って、涙が出るほど本当に嬉しかったんです。あの当時は、絶望しかありませんでしたから。自分に絶望し、社会に絶望し、寺に絶望し・・・。絶望淵にある人間にとっては孤独しかありません。そういう状況にあってH先生の言葉は驚くほど心に響きました。 また、別の会合でH先生が同席していたときのことです。そのときH先生が私に対して、「本当に命を懸けて真宗を求め、曽我先生の言葉を求め、自分を求めているのか。命を懸けないで本当の自分に出遇うということはできません」と、本当に真剣にお叱りを受けました。その後続いて「どうか、生涯かけて命を懸けて求めてください」と。学生だった私はH先生に対して真面目に話をしていたつもりだったのですが、H先生の目には私の姿が不真面目に映っていたのでしょう。というよりも、心の不真面目さ、仏教の学びそのものに対しての不真面目さを見抜いていたのです。少なくとも命をかけて道を求めて生まれた教え、そしてその教えを命がけで伝えてきたのが仏教の歴史でありました。その仏教を学ぶには命をかけなければ駄目なんだということです。逆に言えば、命をかけなければ仏教は分からないし、本当の自分に出遇えないんだと。そのことをH先生は教えてくださったのです。そのときの出来事が20年ほど経った今でも、ずっと心に残っていて忘れることができません。そして、今でも響いています。H先生の願いに十分応えることはできていませんか・・・。H先生に対して、念仏の教えが一人の人間になられた方だと思いましたし、念仏の教えが本当の人間を生み出すのだと、そんなことを思いました。 ☆【真宗との出遇いは、真の人との出遇いの歴史】 このように、親鸞聖人の言葉に出遇っている人、すなわち、念仏者との出遇いによって、私が思い描いていたお寺のイメージ、浄土真宗のイメージは脆くも崩れ去りました。 最近、様々な言葉が氾濫し、軽くて耳障りの良い言葉が多くなりました。そういう中にあって、私たちが人生の中で本当に求めているのは、人間の血が通った真実の言葉でありますし、血の通った本当の人間との出遇いなのではないかと思います。ただ、真宗との出遇いということも、真宗というものが漠然とどこかに形としてあるというものではないと思います。そしてまた、真宗との出遇いによって何か今までの自分が立派になるとか、180度生き方が変わるとか、別のものになっていくとか、そういうことではないと思います。 私は、真宗との出遇いは真の人との出遇いだと思います。生死(しょうじ)という言葉で象徴されるように、人間の存在それ自体が持っている苦悩を越えるために、念仏の教えを手がかりに命懸けで道を求めた人がいました。つまり、念仏に生きる人との出遇いがあるのであります。阿弥陀仏が菩薩であったときの姿が法蔵菩薩ですが、その法蔵菩薩が世自在王仏と出遇い、一切の人々を救うために本願を発し、浄土を建立なされました。そして、念仏の教えの元になっている経典『大無量寿経』では釈尊と弟子の阿難尊者との出遇いが発端になって教えが説かれています。そして、浄土宗を開かれた法然上人と親鸞聖人が出遇っているのであります。 ☆【真宗の学び=新しい「見方」を教えていただく】 つまり、念仏の教えが具体的に「人」を生み出し、本当の意味で人が人と出遇いを遂げてきた歴史が浄土真宗だと思います。そして、真宗の教えとの出遇い、念仏に生きる人との出遇いによって何が変わるか。変わらないのが本当なんでしょう。念仏の教えによって何か変わると思っているけれども、そうではなく、どうにもこうにも変わらない自分というものを気づかせていただくのでありましょう。状況は已然として変わらないけれども、真宗の学びによって、そこに新しい「見方」というものを教えていただくのだと思います。 鈴木章子さん(※2)という方がおられました。この方は北海道のお寺の坊守さんであった方で癌を患い、闘病生活の中で日記をつけておられました。その日記の中に一句の詩があります。「変換」という詩です。
変 換 死に向かって 進んでいるのではない 今をもらって生きているのだ 今ゼロであって当然の私が 今生きている ひき算から足し算の変換 誰が教えてくれたのでしょう 新しい生命 嬉しくて 踊っています “いのち 日々あらたなり” うーん わかります」 (鈴木章子著『癌告知のあとで−私の如是我聞−』探求社より) とありますが、そういう「見方」ですね。言うならば、仏様の眼で社会を見、他人を見、自分を見る、そして仏様の眼で自分のいのちを見る。そういう見方を仏様によっていただく、これが真宗の学びの大事な点だと思います。そういう見方というものをいただくと、そこに、本当に同朋(どうぼう)という「友」を発見する。同朋というからといって、仲良しグループということではありません。「私」という人間ともっとも価値観の異なる人をも包んでいく言葉だと思います。ある意味では、自分にもっとも厳しく接している人をも同朋という言葉で包んでいける、そういう世界が同朋ということの中身だと思います。そこにはやはり、願いというものがあるのでしょう。 そういう意味では、同朋会運動は決して仲間づくり運動ではありません。仏様の願いのもとに、全ての人を同朋(友)として見出していく運動だと思います。そして、念仏の教えを通して、本当の意味での「人」を生み出していく、そのような運動だと思います。 この親鸞教室を大切な真宗の学びの「場」として、ご一緒に勉強させていただけることを本当に嬉しく思っております。 (完、文責 浄影寺) |
|
【注】 |
|
|
※1 同朋会運動 |
正式には「真宗同朋会運動」。1962年、「家の宗教から個の自覚へ」のスローガンのもと進められた真宗大谷派の信仰運動。「門徒一人もなし」という懺悔と、「家」という因習の中に真宗が埋没しているとの反省から、一人一人が自覚的に信仰しようと運動を展開した。 |
|
※2 鈴木章子
|
1941年、北海道に生まれる。1964年、真宗大谷派西念寺坊守となる。1977年、斜里大谷幼稚園園長となる。1988年12月31日、逝去。 『癌告知のあとで−私の如是我聞−』(1989年、探求社刊) |