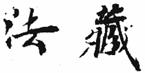|
|
「迷信」を考える -それでも、清め塩を使いますか? |
|
私たちが生活していく中で、気がかりなことが続くと不安な気持ちに陥ってしまうことがあります。例えば、亡くなった人に対して、友引などの日の良し悪し、方角の良し悪しといった、目に見えないものについては確かめようがありませんので、特に、不安が募っていくことになります。そこで今号では、不安の原因になっている「吉凶禍福」、つまり迷信について考えてみようと思います。 【死者に関わる迷信】 生活の不安というものは程度の差こそあれ、誰でも抱えています。不安を解消するには、その原因を取り除くことが大切になります。そこで、私一人で解決できない問題については、大方、その道の経験者の知恵をお借りする。例えば、進路については先輩や先生、仕事については同僚や上司などが良き相談相手として、解決の糸口が見つかることがあります。 ところが、死者に関わるような目に見えない問題については、意味はさておいて、昔からの「言い伝え」(慣習)に従っていれば不安が解消するように考えますが、その「言い伝え」が迷信である限り、気が紛れることはあっても、不安そのものが解消されたとは決して言えないでしょう。つまり、不安の原因を外に向けていくのではなく、不安の原因は私たちの心にあるとして視点を変え、私たちが死者をどのように考えているのかに目を向けていくことが大切だと思います。これを仏教では内観(=自らの内に目を向けていくこと)と言います。 【死穢・産穢・血穢は神道の考え方】 死者に関する迷信のいくつかを挙げてみましょう。中でも葬儀に関わる迷信は実に多いのです。葬儀の際、ご自宅の玄関に置かれる「清め塩」。これで一体何を清めるというのでしょうか。神道に、死穢(死の穢れ)・産穢(お産の穢れ)・血穢(血の穢れ)という三つが不浄であるという考え方があります。鳥居を結界として、その内側が神の領域とされるので、この三穢は神の神聖な領域を穢すものとして塩が登場します。大相撲の力士が土俵で行なう所作は古い神道儀礼に乗っています。しかし、この三穢は、人間が生まれ死ぬ、そして出産する女性の存在を穢れとして見なしていくという考え方に基づいていますが、仏教の見方からすれば、「間違い」と言わなくてはなりません。「生老病死」について仏教では、人間の現実苦悩として捉えた上で、人間の命の事実として、私たちに命の意味と尊さを教えて下さる大切な「ご縁」と見ていきます。つまり、大切な人の死をとおして、そこから学ばさせていただくものがありますし、死するからこそ、掛け替えがない命・生きることの意味を訪ねていくのです。 【清め塩は必要ではないと見るのが仏教】 人が亡くなった場面において「清め塩」を使うということは、「死は穢れであり、また亡くなったらどんなに大切な方であっても穢れた存在である」としてしまうことになります。その方が亡くなられるまで大切な人として関わりながら、亡くなった途端に穢れた存在にしてしまうことは、とても悲しいことです。 仏教では、亡くなった方を亡霊ではなく、阿弥陀仏やお釈迦様のように、そのご生涯を通じて私たちに人生の大切な意味を教えて下さった仏様(諸仏)として受け止めております。そこには「清め塩」を使う必要はないのです。 【友引は、何の根拠もない迷信】 また死者に関わる迷信に「友引」という考え方がありますが、これは全く仏教とは関係ないものです。これは14世紀に、中国から入ってきた「六曜」という暦の考え方で、友引はその一つです。六曜は先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6種類から出来ていますが、何の根拠もない迷信です。先勝は「先んずれば即ち勝つ」(万事に急ぐことが良い)、友引はもともと「共引」と書き勝負事で引き分けという意味ですが、いつしか陰陽道と重なって「凶事に友を引く」という意味になりました。先負は「先んずれば負ける」(急用は避けるべき)、仏滅はもともと「物滅」と書きますが「仏も滅するような大凶日」と伝えられ、大安は「大いに安し」(何事も吉)、赤口は陰陽道の「赤舌日」から牛の刻(午前11時から午後1時)のみ吉でそれ以外は凶とされています。 ようするに、何の根拠もない占いから出てきたもので、勝負事に利用されてきたのです。この日の良し悪しの考え方について親鸞聖人は、 かなしきかなや道俗の 良時吉日えらばしめ 天神地祇をあがめつつ 卜占祭祀つとめとす (『正像末和讃』) と言われ、道俗(僧侶と在家)共に、日の良し悪し・祟る天地の神々・占いや祈禱など何の根拠もないものに振り回され、人間の生き方や考え方を縛っていく在り方について、批判をしています。そういう中で、人間とはどのようにあるべきなのか、どのように生きるべきなのかを求めてきた親鸞聖人にとって、人間を人間でないものにしていく在り方から解放されていく道を、念仏をとおして教えて下さった。つまり、仏様の智慧をとおして物事を考え、人生を見つめ直していくことが大切だと教えて下さいました。 【先祖は祟る亡霊?それとも仏様?】 例えば、占い師や霊媒師に「あなたに不幸が起こっているのは、10代前の先祖が祟っているからです」と言われたとします。皆さんはどのように考えますでしょうか。 仏教の智慧をもって見ていきますと、「10代前の先祖が祟っている」というけれども、私ども子孫に祟りを及ぼすようなものは、果たして、本当に私たちの先祖なのでしょうか。結論から言えば、私どもが先祖供養を怠ったとしても、私たちの先祖は祟ることはありません。私たちもいつかは死んで先祖の一員になります。仮に、私たちの子孫、例えば子供や孫が私の供養を怠ったからといって、その子どもや孫に対して私たちは化けて出たり、祟るというようなことをするでしょうか。むしろ、温かい目で見守っていくものこそ先祖なのです。 そしてそもそも、不幸が起こっているというけれども、世の道理は、原因があって、条件が整って、初めて結果になります。例えば、交通事故を見ますと、相手の自動車があり、横断歩道を渡ろうとする自分がいて、天候は激しい雨降りで、路面が濡れてスリップしやすい。車の運転手はフロントガラスに叩きつける雨で視界が悪いし、歩行者は傘を深くさして、前をよく見ることが出来ない。こうした条件(縁)が重なって事故が起こっていきます。このような見方をするのが仏教です。不幸とされるものも原因・条件があって結果として出てくるのです。しかし一方では、結果を糧として、次の考え方や対策、場合によっては人生の大きな転換となり、その人の人生に厚みをもたらすこともあるでしょう。 そのように、私たちが物を考えたり見たりする時に、どのような価値観・人生観をもって見ているのかによって、受け止めや意味が変わっていくのです。 亡くなった方を「祟りを及ぼす亡霊」として見ていくのか、または阿弥陀仏やお釈迦さまのように、苦しみや悲しみを重ねながら一生涯をとおして、私たちに人生の意味を教えて下さった「諸仏」(仏様)として受け止めていくのか、そこには大きな違いがあります。 親鸞聖人が教えて下さるお念仏の教えは、仏様の智慧をとおして社会を見、自分を見て、何が真実で何が偽物なのか、そのことを見抜いていく眼を育てて下さるのです。 (了・文責は当院) |