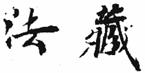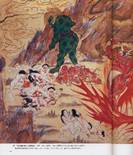|
|
|
�^�@��J�h ��e�� |
|
�g�b�v�@�����Љ��@�^�@�̋����@�����̊����@�{���Č��@���L�@�f���� �Q�q�̂��ē��i�i��[���E�i��o�j�@�֘A�����N�@��e���Č��ւ̎Q��ɂ��� |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b
|
|
�u������̖{����v �@�@�@��e���E�O�� |
|
���@�̏O�k�E�O�����A�W���V���A���k�ʉ@��Â̋œV�u���Ŗ@�b���������܂����B�����̏��^���f�ڂ������܂��B ���҂ƒʂ��鐢�E �n���E��S�E�{���̂Ȃ����E�����߂� �y���{��E�{�L�̊�z �u������̖{�i���Ɓj����v�Ƃ����u��́A�w�喳�ʎ��o�x�ɂ��錾�t�ł��B�܂�A����ɕ������ɂȂ�O�g�E�@���Ƃ��������ł��������ɁA�����݉����ɏo�����A��ϊ������A���ʂ��̂ĂĈ�l�̏C�s�m�ƂȂ����B�����āA�u�Q����v�������ĕ���櫒Q���A���̌�A�l�\����i�{��j�����Ă�ꂽ�A�ƁB���̖{��̒��O�ɐ���ꂽ����ɂ̎v���E�u�����̌��t�ł��B �Ȃ��A�{������ĂāA���ɂȂ��Ƃ���̂��A����́A�u�O���̐����v�Ƃ����ꂵ�݂̖{�����߂ł���ƁB�����ɂ́A���̊肢�ƌ����Ă��A�P�Ȃ闝�z�Ƃ��Č���Ă���̂ł͂Ȃ��B�ڂ̑O�ɁA��Y����l�̌����̎p������B���ꂩ�猚�����悤�Ƃ����y�Ƃ������E�́A������̐��E�ł͂Ȃ��̂��B���̐��E���ǂ�قǁA�f���炵�����E�ł����Ă��A�����ɐ����Ă���l�Ԃ̋�Y���������A��y�Ƃ������E�͐��藧���Ȃ��B�����āA�����ɋN�����Ă����Y�ɑ��āA���̏�Ԃ����P����Ƃ��������A��Y�̌����E�{���A�Ƃ����B�����Ă݂�A�Ώ��Ö@�ł͂Ȃ��āA���{�����ł��B���ꂪ�A��y���������悤�Ƃ��鈢��ɕ��̎u�Ȃ̂ł��傤�B ���āA����ɂ̖{�肪�l�\����ƌ�����̂́A�N�m�Z�i�������������j�Ƃ��������|�ꂽ�w�喳�ʎ��o�x�ɐ�����Ă��邩��ł��B�������A�u������̖{���v�Ƃ����̂ł�����A�����ʂ�A��Y�̖{�͈�B�]���āA�{����܂���̍��{�I�Ȋ肢����n�܂����̂ł��傤�B��̍��{�̊肢���l�\����̗p�����������Ƃ������Ƃł��B����ŁA�{����u���{��v�Ƃ������̂ł��B�����Ă�����A�u�{�L�̊�v�Ƃ����Ӗ�������܂��B���Ȃ킿�A�{�L�Ƃ����A�l�Ԃ̑��݂̐[���Ƃ���ɖ{���I�ɂ���肢�A���̐g�𑶍݂����߂Ă���肢���ĂыN�����Ƃ����Ӗ�������B�����������{��E�{�L�̊���ĂыN�����āA�������ɏ�y�Ƃ������y��^���悤�Ƃ��Ă���B�����ɁA�������������Ă���A���̌����̎Љ�������ӎ�����Ă���̂ł��B �y�u���@�����v�_�c����z �����A�u���@�����v�_�c������ɂȂ��Ă��܂����B���́A�����ł͂Ȃ�������ڎw���Ă���Ƃ����v���Ȃ��̂ł��B���@�́A���Ƃ��ƍ��ƌ��͂�A�����̎��R��ۏ��邽�߂ɐ��肳�ꂽ���́B������u������`�v�ƌ����܂��B�܂�A���@�����`���͍����ɂ���̂ł͂Ȃ��A���͂��߁A��b�E�c���E�������ȂǂɁA���@����Ɨi��̋`�����ۂ����Ă���B�������A���@�����炵�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��א��҂��猛�@�����̐����オ��A�V�c�����ƌ���Ƃ��A������ς��āA���q�������h�R�ɂ��A�R�@��c��ݒu�A�܂��A�l�����u���v��D�悵�č����̎��R�𐧌����铙�A���@���\����ɏƂ炷�ƁA���@�ᔽ�̐����o�Ă����������Ȃ��B������A���@�������āA�ǂ̂悤�ȍ��ɂ��Ă������Ƃ��Ă���̂��B�����}���o���ꂽ���@�����̑��Ă�ǂނƁA����Љ�̃C���[�W�������Ԃ悤�ł��B���@��ǂނƁA���̍��������ɂ��A�ǂ̂悤�ȍ���ڎw���Ă���̂��A���̂��Ƃ������Ă��܂��B �y����u���O����̊�v�z �ł́A��y�����̊�ɂȂ�{��ɂ��Ă͂ǂ����B���āA�]��ʐ[�搶�́A�{����u��y�̌��@�v���ƌ����܂����B�܂������A�{��Ƃ������@�ɂ���āA��y�̐��i���\����Ă���̂ł��傤�B�����āA���ۂ̍��ł́u�����v�ł��傤���A����C�搶�́u��y�̏Z�l�v�Ƌ��܂������A��y�ɐ�����Z�l�A���Ȃ킿�A�O�������l�̎p���A���̖{�肩��f���܂��B���ɁA�l�\����̑���u���O����̊�v���A��y�̏Z�l���A�悭�����Ă���Ǝv���܂��B �s���O����̊�t �u�݉䓾���A���L�n���� �S�{���ҁA�s�搳�o�v �i���Ƃ���A����ɁA���ɒn���E��S�E�{������A���o����炶�j ���Ƃ��ƁA���̒n���E��S�E�{���́A�Z���Ƃ����A�l�Ԃ̖����݂̍����Z�ʂ�Ɏ����ꂽ�����̎O���n���E��S�E�{���ł��B�{��̑���ł́B�n���E��S�E�{���̂Ȃ����E����肽���A�Ƃ������Ƃł��B�ł́A���̒n���E��S�E�{���̂Ȃ����E�ɐ旧���āA���������A�u�n���E��S�E�{���v�Ƃ������t�Ō������Ă��Ă��鎄�����̐��E�A�܂�A���̎Љ�ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂����Ă����K�v������܂��B�����Ă݂�A�������̌������o�Ƃ��Č���Ă���̂��A�u���O����̊�v�̒��g������ł��B
�܂��A�u���O����v�́u���v�Ƃ������́A������A�u���v�Ƃ������u�����v�Ƃ����Ӗ��B�l�ԂƂ��Đ����Ă�����Ō������ׂ������A�l�Ԃ̑������������D���Ă����悤�Ȃ��̂���������A�Ƃ������Ƃł��B���������A�l�ԂƂ������t�́u�ԁv�Ƃ������́u�ԕ��v�A�l�Ɛl�Ƃ̊W�����Ӗ����܂��B�l�Ɛl�Ƃ̊ԕ�������̂��l�ԂȂ̂ł��B�������A���́u�ԁv�������A��ɁA�l�Ɛl�Ƃ��w�����������Ă���B���̂悤�Ȍ������ׂ��݂�����u���v�Ƃ������Ƃ̈Ӗ��ł��B �{�����搶�́A�u�l�Ԃ́s�ԁt�����ȂƂ��Đ�������̂��v�ƌ����܂����B�l�Ɛl�Ƃ́u�ցv�̒��ɁA�����Ǝ����̋��ꏊ�������āA���߂āA�����̑��݂��ӎ������B�܂�A���҂Ƃ̊W�ɂ����Ď��Ȃ�����̂ł��ˁB �y�ق�����z ���āA�{��搶���炱�̂悤�Ȃ��b���܂����B ���邲����̕����u�����ƁA�ق�������~�����Ȃ�B�������A�����ƁA�ق���������Ȃ��Ȃ�v�Ƌ�������ƌ����̂ł��B�u�ق�����v�Ƃ����̂́A�����Ȃ��ł���i�j�B�u��E�A�E���v�ł��B�܂�A�u�E�A���E���k�v�����Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃł��ˁB �Ⴆ�A�ΘV���āA�d���̑�������O��A�Ⴂ����ɐ��т�C����悤�ɂȂ�ƁA�C�y�Ȗʂ������ėǂ��킯�ł��B�Ƃ��낪�A�Ⴂ�l���������������������Ă���ƁB�������A���̕��A�����Ȃ��̂Őu�˂�ƁA�u�S�z���Ȃ��Ă������v�Ƃ����Ԏ����A���Ă���B�����Ēi�X�A�ƒ�̂��Ƃ������悤�ɂȂ����ƁB�����Ȃ�ƁA���S�n�������Ȃ邵�A�a�O�����o�Ă��܂��B�Ђ���Ƃ���ƁA�����b�シ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���k�܂ł����Ȃ��Ă��A���߂āA�E�A������������A�Ƒ��̂��߂ɐ����Ă���Ƃ����������o�Ă���̂ł��傤�B �{��搶�́A�u�l�Ԃ͕�A����~�����鑶�݁B��A�����Ȃ��Ȃ�Ώ��݂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂��v�Ƌ��Ă��܂����A�܂��ɁA��A���Ƃ����u�ԁv���鑶�݂��l�ԂȂ̂ł��B �y����P�\���Ȃ��z �����āA�u��v�Ƃ������́u����{���v�Ő��藧���A�u���������v�Ƃ����Ӗ�������܂��B�]���āA�P�\���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B �܂�A�u����v�Ƃ́A�u�ԁv�����ȂƂ��鑶�݂ł���l�Ԃ��A�l�Ԃ̗~�]�������o���ɂȂ�悤�ȏŁA�l�ɑ���s�M�������܂��B�l�Ԑ����Y�^�Y�^�ɐ��A�l�Ԃ��l�Ԃł��邱�Ƃ������Ă����悤�ȁA���������ꍏ�̗P�\���Ȃ��̒��Ő����Ă���B���݂̍�����u����v�ł��B�@�@ ���́u�O����v�ɂ��ĕ���C�搶�́A�u���l�̍r��v�Ƌ��܂����B�吨�̐l�ԂɈ͂܂�Đ����Ă��Ȃ���A�����ɒN��l�Ƃ��ĐM������l�����Ȃ���ԁB�l��S���M���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����Ԃ��u���l�̍r��v�ƌ����܂����B��ԈႦ�A���ł��M���������Ă����悤�ȁA���������A�Ƃ��ւ��̒��ŁA�������͐����Ă��܂��B �y�ߋƂɍS���n���z �ł́A�n���E��S�E�{���́A���������Ă���̂��B �n���́A�u�����naraka�i�ޗ��j�B�ߋƂɂ���Đ�����ɋ�̐��E�v�Ƃ����Ӗ��B�܂�A�ߋƁA���̍߂ɑ��鋰�|�E�����Ƃ����A�����������퐶���ŁA�������Ă����̒��ɂ���܂��B �n���ɂ��āA�w���o�v�W�x�ɂ́u���͑��̋ǂȂ�B�ǂ͍S�ǁi�������傭�j�Ƃ����B���݂��v�ƁB�v����ɁA���݂�����t����ꂽ��ԁA��݂̍���ɍS������A�{���݂̍�����ł��Ȃ���Ԃ������܂��B �Ⴆ�A�w�ϖ��ʎ��o�x��w���όo�x�ŃA�W���Z�̖�肪���グ���Ă��܂��B���q��Ƃ������̂��Ƃɐ��܂ꂽ�A�W���Z���A�ߑ��̒�q�ŏ]�Z��̃_�C�o�_�b�^�ɂ����̂�����A�N�[�f�^�[���N�����B���̃r���o�V���������E���A��e�̃C�_�C�P�v�l���E�����Ƃ������A��b���|�߂��A��e�E�Q���v���Ƃǂ܂����B���炭����ƁA�����̍s�����ƁE�߂̏d������A�n���ɑ���̂ł͂Ȃ����Ɣ��ɋ��|���A�ꂵ�ނ̂ł��B�Ƃ����߂́A���Ԃ��������Ȃ��킯�ł�����A�߂ق�ڂ��̂��߂ɑP����ςƂ��Ă��A������������킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���U�A���̍߂ɔ����A�Ղ܂�Ă��������Ȃ��B�����Ɉ��̐�]������B���������A�ƁE�߂ɔ����A���������Ȃ��琶���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����n���ł��B �y�����n�����z�n���z ���M�m�s�́w�����v�W�x�ɂ́A�n����������Ă��܂��B�傫������M�n���Ɣ��劦�n����������A���̑��Ԗڂ��u�����n���v�ł��B �����n���Ƃ����̂́A�n���ɑ���ƁA���̒n���̏Z�l���A����������S�̖_�ŁA���̂Ă��瑫�̐�܂ŁA�荏�݁A����ׂ��Ă����B�����Đ����ȕ��������ƁA�܂������Ԃ�A�Ăѐ荏�܂�A����ׂ���A�܂����������Ɗ����Ԃ�A������J��Ԃ��I��肪�Ȃ��B�����ɁA���������Ă��Ă��ꂵ�݂��I���Ȃ��Ƃ������ƂŁA�l�Ԃɂ͏����Ȃ��߂�����̂��A�Ƃ������Ƃ�������B �܂����܌o�T�ł́A���̓����n�����u�z�n���v�Ƃ������t�ŗ}�����Ă��܂��B�������́A�����̌o����̌����Ă������Ƃ�P���Ƃ��āA�����̕������E���b�e����\���āA�������~�߂Ă��܂����Ƃ������ł��ˁB�܂�A�����������Ƃ��Č����ɁA���������Ɏ����̑z�����d�˂Č��Ă��܂��B���肪�h���̌������b���Ă��A�����̑̌��ɍ��킹�ė������悤�Ƃ���B �������A���������̌��������ƂƁA���̕����̌��������ƂƂ́A���S���قȂ�Ƃ������Ƃ�����̂ł��B�u�v����Ɂv�Ƃ������t�����������ł��傤�B�����������Ƃ��āA����̂܂~�߂邱�Ƃ����X�ł��Ȃ��̂��������ł��B �y�w�C�g�X�s�[�`�z ������N�قǑO����A�u�w�C�g�X�s�[�`�v�Ƃ����A���̊ۂ���ɁA�����̔O���o���ɂ������t�����тȂ���A�ݓ����N�l�E�؍��l���Z�ޒn����f������Ⴂ�l�̎p���o�Ă��܂����B�w�C�g�X�s�[�`�Ƃ́u�����\���v�Ƃ����Ӗ��ŁA�������̐l��⑮���ɑ��āA�\�́A���ʒ����A���ʐ�������s�ׂ̂��ƁB���ۓI�ɂ́u�l�퍷�ʓP�p���v�ɂ���ċ֎~����Ă���s�ׂł����A���{�ł͎����܂�@���͂Ȃ��̂�����ł��B
�ŋ߂̃w�C�g�X�s�[�`�́A�k���N����̓y���Ƃ������ۏ���w�i�ɂ���悤�ł����A�����ɏ悶�āA�i�V���i���Y�������A���N�w�Z�̎q�������ɂ܂Ŕ�Q���y�ԏ́A���āA�֓���k�Ђ̎��ɁA�f�}��������N���Ƃ������N�l�s�E�������v���N�����܂��B �����������ʂ⒆���Ƃ������́A�Ό��E���b�e���ɂ���āA���炪�����Ă��镮��̓f���o���ɗ��p����邱�Ƃ������̂ł��B���ʐ���������҂́A���炭�A���퐶���̒��ŁA�ݓ����N�l�E�؍��l�ɏo����Ƃ��Ȃ��̂ł��傤�B�u�z�v�Ƃ������ꂽ�C���[�W���������A�l�̓i�}�g�̐l�Ƃ͏o����Ƃ��ł��Ȃ��B�����������ʖ��́A���ʂ�����Ă���l���l�Ԑ���D���Ă��������ł͂���܂���B���ʎ҂��A���ʂ��邱�Ƃɂ���āA����̐l�Ԑ����������Ă����A����A�݂��̐l�Ԑ��������Ă������Ȃ̂ł��B �y�ǓƂɂ��ē����Ȃ��z ���ꂩ��A�w�����v�W�x�ɁA�u��A���A���鏊�Ȃ��A�ǓƂɂ��ē����Ȃ��v�ƒn���̂�����ʂ������Ă��܂��B �������Ƒ����̐l�Ɉ͂܂�Đ����Ă������A�C�����Ă݂�A�킪�l���ɂ����āA��т��Ƃ��ɂ��A�߂��݂��������Ȃ���l�������ɐ�����A����A�{���̈Ӗ��ŁA�����ƌĂׂ�l�͈�l�����Ȃ������B�ǓƂł������A�ƁB�����҂����Ȃ��Ƃ������Ƃ̖��́A�l�Ɛl�Ƃ́u�ԁv�������A������Ԃɂ��Ȃ���A���ꂼ�ꂪ�A���ꂼ����Ă���A�ʂ��Ă����Ȃ���������Ă���̂ł��B �y��S�̖�聁�×~���z ��S�́A�~�����������߂Ă��A������������Ă��Ȃ��A�l�Ԃ��×~���̖��ł��B����͕������ł͂Ȃ��B�l�l���牽�����������āA�ŏ������A���̌��t���o�܂��傤�B�������A�����ɁA���O���Ƃ����S�������Ă���ƁA�~���������Ȃ��Ă���悤�ɂȂ�܂��B���N�A����������Ε��䒆���ɂ��A�s������������A�~�����o�Ă��܂��H�i�j�����Ȃ�ƁA���X�̈Ӗ��������ɍs���Ă��܂��āA���̕i���ɂ���ڂ��D���Ă��܂��B �܂��A��S�͐H�̖��ł�����܂��B�����ɂ́A�u�H�ׂĂ��邾���ŁA������ƌ�����̂��v�Ƃ�����肪����܂��B�H�ו������߁A�~�����������߂�A���ꂾ�����A���Ȃ��ɂƂ��Đ����邱�ƂȂ̂��A�Ƃ����؎��Ȗ����N���Ă���̂���S�ł��B �y�{�������ꂼ��z �{���́A�l�Ԃ́A���ꂼ��̗���ł��������Ȃ��Ƃ������ƁB�]��ʐ[�搶�́A�u�P�l����̉Ƃɂ͑������₦���A���l����̉Ƃɂ́A������������v�ƌ����܂����B�P�l�̉ƒ�́A���ꂼ��A�������P�l���Ǝv���Ă��邩��A�݂��ɁA�����̐��������咣�������B������A�ǂ����Ă����܂��₦�Ȃ��̂ł��B���l�̉ƒ�ɂ́A���ꂼ��A�����������Ǝv���Ă���̂ŁA���݂��Ɂu���܂Ȃ������v�Ƃ������t���o�Ă��܂��傤�B�����ɁA�e�q�A�v�w�ł����Ă��A�ƒ�̒��ł��O�ł��A�l�Ƃ��Ă̌�����������Ȃ�A�l�Ɛl�͌𗬂��������Ƃ��ł���̂ł��B����́A�o�T�Ɍ��������p���ɂ��ʂ���̂ł��ˁB �n���E��S�E�{���Ƃ����O����ɋ��ʂ��邱�Ƃ́A�����ꏊ�ɂ��Ă��A���҂ƒʂ������Ȃ��A�l�Ɛl�Ƃ́u�ԁv�������Ă���Ƃ������Ȃ̂ł��B�������A���҂ƒʂ������Ȃ��ǂɂȂ��Ă����̂́A���́A���́u���v�ł������B���̔F������{�肪�n�܂��Ă��܂��B �n���E��S�E�{���̖�肪�A�{��̍ŏ��ɂ���̂́A�P���ɏ��ԂƂ��Ă���̂ł͂Ȃ��B�J��A�{��S�̂ɂ������Ă������Ƃ��Ēu���ꂽ�̂��Ǝv���܂��B�܂�A��y���ǂ�قǑf���炵���Ƃ���ł������Ƃ��Ă��A��y�ɉ�������l���A���҂ƒʂ��Ȃ���Ԃł���Ȃ�A�����͛O�k�ƑS���������ƂɂȂ�A��y�͌����Ȃ��̂ł��傤�B �y�@���̉Ƃɐ��܂��z �u�O���Ƌ��ɉ�������v�Ƃ������t���P����t�ɂ���悤�ɁA�u���Ɂv�Ƃ�����_�ŁA�l�͐l�ɂȂ��Ă����B����́A�l�́A�l�Ƃ́u�ԁv�ɂ����āA�l�Ԃł��邱�Ƃ����Ă������̂Ȃ̂ł��傤�B�w���s�M�x�Ɂu�@���̉Ɓv�Ƃ������t������܂����A�܂������A�O���\�����̂́u�@���̉Ɓv�ɐ��܂�A�u��y�̏Z�l�v�ƂȂ�A���݂��ɁA�l���̓����҂ƂȂ��Đ�����̂��B�����ɁA�䓯���E�䓯�s�̐��E���J����Ă����̂ł���܂��傤���A�{��̑���Ŋ���Ă��邱�Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�i���E���ӂ͓��@�j |