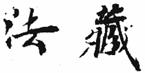法 話
|
|
「愚者になりて」 浄影寺・釋弘道 |
|
東日本大震災から1年7ヵ月余り経った昨年2012年10月16日から22日、仙台教区気仙組(陸前高田市・大船渡市)の寺院7ヵ寺に開催されている定例布教に参加、お話をするご縁を頂戴いたしました。まだまだ復旧・復興からは遠い震災被害の現実の中で、被害に遭われた多くのご門徒と、親鸞聖人の教えに向きあう一週間を過ごさせていただきました。この抄録は、当日の法話に加筆訂正を加えたものです。 本願を中心に据えた生き方へ ―人間知の闇を超える― 【人間の知恵の闇】 「愚者になりて」は、親鸞聖人が書かれたお手紙『末燈鈔』の中にある法然上人の「浄土宗のひとは愚者になりて往生す」から引いた言葉です。親鸞聖人は法然上人が開いた仏教・浄土宗にご生涯を捧げられます。その中で、浄土宗、そして浄土真宗とは何かと言えば、法然上人の「愚者になりて往生す」る、というこの一言で言い尽きるのだと、抑えられていくのです。 考えてみれば、私たちは、愚者ではなくて、おおよそ、知者・賢さというところで生きているのでしょう。賢さというのは、より便利で快適な生活をするためにもつ、言わば、人間の知恵です。快適な生活をしていくためには、複雑で面倒で、煩わしいことは出来るだけ排除して、痒いところに手が届くようなことを求めていく。すると、それに応えていく便利なものが次々に商品化され、利用されていくようになります。こうした「向上進歩」という生き方の中で進歩発展が遂げられてきた、言わば、賢さ・人間の知恵を象徴しているのが、科学・技術です。その意味では、科学・技術というものは、要は人間を幸せにするためにあると言っても過言ではない。そこに、私たちは信じ、夢も描いてきたのでしょう。 ところが、2011年3月11日に発生した東日本大震災によって、高度な科学・技術を標榜する原子力発電所が爆発を起こした。人間が作った科学・技術の暴走を食い止めることができなかった。その結果、人間の生命を脅かし、国土を汚染し、居住することが許されない場所を作ってしまったのです。一度の失敗が取り返しのつかない事態を招く、それが原発災害です。 原発の問題は、核兵器に使用されている危険な原子力の技術を、「平和利用」という名前を冠した形で、ささやかな家庭に持ち込んでしまったということです。ここに「賢さ」と言われるものの落とし穴、人間のおごりがあり、これが「安全神話」を作ってしまった。その意味では、原発災害は、人間の知恵の闇が起こした、明らかな人災でしょう。そして、それは戦後の高度経済成長の流れの中で、物質的な豊かさこそが、私たちが描く便利で快適な生活であると思ってきた。そこに、原発を安易に受け入れていく環境があったのでしょう。そして、「豊かだ」と言われる日本社会の中で、毎年3万3千人が自死する状況がある。このことが象徴しているように、科学・技術で作り上げた文明社会が行き詰まりを見せていた。そこへ震災が起こりました。 社会の行き詰まりは、経済至上主義という状況の中で、命に値段がつけられ、人間が切り捨てられていく状況が起こっていく、つまり、役に立つ・役に立たないという価値観があらゆるものに持ち込まれ、言わば、人間の命が、経済活動の素材として扱われていく。つまり、人材・人的資源として価値があるかないかを人間に見ていくという、人間の商品化が起こってまいります。そして、商品価値にならないとなれば、冷酷な形で、生きることの意味が否定され、排除され切り捨てられる人間を生み出していくことになるのです。 【生きるだけを生きる】 岐阜県郡上八幡に末松保という青年がいました。肝硬変を患い、28歳の若さで亡くなったのですが、亡くなる2ヵ月ほど前に書かれた日記が遺されています。 「限られた人生の為すべきことを教えて下さい/短い人生の歩き方を教えて下さい/半人前の私に、一体、何ができるのでしょうか/ただ生きるだけを生きるだけでよいのでしょうか」 (末松保『保絶唱』) 末松さんは、病床の中で残り少ない自らの命と向き合い、生きる意味を訪ねられます。「半人前の私」と言われるように、他人の手を借りなければ何一つ出来ない自らの有りようを見つめながら、「生きるだけを生きる」しかない自分自身に、それでも生きる意味があるのかと問うているのです。仮に、何かをすることが生きている意味であると言った時、「ただ生きるだけを生きる」しかない存在にとって、その存在意味は失われてしまうことになるのです。 私たちの社会は、経済性・効率化を優先させて動いています。そういう社会の中で、もし、「ただ生きるだけを生きる」者にとって、存在意味があるとするならば、それは何処にあるのか。実は、これは人間存在の本質的な課題なのですね。 ところで、日常生活の中で、ふと、存在そのものが非常に尊いと感じる瞬間があります。それは赤ちゃんの存在です。そこには、効率的だとか経済だとか、役に立つとか役に立たないとかという世界とは、ほぼ関係なく生きている。赤ちゃんは、能力という点から見れば、全く無力と言わずにおれない存在である。けれども、その場の空気を和ませ、周りの大人から笑顔と優しい心を引き出している。何かをして意味があるというよりも、その存在そのものが、みんな一緒に生きているという世界を開いていく働きを持っているのです。 ご承知のように、釈尊が誕生された時、七歩あるいて「天上天下唯我独尊」と仰ったという伝説がございます。「独尊」とは「独りとして尊い」という意味です。誰かと比べて命の価値を見るのではなくて、この地上にたった独りとして誕生した、その掛け替えのない絶対的な命が、尊い世界を開いていくということでしょう。一人の人間の誕生、その存在自体がすでに働きを持ち、暖かい世界を開いていく。その世界を、親鸞聖人は「浄土」という言葉で教えて下さってのではないかと思います。 【無言の問い】 20年前の話ですが、岐阜県に、平野恵子という方がいました。平野さんは由紀乃というお嬢さんを授かるのですが、重度の心身障害児と診断されてショックを受けられた。手足は動かすことができず、声を発することもできない。食事するにも、誰かがお世話をしなければ生きることもできないというお子さんでした。平野さんは、この子はどれだけ長生きしても救われないのかと、度々、自殺を考えられたそうです。 ある時、平野さんのご実家で法要があって、その時、廣瀬杲という先生が法話にいらしたのだそうです。その時のエピソードが、平野さんが書かれた本『子どもたちよ、ありがとう』で紹介されています。廣瀬先生は次のようなことをお話されました。 「問いのないところに道は開けない。人生には問いがあること。その問題をいただいたところに道が開かれる。問題のない人生は、それは寂しい。むしろ問題があればこそ道が開かれる。問題のないところに救いはない」と。そのお話を聞いた平野さんは憤慨され、法話の後、由紀乃ちゃんを抱えて先生の控え室へ行きました。そして平野さんは「今日はとても残酷なお話をなさいましたね。問いのない人が救われないというのであれば、由紀乃は生涯、口で問えません。なんで、こんな身体に生まれてきたの、と問うこともできない。そしたら、この子は救われないし、生きる道が閉ざされてしまうということですか」と仰った。その訴えを静かに聞いた廣瀬先生は次のようにお話しされました。 「由紀乃ちゃんは問いがないとおっしゃるけれども、どうして、そういうことが言えましょうか。由紀乃ちゃんは身体全体で問うておられませんか。問うということは、ただ言葉で問うというよりも、むしろ、無言の問いというところに本当の問いがある。無言の問い、言葉にならない問いというものが、いかに深いものか、由紀乃ちゃん自身が身体で、私たちに呼びかけておられる」と。そのお話を伺った平野さんは、その後、「私はこの子を心配しているようで、子どもを見る眼が曇っていた」と述懐され、ガンの闘病生活を経て40歳で亡くなるまで、お念仏の教えを聞き続けられたのです。 由紀乃ちゃんの存在が「無言の問い」を発し、その問いによって、いのちの世界が開かれていく。言い換えれば、「生きるだけを生きる」という、その命そのものが、「無言の問い」となって、そこに、いのちの世界が開かれていく、ここに眼を開かせて下さるのがお念仏の教えなのでしょう。 その意味では、経済性や効率だけで人間の価値を見ていく社会は、裏を返せば、経済活動によって人間が排除されていく状況を作り、そこには虚しさと絶望しか残りません。「生きるだけを生きる」という現実に気づかせていただいた時、生活の中で起こる個々の問いが問題にならなくなるほど、もっと本質的な、自らの存在そのものを問わずにはおれない問題に、向き合わざるを得なくなるのです。 【不安は私の命】 私たちは生活の中で問題が起こるたびに不安が募りますが、個々の問題を解決したとしても、起こる不安そのものはなくなりません。また不安から逃げようとしても、逃げきれるものではありません。なぜかと言えば、私たちは不安の種を持っているからです。だから、様々な問題を抱え、不安の種を持っている、この自分と向き合っていかない限り、本当の問題は見えてこないのです。そうした、微かな不安の深いところに、実は、人生そのものを問うものがあるのです。つまり、不安は、私自身の在り方を問い返すものなのでしょう。物事が上手く運んで、一見、より良い生活を送っているように見えても、「あなたの人生は、これでいいのか」という問い返しが、不安という形で、常に起こっているのですね。 宮城𩣆先生から、かつて、お聞きしたお話しです。金沢に山崎ヨンという熱心な真宗門徒のお婆さんがいたそうです。山崎さんは障害を持つ子どもを抱えながら一人で行商をして、ご苦労を重ねて生きてこられたのです。そこへ、ある新興宗教の方が来られて、「婆ちゃん、不安ないか?」という。「不安はありますよ」というと、その新興宗教の方が「不安を無料でとる会があるから、不安を取ってもらったどうや」と言われたそうです。すると、山崎さんは「ご苦労さんやねえ。不安の世の中でねえ。そやけど、この不安、あんたらにあげてしもうたら、何を力に生きていったらいいがやろね。不安は私の命やもん」と言われたというのです。 凄いでしょう。何か、ここに真宗門徒の生き方があります。不安を不安として引き受ける力と言いますか、不安を力にしていくような教えを親鸞聖人から賜ったということですね。また、不安がお念仏の教えを聞かせていただく大事なご縁となったということですね。 一般的には、不安がない方が良いのでしょう。けれども、何か、自分勝手な空想を描きながら、時として、現実とは全く乖離し、思い違いをして生きていきそうな私を、命の深いところから呼び返し、願って下さるものがある、それが「不安」という形で表れているのです。そのことを、本当の意味で、気づかせて下さるのがお念仏の教えなのではないでしょうか。 【愚者になりて】 このように考えてまいりますと、「愚者になりて」という言葉で教えて下さることは、人間の知恵を中心にして生きてきた生き方から、仏様の智慧・本願を中心に据えて生きていく生き方への転換を求めているのでしょう。もう少し言えば、「自分の経験を頼りとし、自信心を持って生きてきたけれども、そこに落とし穴はないのか。これは本当に、あなたが人生を掛けて求めていることなのか」と、問い返して下さる声に気づくということでしょう。 安田理深先生の言葉に「凡愚というのは、現実に頭が下がったものだ」とありますが、命の歴史が一人の人間を誕生せしめた事実、それは紛れもなく、この私の存在で起こったのであった。その事実に頭が下がっていく、そして、本当に命そのものが願ってくださっている声に気づかせていただく、この気づきが「愚者になる」ということの意味だと思います。ですから、私たちは、お内仏(お仏壇)に向かってお参りしていくことは、頭が下がるような命の事実に触れるということ、そして、その命の事実のもとに願ってくださっている仏様のご本願に気づかせていただく。つまり、「生きるだけを生きるしかない」この命に何が願われてきたのか、そして、何を願いとしてこの私という命が誕生したのか、そのことを、ただただ、お念仏の教えを通して、謙虚に聞かせていただく。ここに「愚者になりて往生す」ということが教えられているのではないかと思います。(終) (文責は浄影寺) |