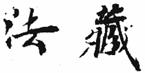|
|
|
�^�@��J�h ��e�� |
|
�g�b�v�@�����Љ��@�^�@�̋����@�����̊����@�{���Č��@���L�@�f���� �Q�q�̂��ē��i�i��[���E�i��o�j�@�֘A�����N�@��e���Č��ւ̎Q��ɂ��� |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b
|
|
��n�ɐ�����〜��k�Ђ���〜 ��e���O�k �M�y�O���@ �����@2011�N10��16��〜22�� |
|
��N3��11���ɔ������������{��k�Ђɂ���Ôg�̒܍����c���䋳��C��g�i���O���c�s�E��D�n�s�j�B�C��g�̊e���@�ł́A�u���̂悤�ȑ傫�ȍЊQ�̒������炱���A�e�a���l�̘b�����Ƃ�厖�ɂ������v�ƁA�k�Ђ���2������ɂ͖����̒��z�����ĊJ���ꂽ�B���v�����A��N10��16������22���ɂ�����7�����ɏo�����A�k�Д�Q�̌����������̒��ŁA�e�a���l�̋����ƌ�����������T�ԂƂȂ����B �l�Ԃ͑�n�Ƌ��ɂ��鑶�� �N���̂��߂ɐ����邱�Ƃ���тƂȂ�`��y�` �������邱�ƑS�̂����ꂽ-�����{��k��- �`���A���̂��т̑�k�Ђɂ���ċ]���ƂȂ�ꂽ���X�ɒ��S��肨����݂�\���グ�܂��Ƌ��ɁA��Q�ɑ���ꂽ���X�ɂ��������\���グ�܂��B ����i2011�N�j3��11���̌ߌ�2��46���A���k�����m����k���Ƃ���}�O�j�`���[�h9�̑�n�k���N��A����ɂ���ċ���ȒÔg���������ē��k�̊C�ݒn������ݍ��݁A���ҁE�s���s���҂����킹�Ė�2���l�̕����]���ƂȂ�܂����B�����āA�����d�͕�����ꌴ���������������Ƃɂ����˔\�������g�債�A���܂��A�������Ă��Ȃ��ł��B���̂悤�ȁA���\�L�̎��R�ЊQ�E�l�Ђ��āA���炭�A�����̐l�X�̈ӎ��̒��ɁA�����I�����ł͂Ȃ����Ȃ���ʉe����^���A����܂ł̐������≿�l�ςɑ��đ傫���ύX�𔗂�悤�Ȍo�������܂����B �������āA�k�Ђ��玞�Ԃ��o���Ă����܂��ƁA�h�����Ƃł��傤����ǂ��A��k�Ђ��̂��̂ƌ��������A�~�ߒ����Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���߂āA���̑�k�Ђ́A��́A�������̉���D���Ă��܂����̂��B�����āA�����A�k�Ђ��C�Â����Ă��ꂽ���Ƃ�����Ƃ���Ȃ�A����͉��Ȃ̂��B�k�Ђɂ���āA���Ƃ����l�Ԃ�����܂Ő����Ă������ƁA���̂��ƑS�̂�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă��܂��B �k�Ќ�A�Ôg��Q����������ɎQ��܂��ƁA�ڂɂ������i�́A���O���c�s���D�n�s�Ɠ����悤�ɁA�Ƃ�ԂȂǓ���̐����������ς��l�܂����������I�Ɖ����āA�����炱����ɎR�ς݂ƂȂ��Ă��܂����B���̂悤�ȔߎS�ȏ�O�ɑ����̕����u���t���������v�Ƌ�����Ă��܂����A�������t����������l�ł����B����́A����܂ŋȂ���Ȃ�ɂ��e�a���l�̋����ɐG��A�����Ȃǂʼn��������̌��t���Ă����̂ł����A���̎S���O�ɂ��āA���̌��t�ɂǂ�قǂ̗͂��������̂��Ɩ�킸�ɂ���܂���ł����B���Ȃ��Ƃ��A�������銙�q����̒��ɂ����Đ������e�a���l�̌��t�́A���ɖ������l������ސl�X�ɗE�C��^���A������͂�^���Ă����͂��ł���܂��B�������A���̐e�a���l�̌��t���u���v�Ƃ����t�B���^�[��ʂ��Ĕ�����ꂽ���A�S���Ɨǂ��قǁA������͂�^���Ȃ����̂ƂȂ��Ă��܂��Ă����̂ł͂Ȃ����ƁA�k�В���A���⎩�����邱�Ƃ������A���l�̌��t���邱�Ƃ��T���Ă����̂ł��B ���l��-���t�ɐ��������- �������A���퐶�����ڂ݂�A�l�ԂƂ������̂͌��t�ɂ���ċꂵ�݁A���t�ɂ���ĉx�сA���t�ɂ���Đ�����͂�^������A�܂�A���t�ɂ���Đ����Ă���̂��l�Ԃł���Ƃ������Ƃ����X�Ȃ���Ɋ�����悤�ɂȂ�܂����B����͎��Ƃ��āA�{���̈Ӗ��Ō��̒ʂ����A������̌��t�����̐l�̐l����傫���ς��Ă����A���́A�l����傫���ύX���Ă����悤�Ȍ��t��l�Ԃ͖{���I�ɋ��߂Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B �Ƃ���Ȃ�A�k�ЂŌ��t�������قǂ̏o�����ɑ����A�����Ă��邱�Ƃ����ꂩ�����Ă��邩�炱���A���̌����������̐^�������ŁA�e�a���l�̌��t�����߁A���t�ƌ��������A���������Ă����A�����������������A���ǂ��^�@��k�ɋ��߂��Ă���̂��ƋC�������Ă��������܂����B �����y�Ƃ͑�n�� ���āA���̂��т̐k�Ђɂ���Ôg�ɂ���āA�����̕�����ȉƑ��������A�܂��A�������̂ɂ����˔\�����ɂ���āA�����̊�Ղ��D���Ă��܂��܂����B����́A�Ôg�ƕ��˔\�Ƃ�����Q�̍�������Ƃ��܂��Ă��A�k�Ђ��̂��̂��������Ƃ��ꌾ�Ő\���グ��Ȃ�A�u���y�v���������Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B���y�Ƃ́A�P�ɏꏊ��\���̂ł͂���܂���B����́A�ߋ����猻�݁A���݂��疢���ֈ����p���ł��������҂̉c�݂ł���A�����ėl�X�Ȋւ��̒��ŁA����Ȃ��l�Ԃ��Y�݁E���ł������̂ł��B�{�����搶�́u���y�ɂ͑�n��������v�Ƌ��܂����B���Ȃ킿��n�̓����A���y�̒��ɂ��̂��ݏo������������B����䂦�ɁA���y�ɂ́u���̂��v�̊���������̂��Ƌ����ĉ������܂����B �܂�A���y�̖{���͑�n�ł��ˁB�l�Ԃ͑�n���琶�܂�A��n�ɗ����Đ����A�����s����Α�n�ɋA���Ă����B�l�Ԃ̑��݂��̂��̂��A��ɑ�n�Ƌ��ɂ���A���̂悤�ȁu���̂��v�����ꂩ�琬�藧�����߂Ă��铭������n�ɂ͂���̂ł��B�����āA���ǂ��̐����A���Ȃ킿�A�l�I�ɑ̌������ꂵ�݂�߂��݂��N���ɓ`����ꂽ���A���̑̌��͒P�Ȃ�l�ɗ��܂炸�A�l�Ԃ̋ꂵ�݁E�l�Ԃ̑̌��Ƃ��đ�n�ɋL������Ă����A�����ɐ��������j������B���̂悤�ȗ��j�I�ȓ�������n�Ƃ������̂ɂ���Ǝv���̂ł��B ���ꂾ���ł͂������܂���B�e�a���l�̒��q�w���s�M�x�ɁA���l�̂��S�E�ߊ���������ӏ��Ɂu�ߊ�́c�Ȃ��A��n�̂��Ƃ��A�O���\����ؔ@���o�����邪�䂦�Ɂv�Ƃ���܂��B�O���Ƃ͉ߋ��E���݁E�����̂��ƁB�\���Ƃ͂�������p���Ӗ����܂��B�܂�A�ߊ�Ƃ͑�n�̂悤�Ȃ��̂��ƁB�Ȃ����������邩�Ƃ����A���ԓI�ɂ���ԓI�ɂ������̔@���ݏo�������邩��ł���A�ƌ����̂ł��B���l�����ݏo�����w�i�ɂ́A�ܘ_�A�l�Ԃ��������ł̋�Y�Ƃ������̂�����킯�ł��̂ŁA�l�Ԃ̋�Y�Ƌ��ɁA�����̔@���ݏo���Ă����A���̂悤�ȓ����������Ă���̂���n�Ƃ������Ƃł��B���������\���グ��Ȃ�A��n�́A�@���E�l�Ԃɂ��Ă��A�ߋ��⌻�݂̑��݂ݏo���̂����ł͂Ȃ��A�������܂�Ȃ��@����l�Ԃ����A���̑�n�̒��ɏh���Ă���̂��A�܂�A���������h���A���̖����ݏo���̂���n���Ƃ������Ƃł��B �Ƃ��낪�A�������͐k�Ђɂ���āA���̂悤�ȍ��y�������Ă��܂����B����́A�ߋ����猻�݂ɑ��������̏�������������ł͂Ȃ��āA�����������������Ƃ��Ӗ�����̂ł��B�����ɁA��ЊQ�������������Ɣ߂���������悤�Ɏv���܂��B ���u��n�v�͎����Ȃ� ����A������̍u�������������܂����B���̒��ň�ۂɎc��܂����̂��u��]�̔��͐�]���Ƃ�������ǂ��Ⴄ�B��]�����������ł͐l�Ԃ͐�]���Ȃ��B��]�Ƃ͑S�Ă��������Ƃ��B�������D���邱�Ƃɂ���āA�l�Ԃ͐�]����̂��v�Ƃ������t�ł����B���́u�S�Ă��������Ɓv�́u�S�āv�̒��ɂ͉ߋ��⌻�݂����ł͂Ȃ��A���ꂩ�琶���Ă������Ƃ��関���܂Ŋ܂݁A���ꂪ���ꂩ��D���Ă��܂����Ƃɂ���āA�l�Ԃ͐�]����̂��ƌ����̂ł��B�u�S�āv�Ƃ������t����������A���y�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤�B�������A��قǐ\���グ���悤�Ɂu���y�v�Ƃ́A�P�ɏꏊ�Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�������܂߁A����Ȃ��l�Ԃ�@���ݏo�������Ă��������A���Ȃ킿�u��n���v�ł���B�Ƃ���Ȃ�A���́A�k�Ђɂ���āA�ꏊ�Ƃ��Ă̍��y���������Ƃ��Ă��A�����Ƃ��Ă̑�n���̂��̂́A�����āA�����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B ���������\���グ��Ȃ�A�k�Ђɂ���đS�Ă������A�����ɐ�]�Ƃ��������Ȃ��悤�ȏ��������Ƃ��Ă��A�u��n���v���������A�����āA����������ꂽ�̂ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�Ƃ��āA����������ꂽ�悤�Ɍ����邯��ǂ��A����́A�����Ɍq�����Ă����悤�ȁu���v��������ꂽ�Ƃ������ƂȂ̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B���������A�����Ƃ́u�������炸�v�A�܂����Ă��Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł��̂ŁA���݂̂�����ɂ���Ăǂ̂悤�ɂ��ς��̂������Ȃ̂ł��B �����āA�������́A���A���ɁA�u���̂��v�����āA�����ɐ����Ă���A���̌��R���鑶�݂̎����ɁA���́A��n������̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B���l�̋����ɂ���āA�����̂��ƂɋC�Â����Ă��������B�܂�A�����ɐ����Ă���A���́u���̂��v���̂��̂̒��ɐl�Ԃ������Ă����悤�ȁu��n�v������A�܂��A�������������J����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B ����y�ɐ����� ���̈Ӗ��ł́A�l�Ԃ́A�{���A��n�ɐ����鑶�݂Ȃ̂��B�����ɋC�Â����Ă����������Ƃ��o����Ȃ�A�u�S�āv���������l�Ԃ��A�ĂсA�l�ԂƂ��ė����オ���Ă������Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����B���̂��Ƃ���ԁA����Ă����̂��A�ЊQ�ŖS���Ȃ�ꂽ���X�ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B���̂悤�ȑ�n���A�e�a���l�͔@���̑�n�A���Ȃ킿�u��y�v�Ƃ������t�ŋ����A�u��y�Ƃ�����n����v�u��y�ɐ�����v�Ɨ�܂��ĉ������Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�܂���B �����n�������r���A���O���c�s�ŁA����̑�Ôg�ɑς��ėB��c�����u��Ղ̈�{���v���ڂɗ��܂�܂����B���̈�{���ɊF����͉������Ă����łȂ�̂ł��傤���c�B���Ƃ����̂́A���̂����ł��悭�ے����Ă���Ǝv���܂��B���͑�n���琶�ݏo����A���ݏo���ꂽ���͑�n�ɂ������藧���ė���Ȃ��悤�ɁA��n���琶�ݏo���ꂽ�l�Ԃ͂��̑�n�𗧋r�n�Ƃ��āA�������痣��Ȃ��B���̐��܂ꂽ�����ꂼ�ꂪ���̑�n�Ōq����Ȃ��琶���A�₪�āA��n���琶�ݏo���ꂽ�l�Ԃ��A���̐g���n�Ƃ��Ď��̂��̂������ł����B�����ɐe�a���l�������ĉ�����u��y�ɐ�����v�Ƃ������E������Ǝv���܂��B ��������ꂸ�Ɍ����A�u��y�ɐ�����v�Ƃ������t�̈Ӗ��́A�����̂��߂ɐ�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��̂ł��B��������ƁA�l�Ԃ͎����̂��߂ɐ�����Ƃ������Ƃ��A�x���߂��܂��ƁA�����̂��Ƃ������������Ȃ��Ȃ��đ��l�������̂��A���ɂ́A�����̊k������ČǗ����Đ����Ă�����������܂���B���̊k�̂��Ƃ���łƌ�����ł��B��y�Ƃ����̂́A�����̊k����鐢�E�ł͂���܂���B�ނ���A��ł����j���āA�L�����E�����邱�Ƃ��C�Â����ĉ�����̂ł��B �u��y�ɐ�����v�Ƃ́u��y�̕�F�ƂȂ�v�Ƃ������Ƃł��B��y�̕�F�ƌ����Ă��A����т₩�Ȉ߂�Z������F�Ȃǂł͂���܂���B�u��y�̕�F�v�Ƃ͑��҂̂��߂ɐ����A���҂̊�т�߂��݂������̊�є߂��݂Ƃ��鑶�݂ł��B�܂�A���҂̂��߂ɐ����邱�Ƃ���тƂ���̂���y�̕�F�ł��B�Ƃ���ƁA�u��y�ɐ�����v�Ƃ́A���҂̂��߂ɐ�����A�N���̂��߂ɐ�����A�����Ė����̂��߂ɐ�����Ƌ�����鐢�E�ł��B�������A���҂̂��߂ɐ����邱�Ƃ��A�����āA�������]���ɂ���Ƃ������Ƃł͂���܂���B �Ⴆ�A�Ⴂ���ꂳ�����Ȃ��q����ɐH����^���Ă���Ƃ��܂��B�����������ɐH�ׂ�q�ǂ��̊���������ꂳ��́A�����ɁA���������H�������Ċ�т�������ȏ�ɁA���炭�A��т������A�����₩�ȍK����������킯�ł��傤�B���҂̊�Ԏp�����āA��������тɖ����Ă����A���̂悤�Ȑ��E����y�Ȃ̂ł��B ���������\���グ��Ȃ�A�u�N���̂��߂ɐ�����v�Ƃ����u�N���v�Ƃ́A�c�̌q����Ō����A�u�����ɐ�����q�ǂ������v�Ƃ������Ƃł��傤�B�q�ǂ������̍K�����肢�A�q�ǂ������̊�т�����̊�тƂ��A�q�ǂ������ɖ���������Ă����B�����āA���̌q����Ō����A�u�F�v�Ƃ������Ƃł��傤�B�ꂵ�����Ƃ�h�����ƁA�߂������ƂɌ��������Ȃ���A�����Ɋ��Y���Ă����F�B���̗F�����A��y�̕�F�̎p�ł���A�e�a���l�������ĉ�����u�䓯���v�i�F�����j�ƌ������Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�������̑��݂͑�n�Ƌ��ɂ���B�����Ă݂�A��l��l����n�ł���A��n�ƂȂ��Đ����Ă���B�����āA��n�Ƃ��Đ����Ă����l��l���A���݂��̍K��������Ď~�܂Ȃ��A�����ɁA��y�ɐ�����l�̎p������A��]�̌���������悤�ȋC������̂ł��B�i�O�j �i���ӁE��e���j |