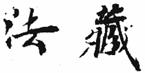法 話
|
恩に報いる‐言葉にまでなった仏様‐
浄影寺報恩講御逮夜法話 浄影寺衆徒 釋弘道 期日 2008年11月1日(土) |
|
2008年11月2日の当院・報恩講御満座前日の11月1日、報恩講御逮夜が勤まり、候補衆徒の釋弘道が話をしました。当日の抄録を掲載します。 ☆【はじめに】 本日は、報恩講のお逮夜へご参詣いただき誠に有難うございます。この報恩講は浄土真宗の寺院にとりまして一年でもっとも大事な法要で、宗祖親鸞聖人のご恩に応えていくご命日の法要です。ご本山・東本願寺では11月21日から28日の一週間勤められていますが、それに先立って全国の各真宗寺院で「お取り越し」と称した報恩講が勤められております。 そこで、親鸞聖人が90年のご生涯を通じて私たちに伝えて下さったお念仏の教えとは何であったのか、そのことをご一緒に考えていけたらと思います。 ☆【報恩講とは-弔から訪へ-】 そもそも、報恩講とは何であるのか。字義で申せば「恩に報いる講(あつま)り」という意味です。つまり、親鸞聖人のご恩に報いるために、親鸞聖人のご命日を機縁として集う御仏事・「ご命日の集い」ということになります。しかしながら、「親鸞聖人のご恩」と申しましても、私たちにとっては何か直接的にご恩を頂いているという感覚はないんじゃないでしょうか。昔から言われますように、父母に対する恩、教師に対する恩ということになれば私たちにとって直接的に恩恵を受けるものですし、具体的なので解り易いわけです。ところが、親鸞聖人のご恩というと解りにくい。親鸞聖人が生きていたのは鎌倉時代ですから、今から750年も前の人ですし、直接、何かしてもらったということは無いわけです。にもかかわらず、「親鸞聖人のご恩」などと言うのは何故なのかですね。そして、「ご恩に報いる」という、この「報いる」とはどういうことなのか。このようなことを考えていく道筋として、親鸞聖人はどのようなご生涯を生き、そして、私たちに何を遺して下さったのか、このことが分かれば、「ご恩」ということも「報いる」ということも、案外、ハッキリしてくるのではないかと思います。 先ほど、報恩講というのは「親鸞聖人のご命日の集いである」と申しましたが、私たちの日常の中でも人が亡くなる、特に身内が亡くなると、亡くなったその年を一年と数えて一周忌・三回忌という具合に年回忌法事を勤めます。余談ですが、仏教では人の年齢について数え年で数えます。普通、赤ちゃんが生まれたらその歳を0歳とし、一年が経って1歳としますが、仏教ではお母さんのお腹の中にいる期間を一年と数えます。また逆に、人が亡くなったら、例えば、満歳60歳で亡くなったとすれば、その年を一年としますので、「61歳で亡くなった」とします。つまりは、娑婆の縁が尽きて亡くなった、その時点で、その人は一足飛びに浄土へ生まれたのである、という考え方です。亡くなった年は、浄土に生まれた年である、とするわけです。それで、亡くなって2年目を三回忌とするわけです。それで、亡くなった日ではあるが命日(命の日)とする。浄土に生まれた日・浄土の命の日、仏様になった誕生日ということになりましょうか。仏様の命に帰る日という意味をもってきます。 そうしますと、亡くなった方のお命日に法事をする、これは真っ先に亡き人を弔うということでしょう。故人を偲ぶ・哀悼するという意味です。しかしもう一つ、「弔」という字を「訪(とぶら)ふ」という意味として使われてもきました。つまり、亡き人を弔うということは、亡き人を単に偲ぶという意味だけではなく、亡き人を訪ねる。亡き人の言葉に耳を傾けながら、亡き人の心を訪ねるということである。もう少し言えば、身こそ無けれども、その人が遺してくれた言葉を手がかりにしながら、その人と本当の意味で出遇っていくという、これが法事を勤めるということではないかと思います。 ☆【出会いから出遇いへ】 私たちは「出会った出会った」と言っていますが、出会ったつもりになっていることが多いのではないですか。「出会う」という字にしましても、顔と顔を付き合わせる・対面するという広い意味で使います。物理的に会うということです。しかし、人は物理的に出会ったといっても、出会ったことにはなっていないことが沢山あります。毎日毎日、顔をあわせている家族であっても、中々解り合えないということもありますし、「出会ったつもりになっていたけれども、お前のことは全く知らなかったんだなあ」ということもあります。そういうことを思いますとき、この「会う」という会い方というのは、人と本当に出遇っていくための「切っ掛け」という意味の出会いではないかと思います。 それに対して、仏教では「出遇い」ということを教えます。「遇」という字からも分かりますように、人との出遇いにはまず「たまたま」ということがあります。それこそ、何かの切っ掛けでたまたま条件が整って出会ったというのが、まず、あるのでしょう。しかし、出遇ってみたら、その人と出遇っていなければ今の私は存在しない、あるいは、その人の存在が私の人生にとって決定的なものになった。もう少し言えば、私がこの世に生まれたのは、この人に出遇うためであったのだ、という。その人の存在が私の人生において掛け替えのない・必然的なものになっていく、そのような出遇い方というものが人生にはあるのだ。その出遇いの意味に気づいたとき、人はそこから新しい歩みが始まって行くものだ、ということを仏教は教えてくれます。そして、そのような出遇うということにしましても、そのような決定的な出遇いによって新しい歩みが始まるということにしましても、そこには、言葉に出遇うということがあります。 ☆【最期の一句の言葉が息子の全生涯】 ある研修の場で40歳程になる女性からお聞きしたお話なのですが、その方はその研修を受ける動機について涙を浮かべながら話されました。それは、5歳なる息子が昨年、小児癌で亡くなったと。その男の子が息を引き取る直前に「お母さん、僕を産んでくれて有難う」と言われたそうなんです。その言葉を聞いたお母さんはこういう受け止めをしました。「息子は「お母さん、僕を産んでくれて有難う」という言葉を遺して亡くなった。5年という短い人生だったけれども、その言葉がこの子の人生の集約なんですね。その子がその一句の言葉になって、今の私を照らしていてくれています」と言われたんです。 つまり、わずか5年という生涯を生きた亡き息子さんが最期に遺した「お母さん、僕を産んでくれて有難う」という言葉が息子さんの全生涯を言い尽くしているのだ。亡くなって身こそ無けれども、その最期の言葉が亡き息子さんそのものになってお母さんを照らし、親鸞聖人の言葉に出遇わせて下さった。もう少し言えば、最期の一句の言葉が息子さんそのものである。だから、その言葉を憶うとき、いつでも息子さんと出遇っていける、ということでしょう。そして、その息子さんの言葉に励まされて、親鸞聖人と同じようにお念仏の道を歩んで行く身にさせていただいたのです。 「人は死して名を遺す」という言葉がありますが、その「名」というのは名声ということでしょう。この名声というものは記録としては残りましょうけれども、それほど人々の記憶には残りません。その名が人々の記憶に残るというときには、その名が単なる名ではなくして、人々の心に常に働いて止まないということがあるということです。その意味では、本当は、人は死して言葉を遺すのでしょう。言葉になって後に続くものを照らし、道を歩ませるということがあると思うのです。つまり、その人亡き後も、働き続け、人を生み出すということがあって、その亡き人のことがずっと語り継がれていくのです。その意味では、名というものも突き詰めれば言葉です。その人の生涯が名という言葉になって語られる。あるいは、その名を呼べば、いつでもその人に出遇うことができ励まされる、そういうものなのでしょう。そうすると、道を歩むということも決して一人ではない、孤独ではないということです。その人の言葉・名によって励まされるということになると、その亡き人と共に道を歩んでいるということになるのです。 逆に申せば、言葉としての名によってその人の人生が語られ、名そのものに、その人の願いが語られていると言っても過言ではないのでしょう。もう少し言えば、遺された者に対して道を歩むことを促していくような願いというものが、言葉としての名に託されているということだと思います。そうしますと、親鸞聖人が南無阿弥陀仏という仏様のお名前、つまり、名号を大事にされ、人にも伝えられたということも、実は、仏様の願いが言葉としての名前になったというところに大変な意味を見出されたのではないかと思います。 ☆【言葉として働く名-南無阿弥陀仏-】 仏様というのは勿論、阿弥陀仏です。しかし、単なる阿弥陀仏ではない、南無阿弥陀仏です。「南無」という二字がついて初めて、私たちの身に働き、私たちと深い関係がある仏様なんだということが解るのです。南無阿弥陀仏は古代インドのサンスクリットの音を漢字で写したもの(音写)に過ぎません。つまり、古代インドの言葉を私たちは称えているということです。この言葉が意味として表記されるときには「帰命尽十方無碍光如来」となります。簡単に言えば、「十方を隈なく照らす光の如来に帰依します」という意味になります。この言葉、特に「帰命」という言葉に親鸞聖人は着目され、帰命というのは「仏様の願いの呼びかけが届いたということだ」(如来本願招喚の勅命)と訳しました。仏様がご自身の名前に託して「教えに従って真実の道を歩みなさい」と呼びかけて下さるということです。 そうしますと、仏様の名前と言っても記号のようにあるのではなくて、名前が働くということです。仏様の名を聞けば仏様の教えをいつでも思い出せて、自分の道・生き方がハッキリしているということです。自分の道・生き方がハッキリするとはどういうことか。それは、ゴール地点がハッキリしているということです。そのゴール地点の名前をハッキリ覚えていれば道に迷ったとしても、同じようにゴールを目指す人に道案内をしてもらえる。だから、安心して迷えるということです。自分の身に降りかかってきている問題を解決したとしても、迷いや不安がなくなるということがないのが私たちです。それは、自分の身に降りかかる問題によって迷っているというよりも、私の存在それ自体が不安や迷いの種だからです。つまり、問題は自分の外にあるのではなくして、私自身の存在が問題になっているということです。その意味では、不安や迷いをなくすことが浄土真宗の救いではないだと思います。人が生きるということは迷いや不安を抱えながら生きるということですし、迷いや不安があるということが「生きている証拠」のようなものです。しかし、その迷いや不安が苦にならない、安心して迷っていけるというのが浄土真宗なのです。親鸞聖人は人間の存在を「煩悩具足の身」と言われましたが、まさしく、煩悩が一つも欠けることなく完全に備わっている、そういう煩悩の塊がこの身なのです。ですから、生きるということは煩悩の塊を生きるということなのでしょう。 ☆【南無阿弥陀仏は生ける言葉の仏身なり】 話が戻りますが、仏様のお名前は意味としては「帰命尽十方無碍光如来」ですが、音としては「南無阿弥陀仏」です。この「意味としての名前」と「音としての名前」について、親鸞聖人は使い分けをしておいでになりますが、ここでは詳細は申しません。ただ、音として名前を見て行くときには、やはり、声、あるいは呼び掛けとして見ていかれたのです。その名を呼べば(聞けば)、この私を呼び掛けて下さっている仏様にいつでも出遇うことができると。先ほどの、5歳の息子さんを亡くされたお母さんのことで申しますと、「僕を産んでくれて有難う」という言葉を思い出せばいつでもその子と出遇える。そして、この自分を前へ押し出してくれる、そういう働きが言葉、そして言葉としての名前にはあるのです。 南無阿弥陀仏について曽我量深先生は「南無阿弥陀仏は生ける言葉の仏身なり」と教えて下さいました。本当の仏様というものは生きた言葉にまでなって下さっているのだと。その生きた言葉がいつも不安でいっぱいの私を励まし、不安を抱えながらも生きていく勇気を与えて下さる、そういう言葉にまでなった仏様が南無阿弥陀仏だと思います。私たちは南無阿弥陀仏によって、不安を抱えながらも、ようやく不安に立って生きる身にさせてもらうのでしょう。親鸞聖人が教えて下さった南無阿弥陀仏、つまり、言葉にまでなった仏様のお名前・名号すなわちお念仏を真宗門徒として、これからも大切にして生きたいと思っております。(完、文責 浄影寺) |