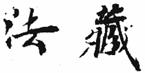法 話
|
|
2007年9月23日、浄影寺において秋季彼岸会法要・門徒物故者追弔法要が勤修され、衆徒・釋弘道が法話を行いました。当日の抄録を掲載いたします。 ☆【はじめに】 本日は、ご参詣いただき誠に有難うございます。少しばかり、時間を拝借いたしましてお話をさせていただきたいと思います。講題は「彼岸と此岸」です。この講題から「まあ、彼岸にちなんだ話だろうと。でも、そもそも彼岸は何となく分かるけど、此岸とはなんだ?」、こういう疑問をもたれると思います。しかし、決して、仏教行事としての彼岸をご説明するということは、さらさら考えていません。そこでサブタイトルに「悲しみを背負ったものを照らす光」という言葉を付けさせていただきました。まあ、講題というのは「一部の総称」と言いまして、そのタイトルがお話全体を言い尽くしているような意味を持つほど、非常に大事な訳です。その意味では講題をお示しできれば、大体、話が終わったと言っても過言ではない(笑)。これからお話しすることはその補足になるかもしれませんがご清聴ください。 ☆【二河白道の譬え】‐善導の信仰告白‐ 講題でもお解かりのように彼岸と此岸という言葉は対句になっています。彼岸というのは「彼の岸」、此岸というのは「此の岸」。しかし、一体、何のことを言っているのだろうという疑問が起こってまいります。 端的に申せば、彼岸は阿弥陀仏の浄土のこと、此岸はこの世、娑婆世界のことです。つまり、「彼岸」(浄土)ということを考える時には、自ずと、此岸(娑婆)、つまり私たちの現実生活を考えざるを得ないんですね。それはなぜか、私たちが生きている現実生活を照らし出すのが浄土だからなんです。 浄土真宗をお開きになった親鸞聖人が、浄土真宗の歴史を担った代表として七人の僧侶を挙げられておりますが−これを七高僧という−、その第5番目、中国・唐の時代に生きた善導大師という方がおられます。その方が浄土三部経の一つである『観無量寿経』の注釈書を書かれ、そこに「二河白道の譬え」が記されてあります。これは一般的には善導大師の信仰告白とも言われています。ここに彼岸ということが出てまいります。どういう話かと言いますと・・・ まず、そこには、広野で旅をする一人の旅人が描かれています。この「一人の旅人」というのは善導大師ご自身であると同時に、人間存在の苦しみに喘ぐ人、全ての人を象徴する「一人」です。つまり、人間である限り背負っていかなくてはならない苦悩を「一人の旅人」として表現して下さっているのです。私なりに現代語訳してみました。 「まさに旅人が誰もいない広野の中で、西に向かって旅をしている。その先には、忽然として二つの河が立ちはだかっている。南に火の河、北には水の河があり、おのおの百歩ほどの幅で底が見えないほど深い。その間に、四,五寸ほどの細長い白い道があり、この道も長さが百歩。しかし、その道を火の河の炎が焼き尽くし、水の河の波が潤していく、それの繰り返し。そのとき、旅人がたった一人であることを見た群賊悪獣が背後から殺そうと向かってくる。旅人が死を恐れて西に向かうと、旅人の行く手を阻む火の河・水の河があり、しかも、一本の道はあれども、旅人を焼き殺すか・溺れさすかどちらかしかない。この状況の中で旅人は決意する。“我今回らばまた死せん、住まらばまた死せん、去かばまた死せん”と決意し、どうあがいても死を避けることができないならば、狭い道なれど先人が渡ったであろうこの道がある。これを尋ねて行こう。その時、東の岸から“仁者、この道を尋ねて行け”そして西の岸から“汝、直ちに来たれ。我よく汝を護らん”という声が聞こえてきた。・・・」(私訳) 少し長くなりましたが、ここに西の岸・東の岸が出てきます。 ☆【一人の旅人】‐存在自体の孤独と、人に出遇えない悲しみを背負って生きるもの‐ この譬えで注意したいのは、まず「一人の旅人」という点です。私たちはどれだけ「いつも皆と一緒だ」と言いましても、「私」の人生においては「私」にしか責任が取れないということを教えています。他人が「あなたの人生を生涯保障します」と言ったところで、結局、自分が自分の人生を選び、切り開いていくしかないのです。 つまり、私という存在の全責任者は私であるということです。 『大無量寿経』(下巻)に 「人、世間の愛欲の中にありて、独り生じ独り死し独り去り独り来りて、行に当り苦楽の地に赴く。身、自らこれをうくるに、たれも代わる者なし」と。 子どもが病気で苦しんでいるとき、子どもにどれほど愛情深い親があったとしても、子どもの病気を代わってあげることはできません。このことが象徴しているように、私の人生は私が背負って行かなければならない、その意味では、人というものは、本質的に、常に孤独を感じつつ生きるものであるのでしょう。 そしてまた、その孤独というものは、人生の中で本当に道を教える人に出遇えないという悲しみを教えているのです。つまり、人として生きていながら「人」に出逢えないという問題です。と同時にそれは、自分は人として生きながら「人」として生きることができないということです。 釈尊が誕生した時に、その父であるスッドダーナ王はアシタ仙人に釈尊の将来を占ってもらったという。ところが、赤ん坊である釈尊を抱いたアシタ仙人は涙を流したという。王が訊ねるとアシタ仙人は「この赤子がこのままお城に留まれば、世にも稀な偉大な王となり世界を統一するであろうと。もし、お城を出れば、人類を救うブッダ(目覚めた人・真の人)となりましょう。しかし、私は老齢にしてこの赤子が仏陀になる頃には死んでいる。真の人に出逢えないことが悲しいのだ」と。人として生きながら「まこと」の人に出逢えない、これほどの悲しみが人間にあろうものか、ということです。このアシタ仙人の悲しみは同時に、人間として生きる全てのものの深い悲しみとして教えられています。 今の私たちの社会状況を省みてみます。人間という言葉がありますが、人と人との間柄、人と人の結びつきを意味する言葉が「人間」ということです。しかし、現実には、そういった間柄や結びつきを切っていく状況、いや、むしろ、人間が人間を暴力によって抹殺していく状況になっています。それが戦争であり、凶悪化する殺人事件。そういう世界を仏教では地獄と言います。地獄というものはどこかにある世界というのではなくて、いつでも人間が作っていくものでしょう。そうではないですか?それに対して浄土という世界は仏様が作ってくださったものです。そういうことを考えますと・・・ そういうことを考えますと、果たして、私たちは「本当に私は人間である」と言い切っていけるんでしょうか。ひょっとすると、人間という仮面をかぶっているだけかもしれません。そういう中で、本当に道というものを教えてくださる「人」に出遇うというのは中々稀有なことではないですか。人生において本当の師に出逢えない悲しみですね。そういう厳しい問いかけを善導大師はしてくださっています。 そしてもう一点、火の河・水の河が旅人を焼き殺したり、溺れさせて死に至らしむる、あるいは、旅人がたった一人であることを見た群賊悪獣が殺そうと向かってくるとか、これは何を意味しているのかと言いますと、これは全て私という人間の内面の状況を言っているのです。これには善導大師は勿論のこと、親鸞聖人も注意なさっています。つまり、火の河は私たちの怒りです。水の河は私たちの貪欲さです。大体、この怒りと貪欲さは死ぬまで持ち続けていくものではないですか。 親鸞聖人のお手紙に 「凡夫というは、無明煩悩われらが身にみちみちて、欲もおおく、いかり、はらだち、そねみ、ねたむこころおおく、ひまなくして、臨終の一念にいたるまでとどまらず、きえず、たえず」(『一念多念文意』) と仰っていますが、人間というものは、死ぬ寸前まで怒りや妬みが消えないんだと。 ちょっと余り宜しくない話になりますが、 あるお爺さんがご臨終になったと。その後、そのお爺さんの枕元でその息子たちが遺産相続の話でもめていた。すると、亡くなったはずのお爺さんの口から「お前たちには渡さん」と言ったと言うんですね。これは本当かどうか分かりませんよ。分かりませんけれども想像できることです。自分の臨終が近づきつつも、財産が心配で安心して死ねないと、こういうことは考えられないことではないと思います。 そういうですね、怒り・妬み・貪欲というものがその人の人生を焼き尽くし、溺れさせていくということです。群賊悪獣が襲い来てこの私を殺すのかと思っていたら、この群賊悪獣というのは、実は、私という人間の中身そのものだったということです。もう少し言えば、私の身と心が群賊悪獣の正体だったのです。 ☆【他化自在天の大魔王】‐怒りと貪欲さで固めて生きる私たち‐ そもそも、この娑婆は力がものをいう世界です。逆に言えば、力の持たない者は我慢しなくてはならない世界です。仏教で娑婆を「堪忍土」とも言います。つまり、耐え忍ぶ世界です。だから私たちは力を付けて生きていこうとします。力と一口に言っても色々ありますが、学歴・経済力・体力・地位など。また人を人材と見る考え方も、人的資源と見、役に立つか役に立たないかで判断してしまうんでしょう。そういう「力」というものを基準にして出来ている世界を娑婆と言います。そこで生きる私たちは常に天を目指して生きています。 仏教で言えば、私たちは他化自在天を目指して生きている。「他化自在天」というのは、他の人の力で成り立っている生活を言います。他の人が準備してくださったところに胡坐(あぐら)をかいて生きている在り方・・・親鸞聖人の言葉には「他化天の大魔王」とありますが、これは私たちのことです。大魔王ですよ。お金を出せば何でも出来るという風潮がありますが、確かに、そういう一面もありましょう。しかし、 しかし、私たちがこうして生活できるのは、そこに多くの人の働きというものがあるからです。作物を作る人、魚を採る人、水を供給する人、物を作る人、石油だって中東地域から運搬してくるんですよ。そのことに意識を持たず、この生活が当たり前だと思って生きているものを親鸞聖人は「他化天の大魔王」と言ったのです。そういう、力によって幅を利かせ、怒りと貪欲さで自分の身を固めている私たちが、他化自在天を目指して生きていく中で、他人を踏み台にし、他人を傷つけ、場合によっては人を排除し、地獄という世界を作ってしまい、いつしか、怒りと貪りによって自分自身を潰していくんでしょう。そういう私たちのあり方、存在をキチット照らしてくださるのが阿弥陀仏であり浄土という世界です。 ☆【悲しみを背負ったものを照らす光】‐如来からの願いと呼びかけ‐ この彼岸、つまり浄土という世界は、親鸞聖人の言葉をお借りすると無量光明土という世界です。無量の光明、量ることの出来ないほどの光を放つ世界だと。と言っても、光というものはそれ自体のみで存在するものではございません。光は、闇を破って明るくするという働きによって、その存在を証明しているのです。つまり、光は物にぶつかって明るくなり、そこで初めて光ということが分かるのです。当たるものがない空間では光は光の証明ができません。つまり、闇を破るという働きによって光は光になるのです。 つまり、阿弥陀仏の浄土は光の世界だという時は、そこに何らかの働きがあるということです。どういう働きかと言えば、人間存在の中にある深い闇を破るという働きです。 先ほど最初に触れました「二河白道の譬え」で申しますと、戻っても留まっても進んでも逃れることの出来ない「死」というもの、それから、人を押しのけながら天を目指し、人が人を傷つけながら生きているという在り方、そして、そういう中で人として生きながら「人」に出逢えない、「まことの人」に出逢えない、そういう悲しみですね。一見、華やかに見えるような生活の中にあっても、あるいは、豊かに見えるような生活を送っていても、心の深いところに悲しみや淋しさ、そして存在の孤独を感じながら生きている私たち。つまり、存在それ自体がもっている孤独性を感じつつ生きている。そういう私たちに対して、一筋の光を放ってお出でになる仏様が阿弥陀仏です。そして、その光・光明に乗せて願いと呼びかけというものをかけてお出でになります。その阿弥陀仏の願い、呼びかけを本願と言います。根本の願い、人間にとっての根本の願いです。 どういう願いか、簡単に言えば、「十方衆生よ、念仏するものになって下さい」ということ。念仏するものを助けると。現代風に言えば、その呼びかけは「人間であるあなたよ、どうぞ、本当の人間になってください」ということです。「人間として生まれたあなたよ、人間であることに目覚めてください」ということ。もう少し言えば、人間を失って生きる私たちに対して、人と人の間柄を生きるものになってくださいということだと思います。 浄土真宗は「往生を説く仏教」と言われますが、往生ということは、人間を仏にする前に、人間を人間にしてくださる、そうして仏にして下さるということです。本当に、人間を見失いかねない娑婆世界において、人間として生まれたものを本当の人間にして下さるのだ、悲しみを背負って生きるものに対して、阿弥陀仏はその悲しみを一身に担って下さる、そういう光の世界が彼岸・浄土ということだと思います。 大変、纏まりのない話になりましたが、ご清聴いただき有難うございました。 (終了、文責 浄影寺) |
|
|