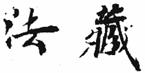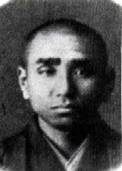法 話
|
|
2006年8月23、24日の両日、東本願寺東北別院で暁天講座が開催され、講座初日に当院の衆徒・釋弘道が出向し法話を行いました。当日の抄録を掲載しご報告致します。 ☆【はじめに】‐講題「浄土ノ真宗」について‐ おはようございます。このたび、ご縁を頂戴しまして、東北別院様の暁天講座へお参りをさせていただくこととなりましたことに、まず、御礼を申し上げます。
今回、「浄土ノ真宗」という講題を掲げさせていただきました。ここにご参詣いただいております皆様にとっては、今さら、「浄土真宗」ということを考えていくということは、いわずもがなのことでございましょう。特に。「浄土真宗」という言葉を聞いたとき、すぐさま浮かんでくるのは宗派名でございます。しかし私は、ここで一度、意識的に宗派名としての「浄土真宗」ということを外し、そもそも、親鸞聖人が「浄土真宗」という言葉で何を明らかにし、人間をどうしていこうとされたのか。もう少し言えば、親鸞聖人が「浄土真宗」という言葉で確かめられた仏教とは、一体、何であったのか。このことを一緒に考えてみたいと思い、親鸞聖人に習って、あえて、「ノ」という一時を加え、「浄土ノ真宗」という講題を掲げさせていただいたのです。 ☆【近年の時代状況】同時多発テロ・アフガン・イラク、そしてレバノン
さて、親鸞聖人の仏教を考えていく上で、社会や人間生活の中で起こっている状況を知ること必要不可欠のことと思います。そこ で本題に先立ちまして、まず、私たちが置かれている社会状況を確認してみたいと思います。 「グローバル」あるいは、「グローバル・スタンダード」という言葉をよく耳にされると思います。つまり、近年、「グローバル・スタンダード」という名の一つの価値観が世界を覆いつつある中で、2001年9月11日、世界を震撼させた「アメリカ同時多発テロ事件」が起こり、それ以降、世界情勢は一転してしまったことは皆さんご承知のことと思います。アメリカは、アメリカの「正義」を基準に、世界を敵か味方かという単純論法で二分割し、それが「世界で最も貧しい国の一つ」と言われているアフガニスタンへの空爆から始まりイラク戦争が起こりました。 「同時多発テロ」によって多くの市民が殺されたことに対しては、テロリストに対して非情に許しがたく、憤りと悲しみを感じます。しかし、それがゆえに、凄惨な事件の犠牲者となり、深い悲しみを背負ったアメリカが「テロとの対決」という名のもとに、テロリスト以外の大多数の人々を巻き込み、超大国の軍事力という巨大な暴力によって人間を殺していく状況に、深い悲しみを覚えます。そして最近では、アメリカと同様、「テロとの対決」という旗印を掲げたイスラエルが、レバノンを徹底攻撃をしています。あの激しい空爆によって、子どもを初め、多くの無辜の民が殺されている惨状があるのです。つまり、巨大な暴力によって多くの人を無差別に虐殺する状況が起こり、戦争という異常な空間によって、人間が人間であることを失っていく、そのような状況が世界で起こっています。 ☆【まなざし】
そして、そのような暴力が行われている状況に対して、ある意味では、助長していくことに働いてしまっているのが「無関心」です。この、世界の中で起こっている戦争・暴力や貧困問題などに対して多くの人の無関心が、暗に暴力を容認し、解決を長引かせる要因にもなっていると思います。 大谷派の先輩の言葉に次のような言葉があります。 「人を愛するということの一番もとは、その人にまなざしを向けること」 「眼差し」というのは、その人の存在を見つめ、その人の悩みや苦しみ・悲しみを自分のこととして受け止めていく、そのような眼ですね。それに対して、人が苦しんでいる状況に眼差しを向けない状態を「無関心」というのだと思います。これに対して、親鸞聖人は、社会の状況や人間の苦悩に対して眼差しを向け、人間存在を見つめていったことは言うまでもないことです。 ☆【幸せとは表現すること】−2002年4月2日「全戦没者追弔法会」− さて、本山・東本願寺(京都)では毎年4月の「春の法要」にあわせて「全戦没者追弔法会」(※1)というご法要が勤修されています。2002年4月2日には、「21世紀の子どもたちへ 戦争・いのち・平和−世代をつなぐ対話−」というテーマで行われ、午前に作家の大江健三郎さんの講演、午後は大江さんと10代20代の青年とのシンポジウムが行われました。 そのシンポジウムの中で、一人の高校生が大江さんに質問をしました。 「イスラエルがパレスチナを攻撃している状況の中で、パレスチナの子どもたちは幸せを感じることができないと思う。幸せってなんですか」と。 今日でも言えることですが、当時、イスラエルが圧倒的な軍事力をもってパレスチナを激しく攻撃し、多くの死傷者が出ている状況でした。しかし、パレスチナの状況に対して世界は余りにも目を向けていませんでした。つまり、パレスチナに対して世界は眼差しを向けていなかった、無関心だったのです。 その高校生の問いに対して大江さんは、このようなことを言われました。 「幸せとは自分を表現すること。そして、それを邪魔しないこと」と。 この一文の中で二つのことが言われていると思います。一つは「自分を表現すること」、もう一つは「表現をする人に対して邪魔をしないこと」です。 もちろん、大江さんは作家ですので文学を通して自分を表現するということが課題だと思います。芸術家は芸術を通して、音楽家は音楽を通して自分を表現することが課題だと思います。同じように、私たちもまた、生きるということにおいて表現している、言わば、人は皆、表現者なのだと思います。つまり、生きるということは表現するということだと思います。いな、一人の人間がそこに存在していること、そのこと自体がすでに表現。存在自体がいのちの表現なのでしょう。その表現に対して邪魔をし、抹殺し、表現することを許さないのが戦争という暴力なのです。 続けて大江さんは、数日前に起きたパレスチナの18歳の少女の自爆テロについて触れ、親交のあったパレスチナ系アメリカ人思想家のエドワード・サイード(※2)の言葉を紹介されました。 「パレスチナの少女の自爆テロについてサイードは「テロはいけない。しかし、テロという形をとらなければ、パレスチナの問題を世界に知らせることができない」と。世界の様々な場所で起こっていること、世界の様々な場所で人間がどのように生きているのかを意識してほしい」と。 先ほどの眼差しということですね。社会の様々な状況に対して本当に眼差しを向けるということができるならば、その状況に対して動かざるをえなくなるのが人間なのではないでしょうか。逆に、人間が巨大な暴力によって虐殺されている状況があるにも拘わらず眼差しを向けないとか、無関心であるとすると、果して、私たちはどこまで人間であり続けられるのか、という問題を提起していると思います。無関心によって人間は人間を喪失していくことになる、という提起です。 そのような問いかけが、実は、親鸞聖人の仏教にあるのではないでしょうか。つまり、社会や人間の様々な苦悩と無関係に仏教があるのではありません。人間の現実生活を問い、その現実生活に具体的に働く仏教こそ、親鸞聖人が明らかにされた浄土真宗ではないかと思います。 ☆【行動する仏教】 ベトナム戦争(※3)が続いていた1960年代に、ベトナムの仏教徒、ティック・ナット・ハーンが(※4)「エンゲイジド・ブッディズム」(行動する仏教)を提唱しました。この考えが世界に衝撃的な形で知られるようになったのは、ベトナムの一人の仏教者が「焼身供養」をした1963年(6月11日)の出来事です。当時、ベトナムのサイゴンでティック・クアン・デュックという一人の仏教者がベトナムの平和のために「焼身供養」をし、その後、20人の尼僧が「焼身供養」しました。戦争という凄惨な状況の中で民衆の苦しみを解決したいということでの行動だったのです。それ以降、ベトナムの仏教は民衆のもつ苦悩や悲しみに対して行動していく道を歩んでいくことになりました。民衆に向けた眼差しがベトナムの仏教を動かしたのです。
「行動する仏教」ということで言えば、私たち大谷派にとって忘れることができないのが高木顕明さん(※5)です。顕明さんは明治期に生きた大谷派の仏教者です。縁あって、和歌山の多くの被差別部落のご門徒を抱える寺の住職になります。そこで目の当たりにしたのは、厳しい部落差別の現実に苦しむご門徒の姿でした。そしてご門徒の出遇いの中で顕明さんは、部落差別問題や戦争の問題について深く考えるようになり、やがて一人の念仏者として行動を起こしていきます。 顕明さんが生きた時代は、日清・日露戦争に日本中が沸き立ち、ほとんどの宗教教団は戦争協力をしていくという状況でした。私たち大谷派教団も例外ではありませんでした。そういう中で顕明さんは、「非戦論者」を宣言し、戦争や差別に対して異議を唱えていきます。そのような状況の中で、1911年、「明治天皇暗殺」という国家が捏造し社会主義者や無政府主義者を一掃するという、いわゆる「大逆事件」(幸徳事件)が起こり、24人が死刑判決を受けます。この事件に連座した一人が高木顕明さんでした。死刑判決(翌日、無期懲役に減刑)を受けた顕明さんは、収監された秋田刑務所で自死されました。大谷派は「宗門近代史検証」という取り組みの中で、高木顕明さんの復権の取り組みをしています。 このように、仏教の教えを聞くものが現実の社会や人々の苦悩に眼差しを向けたとき、人々の苦悩や社会を課題にし、そのことに入っていかざるを得ないのです。なぜなら、仏教はもともと、人間の苦悩や社会を課題にしているからです。そもそも、人間は他者との関係なくして存在することはできないものなのですね。 ☆【人間(ジンカン)−間柄を生きる】 私たちは「人間」という言葉を何気なしに使っていますが、もともとは「ジンカン」と読み、社会との関わりを意味する言葉です。その意味では、「人間」という言葉の中に、すでに、社会が意識されているのです。文字どおり人と人の間柄、人と人の繋がりの中で生きる存在が人間です。つまり、間柄を生きるものを「人間」と呼ぶならば、世の中で起こっている様々な出来事や社会と無関係で生きるとか、無関心であるということは、少なくとも「人間」と呼ばないということです。そういう状況を生きている私たちに対して、如来は「人間になれ」という願いをかけて下さっています。 ☆【浄土真宗の救いは二段構え】 大谷派の碩学に曽我量深という方がいます。曽我先生に次のような言葉があります。 「浄土真宗の救いは二段構えである。如来はまず我々を人間にしてくださる。そうして仏にしてくださる」 ご承知のように、浄土真宗の特徴は往生を説くことにあります。曽我先生は、仏教の目標である成仏に先立って、人間として生まれたものを人間にしてくださるのが往生であると。もう少し言えば、人間を人間にするのが浄土真宗の教えであるということです。しかし、「人間を人間にする」ということに違和感を持たれる方が多いかもしれません。「初めから人間に生まれたものがなぜ人間になる必要があるのだ」という違和感です。
先ほど最初の方で申し上げたように、人間が人間に対する眼差しというものを失い、人と人の間柄を断絶し、戦争という暴力によって人間を殺していく状況にあって、本当にどこで「人間」ということが言えるのかということです。こうした人間が人間を喪失していく現実状況に対して、如来は人間になる教えを示してくださるのです。人間として生まれたということは、決して、完成された人間として生まれたのではないのでしょう。むしろ、人間にならせていただいたからこそ、そこから人間の歩みが始まるのではないでしょうか。 だから、人間として生まれながら人間を見失っていく私たちに対して、如来はまず「人間にならしめよう」とする。廣瀬杲先生の言葉をお借りすれば、「人間であるあなたよ、真の人間たれ」(本当の人間になってください)と呼びかけておいでになるのである。つまり、私たちに対して、如来は「人間であるあなたよ」と呼びかけ、仏になることに先立って、まず人間にしてくださるのだ。この呼びかけ・願いを「阿弥陀の本願」というのでしょう。 ☆【宗教とは生涯を尽くしても悔ゆることのない ただ一句のことばとの出会いである】 曽我先生と同じように、同時代を生きた金子大栄という方がおられます。金子先生の言葉に、 「宗教とは生涯を尽くしても悔ゆることのないただ一句のことばとの出会いである」と。 この言葉を受けて、「宗教」という言葉を「人生」あるいは「人間」という言葉にも置き換えることができると思います。なぜなら、およそ、宗教なるものは、人間の存在を根底から支え、存在の意義を与えるものだからです。言わば、人生そのものが「宗教」という名に収斂されていくのだと思います。その意味では、「人生とはただ一句の言葉との出遇いである」と言い直すこともできるのでしょう。 人生の中で、様々な言葉が飛び交い、時には人を傷つけ、悲しませ、貶めていく言葉もありましょうし、戦争や暴力に駆り立てていく言葉もあるのでありましょう。しかし、言葉というのはそれだけではないですね。人を喜ばせたり、勇気づけたり、生きる力になる言葉もあります。ある意味では、人間を活かすも殺すも、どうにでもしてしまう力が言葉にありますし、言語が生活を作っているとも言えましょう。 そういう中にあって、たった一つの真実の言葉が人間を回復させるということにはたらく。言葉は様々あるけれども、人間存在そのものを、根底から奮い立たせていくような、そういう言葉は一句でよいのだ。親鸞聖人にとっては「南無阿弥陀仏」がその一句の言葉であったと思います。この南無阿弥陀仏こそは、人類の苦悩と共にあったのでしょう。 ☆【再び、浄土真宗とは】 「あなたにとって浄土真宗とは何か」と聞かれたら、私は、 「私にとって浄土真宗とは、一句の言葉との出遇いによって、人間が人間になっていく仏道である」 もう少し言うならば、 「一句の言葉によって、人間を人間にしていく仏道が浄土真宗である」と。 そのように言い切ってみたいのです。非常に纏まりのない話になりましたが、時間が参りましたので、これで失礼させていただきます。(終了、文責 浄影寺) |
|
【注】 |
|
|
※1 全戦没者追弔法会 |
現在の名称で勤修されたのは1987年(昭和63)4月から。以前の名称に、真宗の教法に基づいた法要をすることから「法」の字を、十方衆生と呼びかけられていることから「全」の字を付加して勤められている。 1995年6月に真宗大谷派「不戦決議」が発表されている。 |
|
※2 エドワード・サイード |
パレスチナ系アメリカ人思想家。パレスチナ問題に関する著述が多い。著書に、『知識人とは何か』、『戦争とプロパガンダ』、『ペンと剣』など。 |
|
※3 ベトナム戦争 |
1960〜75年の北ベトナム・南ベトナム解放民族戦線とアメリカ・南ベトナム政府との戦争。1975年4月、解放戦線・北ベトナム軍が勝利し戦争終結。 |
|
※4 ティック・ナット・ハーン |
1926年、ベトナム中部に生まれる。エンゲイジド・ブッディイズムを代表する僧侶。ベトナム戦争中、難民救済活動開始。60年代後半、フランスに亡命。現在も、平和運動に取り組む。 |
|
※5 高木顕明 |
1864年、愛知県に大谷派の門徒として生まれる。1899年、35歳で和歌山で寺の住職に就任。厳しい部落差別に苦しむご門徒との出遇い、育てられ、反差別・非戦論を唱える。1910年に国家の「明治天皇暗殺事件」を捏造した「大逆事件」に連座・逮捕され、死刑判決を受ける(翌日、無期懲役に減刑)。のち、秋田刑務所に収監され自死。享年50歳。 |